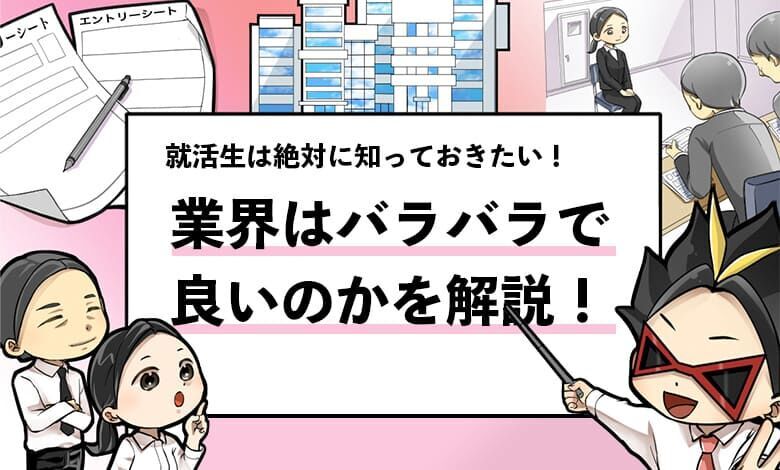
こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。
今回はエントリーする企業を選ぶ上で、業界はバラバラでも良いのか?
そんな就活生からの疑問に答えていきたいと思います。
実際に、僕も就活生の時は「何種類ぐらい業界を選択しても良いのか?」と悩みました。
結果的には、食品業界・化学業界・自動車業界・小売業界(コンビニ本社)の4業界に絞り込んだのですが、この記事を通して、業界はバラバラで良いのか?
またバラバラにした場合に、どんな注意点やメリットがあるのか徹底解説していきます。
この記事1つ読めば、業界をバラバラに選択することについて理解できるので、ぜひ最後まで読み込んでもらえると嬉しいです!
自分は5つの業界バラバラに選んでいます!1つの業界に絞る必要はありませんか?
業界はそこまで絞り込む必要はないよ。自分の価値観に合う業界であれば、極論、どの業界をどれだけの数志望しようが問題はないからね。
- 就活で業界をバラバラに選択してもいいのか?
- 就活で業界をバラバラに選択する際の注意点
- 就活で業界をバラバラに選択するメリット
- 就活で業界をバラバラに選択するデメリット
- 就活で業界をバラバラに選択することに関してよくある質問
- 本記事の要点まとめ
就活で業界をバラバラに選択してもいいのか?

まず結論から話していきますね。
就活で業界はバラバラに選択しても問題ありません。
しかし、それぞれの業界ごとに「なぜその業界を選んだのか?」という業界を選んだ志望理由は答えられるようにしておく必要があります。
適当に企業を選び、その結果、業界がバラバラになってしまった。
そうすると、「なぜ◯◯業界を志望したのでしょうか?」という質問に答えられなくなるので、業界ごとに志望理由は答えられるようにしておくことは必須です。
ちなみに、業界を複数志望する最大のメリットは、志望企業の選択の幅を広げられることにあります。
人によっては「10社しかエントリーしていません」という人もいますが、それだと面接の場数も踏めないし、全落ちするリスクもある。
よって最低でも25社以上はエントリーすることをおすすめしています。
その際に業界バラバラでもいいとなれば、志望企業の選択肢が広がりますよね。
僕がいま就活生なら、逆求人サイトを活用して幅広い業界の企業からスカウトが届く仕組みをつくりますね。
これまで200以上のサイトを見てきましたが、利用するなら「キミスカ」一択です。
キミスカはスカウトが3種類にわかれているのが特徴で、企業の本気度を見極められます。

「ゴールド」と「シルバー」のスカウトのみ絞って対応することで、効率よく自分に合う企業を見つけられますよ。
業界を絞りきれないと悩んでいる人ほど、逆求人サイトで適性のある企業を見つける方法を試してみてくださいね。
なお、就活を7年以上研究してきた僕が心からおすすめできる就活サイトを厳選した記事も書いているので、合わせて参考にしてください!
» 【結局どれ?】僕が今就活生なら絶対利用するのはこの5つ!|100サイト以上から厳選!
各業界ごとに志望動機が明確であれば、業界はバラバラでも問題ないんですね。
そうだよ。僕の場合は、食品業界と化学業界に関しては、農学部だったからその知識を活かせる業界だとして志望。
自動車業界は愛知県在住で、かつ自動車が好きだったから志望。
小売業界のコンビニチェーンに対しては、個人的にコンビニが好きでよく利用しているから志望。このようにそれぞれ明確な志望理由があったんだよね。
就活で業界をバラバラに選択する際の注意点
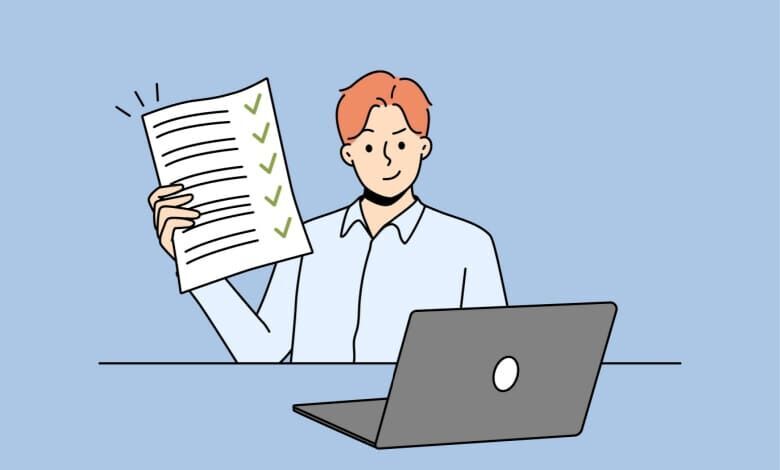
結論、就活では業界をバラバラに選択しても問題ありません。
ですが、先ほど解説したようにそれぞれ志望動機が明確である必要があったりと、業界をバラバラに選択する際には注意点もあります。
それをこの章では詳しく解説していくので、「バラバラに業界を選ぼうと考えている」という方は必ず目を通していってください。
【就活で業界をバラバラに選択する際の注意点】
- 各業界ごとに志望動機を明確にしておく
- 各業界ごとの業界研究に手を抜かない
- 企業選びの軸はブレないようにする
注意点① 各業界ごとに志望動機を明確にしておく
まず第一に、複数の業界を志望していても、それぞれの業界ごとに志望動機を明確化しておく必要があります。
僕の例で話すと、僕は自動車業界も志望していました。
その際、「なぜ農学部なのに自動車業界を志望しているの?」と面接官に聞かれて、答えられなかったら、志望度が低いとしてかなりマイナス評価される。
このあたりは面接官の立場に立てば、当然の話で、容易に質問が予測できます。
複数の業界を志望していると、「なぜ◯◯学部なのにこの業界を?」「なぜ◯◯学部なのにこの職種を?」といった質問がされるシーンが多々あるんですよね。
こうした面接官からの疑問を予測し、事前に対策する必要がある。
今回の場合で言うと、志望する各業界ごとに志望動機を用意しておかないと、そういう質問をされた時に詰みますよ。
注意点② 各業界ごとの業界研究に手を抜かない
次にバラバラに複数の業界を志望していても、1業界ごとに業界研究しましょう。
業界研究とは、「その業界を簡単に説明すると?」「その業界の特徴は?」「その業界の成長性は?」「その業界の将来像は?」といった様々な項目を分析し、理解することです。
業界の選択は、キャリア形成において超重要なんですよね。
なぜなら業界ごとに「将来性」や「儲かりやすさ(利益の出やすさ)」が違うから。
例えば、飲食業界を考えてみると、爆発的な将来性はなかなか予想しづらい。
更には利益率は低いので、儲かりにくい。
それゆえに人件費にお金を避けず、低賃金で長時間労働になってしまう企業が多くなります。
一方で、化学業界を考えてみると、爆発的な将来性もありえますよね。
更には利益率が高く、かつ参入障壁も高いので、儲かりやすいし安定している。
結果、社員に還元できて、ホワイト企業も多い業界となるのです。
このように業界によって将来性や儲かりやすさが異なるので、どの業界を選択してキャリアを形成していくのか十分に考えてみてください。
将来性や安定性があって儲かりやすい業界を選ぶのか?
それとも自分の興味を優先して業界を選ぶのか?
それを決めるためには業界研究が必須であり、業界特性を理解している人は、社会人になってからも転職で役に立ったりと良いことしかありません。
手を抜かないようにしてくださいね!
▼業界研究のやり方を解説した記事はこちら
» 【業界研究ノートの書き方】11個の必須要素によるまとめ方
▼業界研究に最もおすすめの本はこちら
注意点③ 企業選びの軸はブレないようにする
そして最後、業界をバラバラに選択する上での注意点は、業界はバラバラでも企業選びの軸はしっかりと設定することです。
企業選びの軸とは、文字通り、「企業を選ぶ上で自分が大切にする条件」のこと。
具体的に僕が就活生の時の話をすると、企業選びの軸としては、例えば「残業時間が月25時間以内」「40歳以上で平均年収が600万円以上」「自分が心から良いと思える商品やサービスを提供している」といった軸を設けていました。
業界はバラバラでも、こうした企業選びの軸は貫くようにしましょう。
そうすれば、仮に企業から「様々な業界を志望しているんですか?」という質問をされたとしても、「はい、ですがそれぞれの業界ごとに志望動機がそれぞれあり、かつ業界は違えど企業選びの軸は一貫しています。」と答えることができますからね。
業界はバラバラでも良い。
ですが、企業選びの軸はしっかりと設定し、ブラさらないようにすることは重要です!
なるほど!業界はバラバラに、複数選択したとしても、それぞれの業界ごとに志望動機を明確化することや、それぞれ業界研究を徹底すること、企業選びの軸は一貫することが重要になってくるんですね。
そうだよ。それらを押さえておけば、複数の業界をバラバラに選択しても、全く問題ないからね。
就活で業界をバラバラに選択するメリット

ここまで就活で業界をバラバラにしても良いことと、その際の注意点を解説していきました。
この章と次の章を使って、業界をバラバラに選択するメリットとデメリットを1度確認しておこうと思います。
僕が考えるに、就活で業界をバラバラに選択するメリットは大きく3つあります。
【就活で業界をバラバラに選択するメリット】
- エントリーする企業の選択肢が広がる
- 広い視野を持って業界研究することができる
- 途中で志望業界が変わった時に対応できる
メリット① エントリーする企業の選択肢が広がる
まず業界をバラバラに選択すると、エントリーする企業の選択肢が広がります。
僕は第一志望として食品業界を選んでいましたが、食品業界だけだと、僕が設定した企業選びの軸に合致する企業は倍率が高い企業ばかり。
すると、内定を獲得しにくいと予測できたんですよね。
その際に、自動車業界の知名度が低くて倍率も低いけど、労働条件の良い優良企業もエントリーすることでバランスを保つことができました。
このように業界の選択肢を増やすことで、当然ですが企業選びの選択肢も広がります。
あまりに広げすぎても逆に選ぶのが難しくなることもありますが、個人的には4〜5業界ぐらいに絞れば、ちょうど良いと考えています。
メリット② 広い視野を持って業界研究することができる
次に業界をバラバラに複数選ぶメリットは、広い視野を持って業界研究できること。
例えば、1つの業界に最初から絞っている人は、その業界以外を分析することをしない傾向にあります。
すると、実は志望していた業界がブラック企業の多い業界だったという事態になりかねません。
その点、複数の業界を志望することは、複数の業界を見ることに繋がり、広い視野を持って業界選びができるのは魅力ですね。
ちなみに僕が考えるホワイト業界とブラック業界、それぞれをまとめた記事も別で書きました。
「どの業界がホワイト企業が多いのかな?その理由はなぜだろう?」という疑問のある就活生はぜひ参考にしてくださいね!
» 【ホワイト業界ランキング14選】僕がおすすめするホワイト業界を紹介!
» 【ブラック業界ランキング】ブラックだと言われがちな業界は?
メリット③ 途中で志望業界が変わった時に対応できる
最後に、業界をバラバラに選択するメリットとしては、途中で志望業界が変わった時に対応できる点が挙げられます。
例えば、僕は食品業界を志望していて、食品業界に絞っているとしましょう。
就活を進める中で、「やっぱり食品業界は自分に合わないかも?もっと将来の起業に役立つようなスキルや知識が得られる業界の方が良いかもしれない」と考えてしまった。
その時に1つの業界だけに絞っていると、なかなか対応ができないですよね。
気持ち的にも1つに業界を絞ってやってきたのに、今更業界を変えるのは気が引けるし、業界研究のやり方もいまいち分からない。
一方で、業界研究をして複数の業界を見ることができていれば、「将来の起業に役立つとしたら、IT業界の広告代理店あたりが良いかも」というように別の選択肢を持つことができます。
またそもそも志望業界が広ければ、「この業界は選択肢から外そう」という調整も可能ですよね。
軌道修正できる面でも、就活で複数の業界を志望するのはメリットがあります。
(もちろん先に紹介した注意点は押さえた上で、ですけどね!)
なるほど!就活で業界をバラバラに選択することは、こうしたメリットがあるんですね。
そうだよ。次に紹介する「企業から志望度の低さを指摘される可能性がある」といったデメリットもあるけど、メリットも大きい。
就活で業界をバラバラに選択するデメリット

一方で、就活で業界をバラバラに選択することにはデメリットもあります。
僕が考えるデメリットは大きく2つですね。
【就活で業界をバラバラに選択するデメリット】
- 企業から志望度の低さを指摘される可能性がある
- 業界研究と志望業界の設定に時間がかかる
デメリット① 企業から志望度の低さを指摘される可能性がある
最も大きなデメリットは、企業から志望度の低さを指摘される可能性があること。
あなたが食品企業の面接官だとして、「5業界を志望しています」という就活生と、「食品業界に絞っています」という就活生では、後者の方が食品業界への志望度が高いと判断しますよね。
このように、複数の業界を志望し、それがバラバラだと企業側から「適当に業界を選んでいるのではないか?」という疑問を持たれる可能性があります。
ですが、この疑問はうまく対処することができるので、実際に僕が他社の選考状況を聞かれた時に答えていた回答方法を共有しますね。
他社の選考状況を聞かれた際の回答例
面接官「藤井さんは、食品業界だけ志望している?」
僕「いえ、食品業界を含め計4業界を志望しています。それぞれ食品業界、化学業界、自動車業界、コンビニに絞った小売業界です。」
面接官「なるほど、他の企業から内定が出たらどうするの?」
僕「志望する4業界の中で最も志望度が高い業界が食品業界でして、その中でも貴社への志望度が最も高いため、貴社の選考結果が出るまで他社から内定が出ても保留致します。」
このように複数の業界を志望していても、その中で貴社の属する業界が第一志望ですよ。
その中でも、貴社が第一志望ですよと伝えれば、志望度が低いと認識される可能性はありません。
ずるいかもしれないですが、僕はすべての企業に貴社が第一志望ですと答えていました。
就活において、自分の性格や価値観、実績など「自分に関する情報」を偽ることはNGです。
(適性をお互いに判断して入社後のミスマッチがないよう採用するのが就活なので、自分の情報で嘘をついてしまうと入社後のミスマッチに繋がるから!)
しかし、志望度に関しては優しい嘘ですよね。
わざわざ「貴社は第47志望です」とか言う人いないでしょ...。笑
» 【他社の選考状況の答え方は?】"超おすすめの回答例"を共有!
デメリット② 業界研究と志望業界の設定に時間がかかる
続いて、業界をバラバラに複数選択するデメリットとしては、業界研究と志望業界の設定に時間がかかる点が挙げられます。
ですが、これに関しては「時間をかけるべきこと」なので、デメリットではなく、ここは労力と時間をかけていきましょうということになります。
途中でも解説したように、業界の選択はキャリア形成にとって大きな分岐点。
だからこそ業界研究と志望業界の設定には時間をかけるべきです。
なるほど!たしかにメリットとデメリットの両方を見た時に、複数の業界を選ぶことにはメリットが大きいと感じますね。
そうなんだよ。無理に1つの業界に絞る必要はない。複数の業界を志望していることが企業に伝わっても、答え方でカバーできるからね。
就活で業界をバラバラに選択することに関してよくある質問

ここまでの解説で答えきれなかった質問に、この章で回答していきます。
業界選択に迷っている就活生はぜひ参考にしてくださいね!
質問① バラバラではなく業界を絞る場合はどうすれば良いですか?
業界を絞る場合、まずは世の中にどんな業界があるのか、まず広い視野を持ってから徐々に狭めていくことをおすすめします。
なぜなら途中でも解説したとおりで、業界によって将来性、安定性、儲かりやすさなどが大きく異なるからです。
ちなみに僕がおすすめの業界の絞り方は以下の6ステップです。
詳しくは別記事で解説しているので、業界を絞りたいという方は参考に!
【就活での業界の絞り方】
- 大学での専攻と関連する業界を加えるか考える
- 自分が熱狂できる業界があればそれを加えるか考える
- 自分が求めるのは「働きやすさ」か「成長か」を考える
- “働きやすさ特化”の場合はホワイト業界を理解して加える
- “成長特化”の場合は成長業界を理解して加える
- ブラック業界を理解して嫌なら排除する
▼6ステップの詳しい解説はこちら
» 【就活での業界の絞り方は6ステップ】失敗しない方法を解説!
質問② 自分が属する学部に合わせて業界は選ぶべきですか?
「◯◯学部に属しているから、◯◯業界を志望しないといけない」ということはありません。
僕は農学部に属していたので、食品業界や化学業界を志望することと相性は良い。
ですが、同時に自動車業界も小売業界も受けていて、自動車業界の企業からも小売業界の企業からも内々定を獲得できました。
企業側も新卒を選ぶ時に、どの学部に属しているかよりも、そもそもその就活生の人柄、性格、ポテンシャルの方を重視します。
(この点は中途採用との大きな違いと言えますね、中途採用の場合は即戦力を欲する企業が多いので、元々もどの業界に属していたか、前職の経歴を重要視するので)
よって学部に縛られず、業界選択していきましょう!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
就活では、業界を選択する必要があり、これまで業界選択のやり方なんて、だれからも教わってないので困りますよね...。
ですが、何度も言うように業界の選択は、自身のキャリアを大きく左右します。
個人的には、儲かりにくく、労働条件の悪い企業が多い業界への就職はおすすめしません。
広い視野を持って業界研究をするためにも、1つの業界に絞らず、バラバラでも良いので複数の業界に目を向けてみてください。
その際に、この記事が役に立てば嬉しい限りです!
(今は16時ですが、今日は8時から近くのスタバにこもってこの記事を書いてますw)
それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょうか。
【本記事の要点】
- 就活で業界をバラバラに選択しても良い。
- 業界をバラバラに選択する際は、各業界ごとに志望動機を明確化しておくこと、加えて各業界ごとの業界研究に手を抜かないこと、企業選びの軸はブレないようにすることに注意する必要がある。
- 就活で業界をバラバラに選択するメリットは複数あり、「エントリーする企業の選択肢が広がる」「広い視野を持って業界研究することができる」「途中で志望業界が変わった時に対応できる」が大きいところでは挙げられる。








