
【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
大学職員を目指す人も、この本に書いた面接対策や、民間に切り替える際の企業の探し方などがタメになると思います!!
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
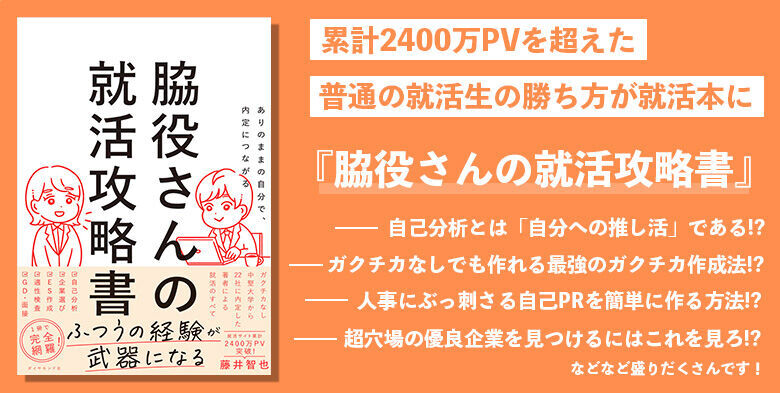
それでは本題に入っていきますね!
就活生や転職を検討している人の中には、大学職員を目指してる人もいますよね。
ただネットで「大学職員」と入れると、予測変換で「大学職員 やめとけ」というネガティブなワードが出てくるので、不安を感じた人も多いかと思います。
そこで今回、実際に大学職員として働いていた人に本音を語ってもらいます!
実は僕が経営している会社の社員の中に、前職が公立大学の職員という方がいるので、この記事は丸々その社員さんに書いてもらいました。
元大学職員だからこそわかるリアルな部分が盛り沢山の記事です。
ここでしか読めない内容ばかりなので、ぜひ最後まで読んでくださいね!

ちなみに、最近就活生から「早く内定が欲しい」と相談されることが多いです。
心の余裕を持つためにも、まず1社目の内定の獲得は本当に有効。
(僕がカゴメからの内定を獲得したのも、「カゴメに落ちても◯◯に入社すれば良いからな」と余裕があったから、面接で緊張せず攻めれたんですよね!)

僕が今就活生なら、「キミスカ」を筆頭とした大手のスカウトサイトに登録して、スカウト経由の内定を取りにいきますね。
現状最も効率的だと考えてます!
特に公務員狙う場合、民間企業の内定も「保険」として取っておくと心の余裕ができるので、スカウトは届く仕組みを作っておくのが最強です!
早期内定の獲得方法について、詳しくは下記の記事に立ち回りをまとめておいたので、そっちの方が気になるという方はぜひ読んでみてください!
» 【カゴメ内定者が解説】"超"早期内定を獲得するための動き方!
大学職員のリアルな働き方が把握できそうですね!
まさにそうなんだよ!口コミサイトやネット上の憶測記事ではなく、現場を経験した人のリアルな声だからね!
- 「大学職員はやめとけ」って本当?【元大学職員の本音】
- 「大学職員はやめとけ」と言われる理由
- 元大学職員の目線で考える「大学職員に向いている人の特徴」
- 元大学職員が思う「大学職員に向いていない人の特徴」
- 元大学職員が教える「大学への就職方法」
- 【必読】大学職員は人気業界なので選考難易度も高い
- 大学職員から広がるキャリアの可能性
- 大学職員になるメリット【4選】
- 大学職員になるデメリット【4選】
- 大学職員を目指している人からよくある質問
- 本記事の要点まとめ
「大学職員はやめとけ」って本当?【元大学職員の本音】

みなさんはじめまして!
就活マンが経営する株式会社L100の藤九(ふじく)と申します。
今回、就活マンよりご依頼をいただき記事を書かせていただきました。
他の記事や口コミサイトには載っていない”大学職員のリアル”を余すことなくお伝えしていくので、ぜひ最後までよんでもらえると嬉しいです!
早速ですが、「大学職員はやめとけ」という声に対する私の本音をお伝えします。
あくまで私個人の意見ですが、大学職員はかなりおすすめの職種です!
私は県や市が母体となる「公立大学」で勤務していたのですが、土日は基本的に休みでしたし、無理な残業などを強いられることも一切ありませんでした。
何より、キャリアセンターという学生に近い立場で働けたことも大きかったですね。
4年ほど働いた上で、今の会社に転職していますが、決してネガティブな理由でやめたわけではなく、あくまで自分自身のキャリアアップのための転職でした。
(就活マンこと藤井さんのビジョンに共感したのもめちゃくちゃデカイです!)
ただ、この記事を読み進める上で必ず理解しておいてほしいのは「あくまで私(藤九)自身の意見や経験である」という点です。
決して大学職員全てに共通するわけではないので、その点はご理解ください。
大学の規模・設置区分・部署などによって働き方は大きく異なる
大学職員といっても、大学の規模や設置区分、部署によって働き方は様々です。
国が設置する「国立大学」、県や市など自治体が設置する「公立大学」、学校法人などが設置する「私立大学」といったように、母体も異なることから、大学それぞれで全く別の企業と考えた方がいいと思います。
また、学生数が数百名程度の小規模大学もあれば、数万人規模の大規模大学もあるため、部署の種類や担当領域も大学によって大きく異なります。
例えば、私は学生数1000名程度の公立大学だったので、就職支援を行うキャリアセンターには4名程度の職員しかいませんでした。
担当業務も合説の企画や学生面談、統計など非常に幅広かったんですが、大規模大学になるとこの担当領域が細分化されてたりします。
私は土日祝は完全に休みでしたが、大学によっては月1回程度の土曜出勤がある場合もあるなど、働き方についても千差万別です。
つまり「大学職員=みんな同じ働き方」とは絶対になりません。
むしろ大学によって全く働き方が異なるという認識でいてくださいね!
これは営業職や事務職でも同じだよね。職種は一緒でも、企業によって働き方は全く異なるわけだから、大学職員も同じというわけだよ!
「大学職員はやめとけ」と言われる理由

ネットで大学職員を検索すると、予測変換で「大学職員 やめとけ」と表示されるわけですが、そもそもなんでやめとけと言われているのか、その理由が気になる人も多いですよね。
そこでこの章では、大学職員はやめとけと言われる理由についてお伝えします。
私自身の経験も含めて、やめとけと言われるのは以下の理由が原因かと。
【「大学職員はやめとけ」と言われる理由】
- 関わる相手の立場が幅広く人間関係が難しいから
- 一般的な事務職よりハードな業務が多いから
- 転職の際に市場価値の高い人材になりにくいから
- これから大学経営は厳しくなっていくことが予想されるから
理由① 関わる相手の立場が幅広く人間関係が難しいから
大学職員の場合、主に業務で関わるのは「同僚」「学生」「教員」になります。
それぞれ全く立場も年齢層も異なるため、相手に合わせたコミュニケーションも必要となり、人間関係に悩む人も多いんですよね。
また、大学職員は教員や学生を陰で支える縁の下の力持ち的な存在なので、時には都合のいいように使われるような場面もあり、正直ストレスは多い仕事だと思います。
特に大学教員は研究第一な人もいれば、大学経営に積極的に参加する人、教育を大切にする人など多種多様であり、正直、関わり方が難しいケースもあります。
私が働いていた大学でも、教員との関係性に悩んで退職した人もいますからね。
こうした”関わる人の特殊性や幅広さ”は、大学職員はやめとけと言われる一因だと考えられますね。
理由② 一般的な事務職よりハードな業務が多いから
「大学職員=事務職」というイメージを持つでしょうが、一般的な事務職とは違った大学ならではの業務も多々あります。
そしてこれが結構ハードだったりするんですよね。
例えば入試関係の部署であれば高校への宣伝活動もありますし、毎年行われるセンター試験や前期後期試験などの時期は非常に忙しくなります。
取り扱う情報や書類も厳密に管理する必要があるなど、神経を要する仕事です。
また、学生生活を支援する部署であれば奨学金に関する業務や学生寮の管理、部活動やサークル活動の支援、学生の相談対応など、ハードな業務が目白押しなんですよね。
こうした”大学ならではのハードな業務”がある点も、事務職でありながら大学職員が大変と言われる理由かと思います。
理由③ 転職の際に市場価値の高い人材になりにくいから
大学職員が取り扱う業務については、先ほどお伝えしたような大学ならではの専門的な業務も多いことから、他の企業等では活用しにくい側面があります。
(中には経理や財務や総務といった一般事務業務もありますよ!)
そのため、いざ転職となった際に、他社に求められるような市場価値の高い人材にはなりにくいというのは少なからずあるかと思います。

とはいえ、私自身は大学キャリアセンターにおける新卒就活支援の経験、知識があったからこそ今の会社(株式会社L100)で新卒採用支援に携われているのも事実なので、これはその人次第によるというのが私の持論ですね。
理由④ これから大学経営は厳しくなっていくことが予想されるから
少子高齢化や大学全入時代の全盛期を迎え、今後は学生の確保が難しくなるため、学生の争奪戦が激しくなるのは間違いありません。
それを見据えて経営統合する大学も増えてきましたし、すでに経営ができなくなった大学も毎年複数現れています。
対策として、海外から留学生の受け入れを始めたり学部を減らすといった対応をしている大学も増えていますが、大学経営が厳しくなるのは間違いないかと。
こうした将来性の不安から、大学職員を敬遠するのは一つの考え方だと思います。
私立はもちろん、国立や公立であっても将来が約束されているわけではないので、この点は「大学職員やめとけ!」の中で、一番意識しておくべき部分ですね。
たしかに大学経営は年々厳しくなっていますよね。
安定した業界とは言えないかもしれないね。お客様となる学生の母数自体が減っていくわけだからね。
元大学職員の目線で考える「大学職員に向いている人の特徴」

大学職員はやめとけと言われる理由について共有しました。
ではこうした理由なども参考にしながら、どういった人が大学職員に向いているのか、その特徴について元職員目線で解説したいと思います。
私が考える”大学職員に向いている人の特徴”は以下のとおりですね。
【大学職員に向いている人の特徴】
- ルーティンワークが好きな人
- 学生の成長や教育に興味がある人
- 教員や学生など幅広い立場の人と関わるのが苦じゃない人
- 自分自身は目立たず縁の下の力持ちとして働くのが好きな人
特徴① ルーティンワークが好きな人
大学では1年のルーティンを繰り返す業務が基本となります。
4月は入学式、8月は前期試験、3月は卒業式など1年間の行事予定は毎年だいたい決まっているため、行う業務もルーティンワークが多いんですよね。
もちろん新しい事業や取り組みを行う場面もありますが、私自身、4年間働く中でそういった機会は数える程度でした。
よって、毎年同じルーティンワークを行うのが好きな人には合う仕事だと思います。
特徴② 学生の成長や教育に興味がある人
大学における主役はやはり学生です。
大学職員の業務も常に「学生ファースト」と言われており、学生向けのサービスが大半を占めています。
よって、学生の成長や教育に興味がある人ほど、そうした業務に対するモチベーションも高く保つことができるんですよね。
こうした視点から、向いている人の特徴の一つとして挙げさせていただきました!
特徴③ 教員や学生など幅広い立場の人と関わるのが苦じゃない人
大学職員は同僚や学生、教員など幅広い立場の人と関わります。
学生や教員といった全く立場の異なる人と関わるため、それぞれに合わせた関わり方が求められる仕事であり、こうした配慮が苦じゃない人でないと務まらないかと。
また、部署によっては学外の人と関わる機会が多いケースもあります。
私はキャリアセンター勤務だったので、企業の採用担当者やナビ会社の人などとも交流する機会が多々ありました。
このように、幅広い立場の人と関わることが好きな人には向いていいる仕事です。
特徴④ 自分自身は目立たず縁の下の力持ちとして働くのが好きな人
大学における主役はやはり学生と教員です。
大学職員はこの両者を支える存在であるため、大学職員自身が表に立って目立つ機会というのはほとんどありません。
こうした”縁の下の力持ち”としての働き方に魅力を感じる人は、大学職員という仕事が非常に向いていると思いますね。
意外とハッキリ向き不向きがわかる仕事ですね!
それだけ独自の仕事をしているからね。この内容を見て「合わないな〜」と感じるなら避けておくべきだと思うよ。
元大学職員が思う「大学職員に向いていない人の特徴」

先ほどの章では「大学職員に向いている人の特徴」をご紹介しました。
では逆に、どんな人が大学職員には向いてないのか、この章では不向きな人の特徴をお伝えします。
【大学職員に向いていない人の特徴】
- 新しい取り組みや挑戦をどんどんしたい人
- 飽きっぽい人
- 成果主義でないと納得できない人
特徴① 新しい取り組みや挑戦をどんどんしたい人
新しい取り組みや挑戦をしたい人には向かない仕事だと思います。
私が働いていた大学の場合、何か新しい取り組みをする際には事務局の決裁に加え、教員側の決裁や根回しなど、かなり労力を要することがほとんどでした。
もちろん改革に積極的な大学もあるとは思いますが、大学業界というのは比較的新しいことに取り組みづらい業界かと思います。
いわゆるベンチャー志向を持っている人には、物足りないかと。
特徴② 飽きっぽい人
先ほどもお伝えしたとおり、大学の業務は基本的にルーティンワークとなるため、毎年同じ業務を繰り返すことが基本です。
よって、飽きっぽい人にとってはすぐに業務に飽きてしまう可能性が高いと思います。
部署異動等があれば仕事内容が変わることもありますが、基本的には決まった業務を淡々とこなすことが求められる仕事です。
特徴③ 成果主義でないと納得できない人
大学職員の仕事は営業職などに比べると、どうしても成果が目に見えにくい仕事なので、成果主義による評価自体が難しい職種です。
よって、成果主義を求めている人には合わない仕事になります。
給与や役職も基本的に年功序列、経験年数に応じて段階的に上がっていくため、実力主義の世界ではありません。
(特に公的側面が強い国立大学や公立大学はその色が強いです!)
元大学職員が教える「大学への就職方法」

大学職員に向いている人や向いていない人の特徴について共有しました。
では次にこの章では、実際にどういった流れで大学職員に就職できるのか、その流れについて解説していきます。
前提として、大学職員への就職方法は設置区分によって流れが異なります。
そこで設置区分ごとに解説していきますね。
①国立大学への就職方法
まず国立大学についてですが、国立大学職員採用については、地区ごとの共通一次試験を受けた上、合格すれば希望する大学の二次試験を受ける流れとなります。
ちなみに一次試験は公務員試験に似た科目での教養試験、二次試験は大学ごとに異なりますが、面接試験などが主になっています。
【国立大学の採用試験の流れ】
- 各地区(北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州)で開催される共通一次試験を受験(複数地区の受験は不可)
- 合格すれば「第一次試験合格者名簿」に登載される
- 地区内の各国立大学法人等の二次試験を受験
- 合格すれば各法人で採用決定
参考:一般社団法人国立大学協会「国立大学法人等職員をめざす方へ」
https://www.janu.jp/univ/employment/saiyou/
②公立大学への就職方法
県立や市立といった”公立大学”の場合、国立大学のような共通一次試験はなく、各大学によって採用試験が実施されます。
そのため、採用試験の時期なども大学によって異なります。
ちなみに私が受けた公立大学の場合、一次試験が12月に実施され、最終結果が出たのは2月中旬頃でした。
試験の流れは以下のような感じです。
【私が受験した公立大学の試験の流れ】※あくまで一例です
- 書類提出(履歴書)
- 一次試験(公務員試験と同様科目による教養試験)
- 二次試験(グループワーク、小論文、個人面接)
- 内定
ほぼ公務員試験と同じ内容・流れでしたね。
大学によっては教養試験ではなく、SPIなどを実施する場合もありますが、やはり公立ということで公務員に似た試験となる傾向があります。
③私立大学への就職方法
私立大学の採用試験については、民間企業と同じ流れになります。
もちろん大学によって試験内容は異なりますが、採用試験の時期もだいたい就活の流れと同様であり、規模が大きい大学ほど新卒採用を実施しています。
【私立大学の採用試験の流れ】※あくまで一例です
- エントリーシート提出・書類選考
- 適性検査(SPIなど)
- 一次試験(グループワークや集団面接など)
- 二次試験(個別面接:管理職クラス)
- 最終試験(個別面接:役員クラス)
設置区分によって試験の流れが違うんですね!
対策内容も変わってくるから注意が必要だね。特に国立や公立は教養試験対策が必要となるから事前準備も必須だよ!
【必読】大学職員は人気業界なので選考難易度も高い

大学職員を目指している人に絶対に知っておいてほしいのは「大学業界は非常に人気のある業界」ということです。
実際、私が受けた大学は地方の小規模公立大学(学生数1000名程度)であり、知名度もかなり低い方ですが、私が受けた採用試験の倍率は124倍でした。
(124名受けて、受かったのが私だけという状況)
知名度の低い地方の公立大学でもこれだけ高倍率なわけですから、知名度や人気のある大学の場合、さらに倍率が高くなることも予想されます。
かなり狭き門である点は理解しておいてください。
人気業界を受けるのであればエントリー数を増やすことが重要
▼転職者向けの対策は以下の記事を参考にしてください!
» 転職を7年研究した僕が考える「ホワイト企業に転職するために必須の3ステップ」と年収も上げる戦略!
大学業界のような人気業界を受ける上で重要になるのは「エントリー数を増やして内定確率を高めること」ということです。
大学業界を受けると同時に、別業界の中堅・中小企業へのエントリー数を増やすことで内定確率を高め、精神的な余裕を持つことが大切なんです。
精神的な余裕がなければ、本命の試験でも焦ってしまいますからね。

ただエントリー数を増やすにあたり、求人を探すのはやっぱり面倒だし時間がかかる。
そこでおすすめするのが就活エージェントから求人を紹介してもらう方法。
就活エージェントとは、面談を通して、あなたに合った求人の紹介から選考支援までを一貫してサポートしてくれる無料サービスのこと。
人気業界を狙いつつ、中堅・中小企業はこの就活エージェントから紹介してもらって確実に内定を取りにいく戦略は効率的だと考えています。
僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」
サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。
ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。
就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。
またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。
運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。
就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。
▼就活エージェント利用者の声
初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑
— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020
なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな
もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう
(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)
逆求人サイトを併用することでさらにエントリーを効率化
就活エージェントと合わせて併用してほしいのが逆求人サイトです。
逆求人サイトとはプロフィールを登録しておくことで、企業側からスカウトが届く求人サイトのこと。

マイナビなどとは真逆で、企業→就活生の流れで連絡を取るようなサイトですね。
就活生はプロフィールを登録したらスカウトを待つだけなので、気になる企業からオファーがあったときだけ連絡を返せばOKです。
基本放置なので、企業候補を効率的に増やしたいなら活用しない手はありません。
利用前は怪しく感じるかもしれませんが、意外と大手からもオファーは届きますし、同サイト経由で内定を得ている人はかなり多くいますよ。
これまで200以上のサイトを見てきた僕のおすすめは、「キミスカ」と「ホワイト企業ナビ」の2つ!
どちらも無料で利用できるので、まだ使ったことがない人はぜひこの機会に登録してくださいね。

たしかに人気業界を受けるならエントリー数は増やしておきたいですね。
間違いないね。自分自身に余裕を持たせるためにも重要な対策だよ!
大学職員から広がるキャリアの可能性

「大学職員の仕事は専門性が高いから、転職がむずかしいのでは?」という不安を持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には大学職員としての経験が、意外なキャリアチャンスにつながるケースも多々あります。
この章では、大学職員から広がるキャリアの可能性について解説します。
【大学職員からのキャリアの選択肢】
- 人材業界や教育業界への転職がしやすい
- 大学内でのキャリアアップの道もある
- 他大学や関連機関へのキャリアパス
- 独立・起業という選択肢
①人材業界や教育業界への転職がしやすい
大学職員の経験は、とくに「人材業界」や「教育業界」と親和性が高いです。
たとえば、キャリアセンターに所属していた場合、就職支援や学生指導のスキルが評価され、人材紹介会社やキャリアコンサルタントとして活躍することも可能です。
実際、私も大学職員としての経験を活かして、現在は人材業界で働いています。
また、教育業界であれば、専門学校や学習塾の運営に携わるなど、学生支援の延長線上で新たなキャリアを築ける可能性があります。
【大学職員から活かせるスキル】
- 学生指導や進路相談の経験 → キャリアコンサルタント、人材紹介業
- 教育機関の運営ノウハウ → 専門学校・塾運営の管理職
- 統計やデータ管理のスキル → 人材マーケティング職
②大学内でのキャリアアップの道もある
大学職員として働き続ける中で、キャリアアップを目指す道も十分にあります。
規模の大きい大学では、管理職や役職付きのポジションに昇格する機会があるのも魅力です。
私立大学の場合、大学経営に関わる重要なポジションを任されることもあり、給与や待遇面での向上も期待できますね。
また、国公立大学では、自治体や国との調整役を担うなど、大学外部との交渉経験を積めることもあります。
【大学内でのキャリアアップ例】
- 管理職(課長、部長職)への昇進
- 新規事業や大学改革プロジェクトのリーダー
- 大学外部との連携窓口としての役割
③他大学や関連機関へのキャリアパス
大学職員としての経験を活かして、他大学や関連機関に転職する道もありますね。
たとえば、海外の大学で働くという選択肢も考えられます。
国際的な大学での経験は、自身のキャリアの幅を大きく広げてくれます。
また、大学関連の機関(学会事務局や研究機関など)への転職も視野に入れられます。
こうした環境では、より専門性の高い業務に携わることができ、専門知識をさらに深められるのが魅力です。
【大学職員からのキャリアパス例】
- 海外大学や国際教育機関での勤務
- 学会や研究機関の運営スタッフ
- 教育関連のNPOや公益財団法人への転職
④独立・起業という選択肢
大学職員として得た経験を活かして、独立や起業を目指す人も少なくありません。
たとえば、教育コンサルティング会社を立ち上げたり、キャリア支援サービスを提供するビジネスを展開するなど、大学職員時代のスキルやネットワークを活用する形です。
私自身も現在、就職支援やキャリアに関する事業に携わっていますが、大学職員時代の経験が大きな財産となっています。
教育や人材に関する知見は、独立しても十分に通用する強みになりますよ!
大学職員って、意外とキャリアの幅が広いんですね!
一見限定的に見えるけど、工夫次第でいくらでも広がるんだよ。
大学職員になるメリット【4選】

この記事を読んでいただいている方は、大学職員という職業に興味を持っている方ばかりだと思います。
そうした方々は「大学職員になるメリット」も気になりますよね。
そこでこの章では、実際に大学職員として働いていた私が感じた”働くメリット”についてお伝えしたいと思います。
主に以下の4点が大学職員のメリットですね。
【大学職員になるメリット】
- 大学の規模によっては高年収が期待できる
- 経営の安定性が高い
- 売上やノルマなど数字に追われることはない
- スケジュールが決まっているので自分自身のスケジュールも立てやすい
- 学生の教育に携われるというやりがいがある
メリット① 大学の規模によっては高年収が期待できる
大学の設置区分や規模によって異なりますが、大学によっては職員でも高年収を期待できる場合があります。
特に首都圏の大規模私立大学などは給料が高いイメージですね。
上記を見てもわかるとおり、私立大学の方が平均年収が高くなっています。
他業界と比べてみても、平均以上であることは間違いないため、待遇面はそれなりに良い職業です。
メリット② 経営の安定性が高い
国立大学であれば国、公立大学であれば自治体などが運営費を補助しており、私立大学にも各種補助等が存在するため、民間企業に比べて経営の安定性は高いです。
また、少子化の流れはありますが、大学に入学する割合自体が高まっているため、しばらくは安定的に経営できる大学が多いかと思います。
とはいえ、地方の小規模私立大学などを中心に知名度や人気のない大学については、徐々に経営が厳しくなっているのも事実なので、この安定性という面においては、大学によって異なることを理解しておいてください。
メリット③ 売上やノルマなど数字に追われることはない
大学職員には営業活動等がないので、基本的にノルマは存在しません。
部署によっては数字を求められる場合(入試関係→受験者数|就職関係→就職率など)もありますが、それが給料に反映されるわけではないので、そんなに大きなプレッシャーに感じることもないかと。
基本的に「大学職員=事務職」という認識は間違いないので、数字に追われる仕事に抵抗感がある人にとっては、大きなメリットかと思います。
メリット④ スケジュールが決まっているので自分自身のスケジュールも立てやすい
大学は年間スケジュールが決まっており、だいたい毎年同じようなスケジュールで業務も回っていくため、自分自身のプライベートなスケジュールも立てやすいです。
実際、私も繁忙期と閑散期を考えながらプライベートの予定を考えていたので、事前に計画も立てやすく、その点は働きやすさに直結していましたね。
メリット⑤ 学生の教育に携われるというやりがいがある
社会人を目の前にした大学生の教育に携われるというのは、大学職員にしか経験できないやりがいですよね。
特に私は就職支援担当だったので、人生を左右する就職という責任感を感じる一方、日々の仕事のやりがいや学生からの感謝を感じる機会も多く、やりがいを感じられる仕事だという実感がありましたよ!
スケジュールはたしかに立てやすい仕事ですよね。
だいたいのスケジュールが決まっているからね。ワークライフバランスは比較的取りやすい仕事だね。
大学職員になるデメリット【4選】

どの仕事にもメリットがあればデメリットもあります。
それは大学職員も例外ではないので、この章では私が感じたデメリット面についてお伝えしていきます。
私自身や私の同僚の意見も含め、大学職員になるデメリットは以下のとおりです。
【大学職員になるデメリット】
- 同じ仕事の繰り返しなので飽きやすい
- 身につくスキルが限定的
- 新しい取り組みに挑戦しづらい
- 成果が見えにくいのでモチベーションの維持が大変
デメリット① 同じ仕事の繰り返しなので飽きやすい
やはり毎年基本的に同じ仕事を繰り返すので、どうしても飽きてしまいますね。
もちろん違う業務が発生するケースもあるんですが、ほとんどの業務は前年踏襲で同じように進めていくので「またこれか」といった感情は生まれてしまいます。
淡々と目の前の業務をこなしていきたい人にとってはメリットかもしれませんが、仕事に刺激を求めていたり、日々違った仕事をしたい人には大きなデメリットです。
デメリット② 身につくスキルが限定的
大学職員はルーティンワークが基本なので、身につくスキルは限定的です。
私の場合は就職支援の部署ということもあり、事務スキル以外にも学生面談であったり新卒採用に関する知識が身につきました。
(そのおかげで今は人材業界で働けています!)
しかしこれは配属された部署によって大きく左右される部分です。
例えば財務系の部署にいけば経理の知識や経験は積めますが、大半の部署で身につくのは基本的な事務スキルのみとなるため、正直、転職市場でもあまり評価されづらいのではないかと思いますね。
デメリット③ 新しい取り組みに挑戦しづらい
大学によって異なりますが、やはりまだまだ大学業界は保守的な業界だと思います。
そのため、新しい取り組みなどにも消極的な場合が多く、特に教員は研修や授業で非常に忙しいので、新しいことをしたがらない傾向にありました。
教員も当然決裁権を持っているので、そこで止められることもしばしば。
私も就職支援に関していろんな提案をしてきましたが、採用されたのはほんの一部であり、根回し含め、かなり労力が必要でしたね。
デメリット④ 成果が見えにくいのでモチベーションの維持が大変
数字に追われないというメリットがある反面、日々の業務の成果が目に見えにくいのも事実なので、人によってはモチベーションの維持が大変だと思います。
私の場合、就職支援の部署だったので、学生の就職先が決まれば学生からお礼を言ってもらえたり、最終的な就職率で成果が見えたりはしましたが、これは就職支援の部署だから感じられたことです。
特に学生と関わらない部署については、学生からお礼を言われたりする機会もないため、大学職員としての成果が感じられにくいと思いますね。
メリットでありデメリットとなる部分がいくつかありますね。
結局は人それぞれの価値観による部分が大きいね。
大学職員を目指している人からよくある質問
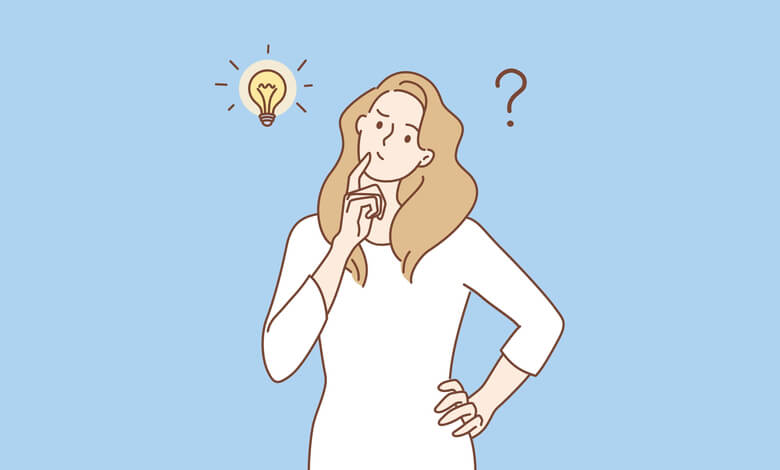
私が大学職員として働いていた際、就職支援の部署にいたこともあって、実際に大学職員を目指している学生から質問される機会も多かったんですよね。
そこでこの章では、大学職員を目指している人からよくある質問と、それに対する回答を共有したいと思います。
大学職員を目指している人はぜひ一度目をとおしてくださいね。
【大学職員を目指している人からよくある質問】
- 大学職員の仕事内容はどんなものがありますか?
- 国公立大学と私立大学はどちらがおすすめですか?
- 学生の保護者対応って大変ですか?
- 繁忙期はありますか?
- 大学で働く上でおすすめの部署はありますか?
質問① 大学職員の仕事内容はどんなものがありますか?
どの会社にもあるような事務業務と大学ならではの事務業務がありますね。
大学の規模や設置している学部学科によって異なる部分はありますが、例えば私が働いていた大学だと以下のような業務がありました。
【一般企業にもあるような事務業務】
総務、財務、経営管理、人事、採用など
【大学ならではの事務業務】
入試関係(入試広報や入試管理)、教務関係(履修管理など)、学生生活関係(奨学金、学生寮管理、部活動サークル管理、インカレなど)、就職関係(学生面談、学内説明会の企画運営、各種統計業務など)
質問② 国公立大学と私立大学はどちらがおすすめですか?
一概には言えず、これは人によるかと思います。
例えば安定志向で公務員などにも興味がある人の場合は国公立大学、民間企業と併願したい場合は私立大学といった形で、それぞれによって向き不向きがあります。
重要なのは、それぞれの違いを事前に把握しておくことです。
大学職員は人気業界のため、別の大学に転職するのもかなり難易度が高くなることから、受ける大学のことは徹底的に調べてくのが重要かと思います。
質問③ 学生の保護者対応って大変ですか?
これは部署によりますね。
例えば私の場合、就職支援の部署だったので基本的に保護者と関わる機会は少ない方でしたが、たまに保護者から学生の就職状況を直接聞かれることなどはありました。
また、奨学金などお金を取り扱う部署については、保護者対応が多い傾向にあります。
中学や高校に比べれば、大学生は大人なので保護者対応の数は少ないですが、やはり教育機関なので保護者対応しないといけない場面はありますね。
質問④ 繁忙期はありますか?
これも部署によって異なりますが、特に3月と4月はどの大学も繁忙期ですね。
3月であれば卒業式や入試、入学に向けた準備などがあり、4月は入学式など新入生の受け入れがあるため、2月後半〜ゴールデンウィークくらいまでは毎年どの部署も慌ただしく働いていました。
逆に8月後半〜9月などは夏休みに入るため、学生対応が多い部署などは比較的業務に集中できるかと思います。
質問⑤ 大学で働く上でおすすめの部署はありますか?
適性や向き不向きは大前提として、私は就職支援系をおすすめしますね。
学生と関わる機会はもちろん、企業の人事担当者と関わる機会も多いため、幅広い関わりが生まれますし、就職率といった数字の面でモチベーションも保ちやすいかと。
また、就職支援に関わらず、やはり学生に関わる部署は魅力的だと思います。
せっかく大学職員として働くわけですから、民間企業で経験できるような事務業務だけではなく、大学職員ならではの業務を経験できる方がやりがいにも繋がりますよ!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!
私自身が持っている大学職員の経験や知識について、余すことなく全てこの記事でお伝えさせていただきました。
私は転職した身ですが、大学職員という仕事は本当に好きでした。
就職支援を通じていろんな学生と関われましたし、就職先が決まった時の喜びややりがいは本当に大きなものでした。
ただ冒頭でもお伝えさせていただいたとおり、この記事の内容は「あくまで私(藤九)自身の意見や経験」であり、決して大学職員全てに共通するわけではありません。
私が大学職員という仕事を好きになれたのは、運が良かっただけかもしれません。
この記事だけでなく、いろんな立場の方やいろんな情報を精査した上で、大学職員という仕事を目指すかどうかを考えていただければと思います。
そしてこの記事が少しでもそのお役に立てれば幸いです。
【本記事のまとめ】
- 大学職員はやめとけという声については、結局人による部分が大きい。
- 大学職員はやめとけと言われる理由は「関わる相手の立場が幅広く人間関係が難しいから」「一般的な事務職よりハードな業務が多いから」「転職の際に市場価値の高い人材になりにくいから」「これから大学経営は厳しくなっていくことが予想されるから」などである。
- 大学職員に向いている人の特徴は「ルーティンワークが好きな人」「学生の成長や教育に興味がある人」「教員や学生など幅広い立場の人と関わるのが苦じゃない人」「自分自身は目立たず縁の下の力持ちとして働くのが好きな人」など。
- 逆に向いていない人の特徴は「新しい取り組みや挑戦をどんどんしたい人」「飽きっぽい人」「成果主義でないと納得できない人」などである。
- 大学職員は人気業界なので、エントリー数を増やすことで内定獲得率を高めるのが重要。








