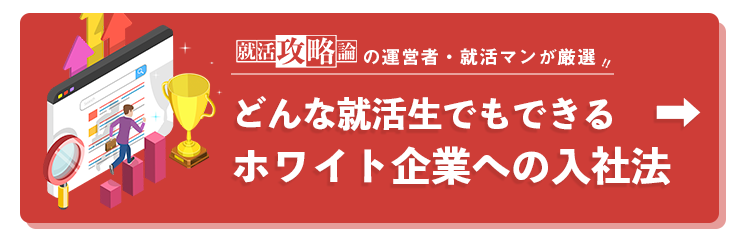【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
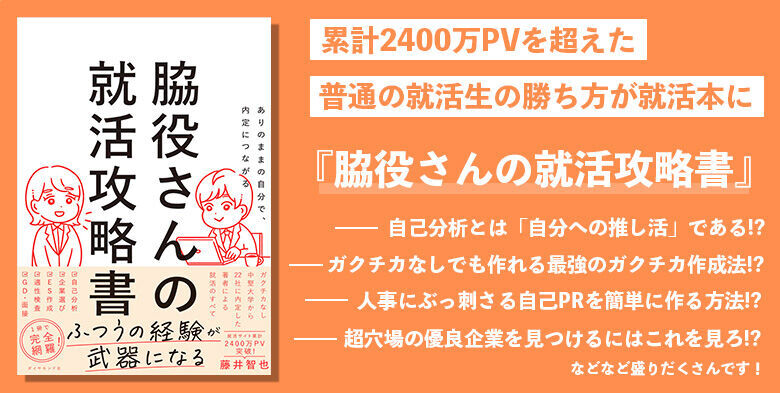
それでは本題に入っていきますね!
今回は、ビルメンの年収や就職偏差値をランキング形式でご紹介します。
ビルメンの仕事はルーティーンワークが多く残業も比較的少ないため、安定した職業といわれています。
そんなビルメンが気になる就活生も多いでしょう。
そこで、今回はビルメンの就職偏差値や年収のランキングに加え、ビルメンで働くメリット・デメリットをお伝えします。
ビルメンに興味のある方はぜひ参考にしてくださいね。
趣味の時間を大切にしたいので、ビルメン業界に興味があります!
会社によっても働き方が異なるし待遇も変わるから、本記事できちんと確認しておこう!
- ビルメンの就職偏差値ランキング
- ビルメンの年収ランキング
- ビルメンの売上ランキング
- そもそもビルメン(ビルメンテナンス)とは?
- ビルメンの仕事は主に施設管理業務
- ビルメンは系列系と独立系で待遇が異なる
- ビルメンの平均年収はいくら?
- ビルメンに就職するメリット
- ビルメンに就職するデメリット
- ビルメンへの就職に向いている人の特徴
- ビルメンへの就職に関して有利に働く資格一覧
- ビルメン業界の現状と将来性
- 本記事の要点まとめ
ビルメンの就職偏差値ランキング

ではさっそく、ビルメンの就職偏差値ランキングを見ていきましょう。
就職偏差値とは、その企業への就職難易度を数値化したものです。
(エントリー者の学歴の高さや倍率によって就職偏差値は決定されます)
【就職偏差値:60】
三井不動産ビルマネジメント・三菱地所ビルマネジメント
【就職偏差値:59】
世界貿易センタービルディング・三菱地所プロパティマネジメント・三井不動産住宅リース
【就職偏差値:58】
NTTファシリティーズ・第一ビルディング・東京流通センター
【就職偏差値:57】
東京海上日動ファシリティーズ・サンシャインシティ・郵船不動産
【就職偏差値:56】
東京ビッグサイト・ザイマックス・三菱地所リテールマネジメント
【就職偏差値:55】
野村ビルマネジメント・ららぽーとマネジメント
【就職偏差値:54】
アトレ・三井不動産住宅サービス・三菱地所藤和コミュニティ・TOC
【就職偏差値:53】
野村リビングサポート・東神開発
【就職偏差値:52】
アサヒファシリティーズ・ファーストファシリティーズ・住友不動産建物サービス
【就職偏差値:51】
大和ライフネクスト(旧コスモスライフ)・長谷工コミュニティ
【就職偏差値:50】
東急コミュニティ・日本ハウジング・三井ホームエステート
【就職偏差値:49】
伊藤忠アーバンコミュニティ・東京不動産管理
【就職偏差値:48】
長谷工ライブネット・MIDファシリティマネジメント
【就職偏差値:47】
JR東日本ビルテック・東急ファシリティサービス・大京アステージ
【圏外】
日本管財
引用:就職偏差値ランキング委員会「ビルメンテナンス業界の就職偏差値ランキング」
就職偏差値トップ2は、三井不動産ビルマネジメントと三菱地所ビルマネジメントでした。
どちらも不動産の系列系ビルメンであり、親会社から仕事がまわってくるため非常に安定しているといえるしょう。
【必見】ビルメンの内定獲得率を高める必須対策!
ビルメンは事業や年収の安定性から、知っている人は知っている穴場な業界です。
ただ穴場ではあるものの、就職偏差値を見てもわかるとおり、決して難易度が低い業界というわけではありません。
人気の高いビルメンを受けるのであれば、内定獲得率を高めるためにも効率よく就活を進めていく必要があるでしょう。
就活を7年以上研究してきた僕としては、「自分に合う企業の持ち駒を増やしつつ、プロに選考対策をサポートしてもらう」がいちばん効率のいい就活法だと考えています。
これまで200以上のサイトを見てきた中でも、とくに有益なのが、「キミスカ」と「
ミーツカンパニー就活サポート」 の2つ。
この2つを活用して持ち駒を増やしつつ、プロのアドバイザーにサポートしてもらいながら選考を進めましょう。
@Kimisuka1
— shi*26卒 (@Ooo_river_) January 17, 2023
キミスカさん経由でつながった企業さんから初めての内定をいただきました😭ありがとうございます😭今後もお世話になります…!
企業探しも選考対策も、ひとりで行うより圧倒的に質の高いものになります。
本気で内定獲得率を上げたいなら、上記の2サイトはいますぐ登録しておいてくださいね。

ちなみに、以下の記事で「僕がいま就活生ならこれを使う!」という就活サイトを厳選して紹介しています。
心からおすすめできるサイトだけをまとめているので、ぜひ参考にして活用してくださいね。
トップ層は、不動産系のビルメンなんですね!
親会社が不動産系だと非常に安定しているため、待遇がよく人気も高いみたいだね。
ビルメンの年収ランキング

次に、ビルメンテナンスを営む企業の年収ランキングを見ていきましょう。
平均年収と平均年齢をまとめると以下のとおりです。
【1位】プロパティデータバンク/平均年収756万円(41.9歳)
【2位】インターライフホールディングス/平均年収740万円(44.0歳)
【3位】第一カッター興業/平均年収603万円(38.6歳)
【4位】エムティジェネックス/平均年収603万円(51.8歳)
【5位】三機サービス/平均年収582万円(39.9歳)
【6位】日本空調サービス/平均年収574万円(38.9歳)
【7位】サンセイ/平均年収561万円(38.9歳)
【8位】NITTOH/平均年収517万円(41.6歳)
【9位】ルーデン・ホールディングス/平均年収507万円(47.6歳)
【10位】イオンディライト/平均年収461万円(46.0歳)
引用:年収ランキング「ビルメンテナンス企業の平均年収ランキング1位~16位【2021年最新版】」
平均年収の最も高いプロパティデータバンクおよびインターライフホールディングスで、700万円を超えています。
知名度はそれほど高くない業界ではありますが、上記のとおり企業によっては年収も高い。
また仕事の安定性の面からも、意外と就活生からの人気もある業界です。
「ビルメン業界は知名度が低いから大丈夫だろう」と気を抜かず、選考を受けるならしっかり対策を練る必要があるでしょう。
日本人一人当たりの平均年収は470万円なので、業界トップ企業は高い給与水準であることがわかるね。
ビルメンの売上ランキング

次に、ビルメンの売上ランキングも共有しておきますね!
以下は、ビルメン業界の中でも売上の上位10社です。
| 企業名 | 売上高(億円) | |
|---|---|---|
| 1 | イオンディライト | 1,757 |
| 2 | 東急不動産ホールディングス | 786 |
| 3 | 日本管財 | 719 |
| 4 | 東洋テック | 274 |
| 5 | ビケンテクノ | 265 |
| 6 | 大成 | 253 |
| 7 | ハリマビステム | 249 |
| 8 | 日本ハウズイング | 93 |
| 9 | ダイビル | 81 |
| 10 | 共立メンテナンス | 74 |
参考:業界動向サーチ「ビル管理業界 売上高ランキング(2021-2022)」
圧倒的に売上が高いのが、イオンディライトというイオングループの会社です。
業界内でもかなりのシェアを占めており、海外にもグループ会社があります。
そのほか、オフィスビルや商業施設の管理運営を事業のひとつとしている「東急不動産ホールディングス」。
建物の管理だけでなく、定期点検などの情報を管理するシステムの提供もしている「日本管財」が、売上ランキングでは2位・3位とつづいています。
売上が高い企業では、ビルメンテナンス以外の事業も幅広く行なっているのが特徴です。
将来性を考えるうえでやはり企業の売上はひとつの指標になるので、必ずチェックしておきましょう。
売上でみると、かなり差がありますね。
そうなんだ。上位の企業は「なぜ売上が高いんだろう?」と考え、企業研究を行うことが大事だよ!
そもそもビルメン(ビルメンテナンス)とは?

ここまでビルメンの年収と就職偏差値を見てきました。
そもそもビルメンについての基礎知識を理解しているでしょうか?
ビルメンとは「ビルメンテナンス」の略で、主に施設管理業務を行います。
簡単に説明すると、“ビルなどの建物や施設を安全かつ衛生的に保つ”ことがビルメンの役割です。
ビルメンの勤務先は大型商業ビルやオフィスビル、病院、大学などさまざまです。
緊急トラブルなどがなければ基本的にルーティーンワークで、毎日同じような流れで仕事に取り組みます。
ビルメンにはノルマなどもないので、重い責任を負わなくてよい点も人によってはメリットでしょう。
裏方仕事で決して目立つ仕事ではありませんが、人々が快適に施設を使用するためにはなくてはならない重要な存在です。
ビルなどの施設を管理するのが主な仕事なんですね!
そうだね!人々が日々使う施設を快適に保つという重要な役割を担っているんだ。
ビルメンの仕事は主に施設管理業務

ビルメンの主な仕事は施設管理業務です。
しかし、施設管理といっても具体的に何をするのかいまいちピンとこないですよね。
ここでは、ビルメンの具体的な業務内容を解説していきます。
【ビルメンの主な仕事内容】
- 清掃・衛生管理業務
- 設備管理業務
- 建物・設備保全業務
- 警備・防災業務
① 清掃・衛生管理業務
清掃・衛生管理業務は、施設内の清掃や衛生的な環境づくりを行う仕事です。
清掃管理業務では、施設の景観維持に加え、什器や備品が損壊していないか確認します。
床や壁、備品などはそれぞれ特性が異なり、場所ごとに適した方法で清掃を行うため知識が必要です。
ときにはトイレのつまりや不具合を直すこともあります。
衛生管理業務では、人工空間である施設内を衛生的に維持管理します。
浮遊粉塵や温度、CO²などの定期的な測定を行ったり飲料水の水質調査を行ったりすることも、業務のひとつです。
排水層や汚水層の清掃やねずみなどの害虫駆除も仕事に含まれます。
② 設備管理業務
設備管理業務では、施設内にある設備機器が問題なく作動しているか確認します。
大きなビルや商業施設内には、電気設備や給排水設備、空調設備、ボイラーなど人々が快適に過ごすためのあらゆる設備があります。
これらの設備に不具合が起きた場合、業務や人命に支障をきたす恐れがあります。
事故や災害などの非常事態を未然に防ぐため、各設備が正常に作動しているかをチェックすることは非常に重要な業務です。
具体的には、施設内にある機器の監視や点検、記録、分析、整備などを行います。
③ 建物・設備保全業務
建物・設備保全業務では、建物を長期的に保全するために建築基準法で定められた定期点検や調査などを行います。
具体的には屋根防水の劣化の有無や外壁タイルの亀裂・落下の可能性の確認、エレベーターやエスカレータの法定点検などです。
定期的な検査により施設の構造や劣化度合いを調査分析し、今後起こりうる故障や消耗を未然に防ぎます。
点検内容により、劣化箇所の補修や施設自体の改装計画も立てられるというメリットもあります。
④ 警備・防災業務
警備・防災業務では、施設と人々の安全を守るために監視や点検を行います。
警備作業では、施設の出入口の監視や夜間の見回りなどを行い不審物や不審者がいないかの確認や、機械警備システムによる駐車場の管理や運営を行います。
また防災設備に不備がないか点検を行い、火災時に火災報知器や鳴るか、防火シャッターがきちんと閉まるかなどを確認します。
いずれも人命にかかわる非常に重要な仕事です。
施設管理といってもいろいろな業務があるんですね!
ビルメンの仕事はビルの管理全般を請け負うから専門的な知識も必要になるよ!
ビルメンは系列系と独立系で待遇が異なる

ビルメンの世界には「系列系」と「独立系」という言葉があります。
どちらも同じビルメン会社に変わりないのですが、これらには明確な待遇の差があるといわれています。
「ビルメンならどちらでもいい」なんて考えていると、入社後後悔...なんてこともあり得ます。
就活時には必ず知っておくべき内容なので、両者の違いをしっかり確認していきましょう。
系列系ビルメンとは?
系列系ビルメンとは「親会社のあるビルメン会社」のことをいいます。
たとえば不動産系なら親会社が不動産会社、鉄道系なら親会社が鉄道会社といった具合です。
系列系の親会社には、以下のようなものがあります。
- 不動産系
- 鉄道系
- 建設系
- 保険系
- 警備系
系列系のビルメンでは、基本的に親会社所有のビルや施設の管理を行います。
親会社の物件を管理しているため安定して仕事を受注でき、管理料金の値下げや解約もほとんどないため会社が傾く心配がほとんどありません。
そのため、系列系ビルメンは独立系と比較し給与が高く福利厚生もしっかりとしています。
年間休日も120日以上を超す会社も多く、しっかりと休みをとれます。
一方で、契約先が系列会社だからこそ責任が重く仕事量が多い傾向にあります。
施設の常駐は独立系ビルメンなどの協力会社に任せ、ひとりで数十件を管理することも系列系ビルメンの特徴です。
ビルメンのメインである設備点検だけでなく書類管理やマネジメント業務を行い、親会社やテナントの担当者と会議をすることもあります。
高い給与をもらいつつ休日もしっかりほしいという方は、系列系ビルメンがおすすめです。
独立系ビルメンとは?
独立系ビルメンとは「親会社を持たないビルメン会社」のことをいいます。
そのため親会社から仕事がもらえる系列系ビルメンと異なり、自分たちで仕事を受注しにいく必要があります。
入札という形で仕事を受託しますが安く入札した会社に仕事がまわるため、価格競争になり系列系ビルメンに比べ、給与が低いのが特徴です。
また官公庁の施設は定期的に入札がありより安く入札した会社に契約を奪われてしまうこともあるため、担当施設の解約リスクは常にあります。
一方で、独立系ビルメンは系列系ビルメンに比べ仕事が楽な傾向にあります。
年間休日は系列系ビルメンよりも少ない傾向にありますが、大半が常駐系の仕事で仕事量も少なく定時退社することがほとんどです。
しばしば「ビルメンは楽」といわれますが、その場合はたいてい独立系ビルメンを指しています。
趣味や夢、副業がありプライベートの時間を大切にしたいという方は、独立系ビルメンがおすすめです。
福利厚生がいい、残業が少ないなど、ホワイト企業をお探しの方はこちらの記事で入社方法を詳しく解説しているので参考にどうぞ!
なるほど!系列系と独立系で、待遇や企業の安定性が異なるんですね!
そうだよ。特に系列系は親会社から仕事が降りてくるから、安定性が高く、待遇が良い傾向にある。
ビルメンの平均年収はいくら?

ビルメンの平均年収は、全国平均で約300万円(37歳)です。
地域や資格の有無などさまざまな要素により年収は変動しますが、水準として高いとはいえないでしょう。
とはいえ先ほども説明した通り系列系ビルメンと独立系ビルメンには待遇に差があり、それぞれで平均年収も異なります。
系列系ビルメンの平均年収は、約450万円です。
親会社のある系列系ビルメンは福利厚生や資格手当、年間休日、昇給制度、退職金制度などがしっかりしており、独立系ビルメンよりも待遇がいいことが特徴です。
一方、独立系ビルメンの平均年収は、約350万円です。
親会社を持たない独立系ビルメンは、系列系ビルメンに比べて待遇に恵まれないケースが少なくありません。
系列系と独立系で平均年収が100万円ほど変わるので、就活前に自分が会社に対して何を求めているのかきちんと考えたほうがいいね!
ビルメンに就職するメリット

ここでは、ビルメンに就職するメリットを紹介します。
まずはメリットを知っておくことで「ビルメンってどんな仕事?」と興味がある方も一層イメージがしやすくなるでしょう。
ビルメンのメリットとして挙げられるのは、以下の3つの項目です。
【ビルメンのメリット】
- 業界が安定している
- 資格で年収が上がる
- 転職しやすい
メリット① 業界が安定している
1つ目は「業界が安定していること」です。
ビルメンの仕事はビルなどの施設があるかぎりなくならないものであり、業界的に安定しているといえます。
また近年では、老朽化した建築物を壊し長く使い続けるための「持続化」に注目が集まっています。
施設を長く使い続けていけるよういかに管理していくのかは、ビルメンの腕の見せ所です。
街が発展し新たな建物がつくられていく中で安定した需要が見込める点は、ビルメン業界のメリットいえるでしょう。
メリット② 資格で年収が上がる
2つ目は「資格の取得で年収を上げられること」です。
給料が安いといわれる業界ですが、コツコツと勉強し関係資格をたくさん取得すればまとまった資格手当をもらうことができます。
ビルメン業界は、とにかく実務経験と資格が強みになる世界です。
このふたつさえあれば資格手当のほかにも選任手当(名義料)が支給され、さらに年収が増えます。
自分の努力次第で年収が上がる点も、ビルメン業界のメリットといえるでしょう。
メリット③ 転職しやすい
3つ目は「転職がしやすいこと」です。
ビルメン業界は基本的に人手不足で、転職がしやすい業界であるといわれています。
未経験者でも中途採用の受け入れがあるほどなので、2度3度の転職回数も不利にはなりません。
どんなに入りたかった会社でも、雇用条件や人間関係のトラブルなどで退職してしまう可能性は誰にでもあります。
実務経験や資格さえあれば同業界への転職が容易である点も、ビルメン業界のメリットといえるでしょう。
なるほど!たしかにビルメンテナンスってなくなることがない仕事ですもんね。更には1度お願いした会社に継続的にお願いするだろうから、安定性も高そう。
まさにそのとおり!こうして業界ごとの特性を考えることは、就職先を選ぶ上で非常に重要だよ。
ビルメンに就職するデメリット

ここでは、ビルメンに就職するデメリットを解説します。
どんな業界や会社に就職したとしても、メリットもあればデメリットもあります。
それぞれを理解しておくことで就活時と入社後のギャップを小さくできるため、今のうちに確認しておきましょう。
ビルメンのデメリットとして挙げられるのは、以下の3つです。
- 汚い仕事がある
- 業界年収が低い
- 継続的な勉強が必要
デメリット① 汚い仕事がある
1つ目は「汚い仕事があること」です。
ビルメンは施設管理業務を行いますが、その中にはトイレの詰まりを直したり汚水層の点検なども含まれます。
こういった仕事に臨機応変に対応できない人だと「辛い」「辞めたい」と感じてしまうことがあります。
こういった仕事は毎日あるわけではなく、やっていくうちに意外と慣れてしまうものでもあります。
ただしこのような仕事を行う可能性があるという点は、あらかじめ覚悟しておいたほうがよいでしょう。
デメリット② 業界年収が低い
2つ目は「業界年収が低いこと」です。
ビルメンの仕事は他業界に比べて年収が低いといわれています。
特に独立系ビルメンは、仕事が比較的楽である分給与もそこまで高くありません。
ただしメリットでもお話したように、年収は資格の取得によりアップする可能性があります。
また経験を積んで独立系から系列系へ転職すれば、平均程度の給与も狙えます。
デメリット③ 継続的な勉強が必要
3つ目は「継続的な勉強が必要であること」です。
ビルメンの仕事において、資格の有無は年収にも信用にもつながるほど重要です。
そのため、仕事をしながら継続的に資格勉強も行う必要があります。
ビルメンの取れる資格は幅広く、かつ上級資格である「三種の神器(エネルギー管理士・建築物環境衛生管理技術者・電験三種)」は難易度が高い試験です。
「コツコツ勉強するのが苦手」という人にとっては、継続的な勉強が必要になる点が苦痛に感じるかもしれません。
ビルメンテナンスはそこまで高い利益を取れない仕事がゆえに、業界全体として見ると給与は低めなんですね。
そうなんだよ。これらのデメリットを考慮した上で、自分に合っているかどうか考えると良いよ。
ビルメンへの就職に向いている人の特徴

ここでは、ビルメンの就職に向いている人の特徴を解説します。
これからビルメン業界を目指す人はぜひ参考にしてくださいね。
ビルメンへの就職に向いている人の特徴は、以下の3つ。
【ビルメンへの就職に向いている人の特徴】
- 自分の時間を大切にしたい
- コツコツと勉強することが苦にならない
- 人とかかわることが好き・得意
特徴① 自分の時間を大切にしたい
1つ目は「自分の時間を大切にしたい人」です。
ビルメンの仕事は、プライベートとの両立が比較的しやすい職業だといわれています。
独立系ビルメンでは残業がほとんどないため、本業で安定しながら趣味や夢、副業をがんばりたい人には適しているでしょう。
系列系ビルメンも年間休日120日以上と休みがしっかりとれるため、休日にやりたいことが十分できる環境です。
自分の人生において、何に重きを置くかはひとそれぞれです。
業界年収が低いといわれがちなビルメンですが、それ以上に大事なことがあるのであればさほど苦にならず続けていけるでしょう。
特徴② コツコツと勉強することが苦にならない
2つ目は「コツコツと勉強することが苦にならない人」です。
ビルメンの仕事では、施設の管理にあたり電気や空調、環境衛生などさまざまな専門知識が必要です。
そのため、入社してからもコツコツと勉強してスキルアップに努めなければなりません。
資格が取得できれば業務範囲が広がったり手当がつき年収が上がったりします。
ですが、勉強のモチベーションが保てそうにない人にとってはある種つらい仕事になるでしょう。
自分のがんばり次第でキャリアアップしていく過程を楽しめる人は、ビルメンに向いているといえます。
特徴③ 人とかかわることが好き・得意
3つ目は「人とかかわることが好き・得意な人」です。
ビルメンの仕事は、実は人とのコミュニケーションが必要となる側面もあります。
とくに系列系ビルメンは、施設利用者やオーナー、設備関連会社の人々など想像以上に人と話す機会も少なくありません。
そのため「機械だけ相手にしていたい」というような人は、入社後のギャップに苦しむ可能性があるため注意が必要です。
とはいえ営業職のような高いコミュニケーション能力が求められるわけではないため、心配しすぎる必要もないでしょう。
上記に当てはまらないからといって諦める必要はないよ。ビルメンに興味がある人は、企業研究をしっかり行なってビルメンの仕事の中でも自分に適性がある職種はなにか調べてみてね!
ビルメンへの就職に関して有利に働く資格一覧
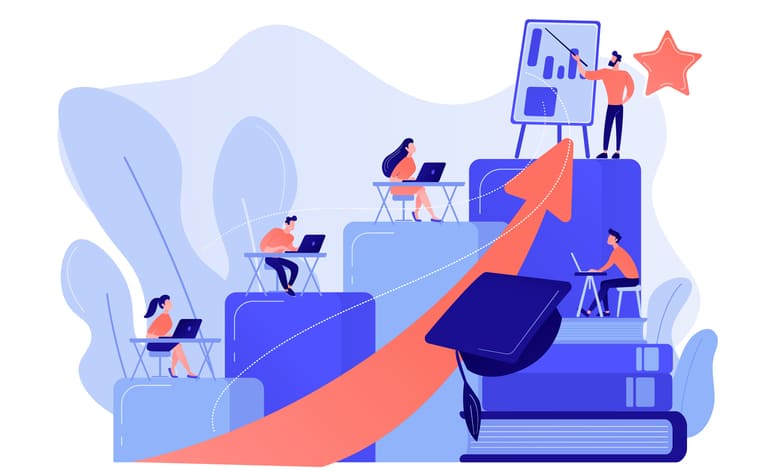
ビルメン業務の説明から、資格が非常に重要となることは理解できたでしょう。
ここでは、ビルメンへの就職に関して有利に働く資格をご紹介します。
「ビルメン4点セット」と呼ばれる、4つの国家資格です。
- 第二種電気工事士
- 二級ボイラー技士
- 危険物取扱者乙種4類
- 第三種冷凍機械責任者
これらはビルメンの仕事をするうえで、まず取っておいたほうがいい基礎的な資格。
取得自体が昇進や昇格の条件になっている会社もあるほどです。
独学で受験できどれも6割取れれば合格点に達する試験のため、就活前に取得しておくことをおすすめします。
4つすべて持っている人は少なく、学生のうちから資格を取得していることで意欲も評価されやすいです。
大学1~2年生の方は、今の内から勉強をすすめておくとよいでしょう。
就活まで時間のない人は、受験できる資格だけでも取得しておくと就活や入社後に役立つよ!
ビルメン業界の現状と将来性

就活において気になるのが、その業界の現状や将来性ですよね。
技術が発展し仕事のあり方も日々うつり変わる昨今では、将来その職業がどうなってゆくのかもあらかじめ考えておく必要があります。
ここでは、ビルメン業界の現状と将来性を解説します。
「やりたいから」「向いているから」という理由も大事ですが、業界の動向も押さえておくとさらに強固な志望理由がつくれるようになりますよ!
ビルメンの現状
ビルメン業界の市場規模はおよそ4兆円(引用:矢野経済研究所「ビル管理市場に関する調査を実施(2020年)」)といわれており、現状では安定して成長し続けています。
ビルメンの仕事はビルなどの施設がある限り、なくなることはありません。
2020年はコロナウイルスの影響で市場規模が縮小しましたが、今後も安定した需要が見込める業界であると考えてよいでしょう。
ビルメンの仕事は裏方業務になるため、社会的認知度が低く業務内容のイメージがしにくいです。
そのため、求人数に比べ働き手の数が少なく人材不足であるという問題はありますが、裏を返せば大手企業や人気企業でなければ入社しやすい業界でもあります。
ビルメンの将来性
ビルメンは将来的にさらに重要な職業になっていくことが予想されます。
これまで建物は30年ごとに壊して立て直されるいわゆる「スクラップ&ビルド型」でした。
しかし近年SDGsが注目されているように、長く建物を使いつづける「ストック型」に流れが変化しているようです。
そのため、今後立てられる建物は長く利用しつづけるための管理がとても重要となり、技術力を有したビルメンが重宝されることが予想されます。
近年では技術の発達によりAIに仕事を奪われると職業もでてくるといわれていますよね。
しかし、状況に応じて臨機応変に対応するビルメンの仕事はまだまだ人間でないとできないものです。
将来のことは誰にもわからないけれど、すぐに仕事がなくなるということはなさそうだね!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
今回の記事を通して、ビルメンの年収や就職偏差値だけでなく、そもそもビルメンの仕事はどんな内容なのか?
加えて、どのような人が向いていて、就職するメリット・デメリットは何かを掴むことができたと思います。
新卒で入社する場合、ビルメンは大学生からの知名度が低い業界なので倍率が低くなりがちで狙い目です。
今回の記事を読んで「ビルメンって業界は面白いかも?」と思った方は、ぜひ自分でもどんな企業があるのか色々調べてみてくださいね。
ちなみに、この記事を読み終わったら「【ホワイト企業】“穴場な優良企業50社”をランキングで共有!」も読んでみてください。
ビルメンのように穴場なホワイト企業を50社まとめています。
穴場なホワイト企業かどうか見分けるポイントも共有しているので、ぜひチェックしておいてください!
それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう。
【本記事の要点まとめ】
- ビルメンとは「ビルメンテナンス」の略で、主に施設管理業務を行う
- ビルメンは系列系と独立系で待遇が異なる
- ビルメンの平均年収は約300万円で、系列系は独立系よりも約100円高い
- ビルメン業界は安定しており、今後も需要が見込める