
就活生や転職者のみなさん、こんにちは!
これまで7年、書いた記事は1500記事を超え、求人サイトの運営まで始めた"日本イチの就活マニア"こと就活マン(@syukatu_man)です!
今回は「SPI対策が間に合わない」と悩んだ時の対処法を解説していきます!
僕はこれまでSPIに関する記事を50記事以上は書いてきています。
だからこそ、SPI本番まで残りどのぐらだとこれをすべきだ、という最適解を理解しています。
この記事を通して、SPI対策が間に合わないという悩みを解決させます!
SPIの能力検査で足切りされるのは、本当にもったいないので、ぜひ参考にしてくださいね。
(※SPIの性格検査で落ちるのは全く問題ありません!自分の性格と合わない企業に入社する方が最悪なので!)
SPI対策が間に合わないと焦っています!やるべきことを教えてください!
SPI対策が間に合わないと悩んだ場合、本番までの残り日数ごとにやるべきことは変わる!詳しく解説していくね!
- SPI対策が間に合わないと感じても可能な限り勉強すべき
- 【重要】間に合わないと悩んだ時に全員がすべきは模擬練習
- 【残り日数別】SPI対策が間に合わない人がすべきこと
- SPI対策が間に合わないと感じている人が意識すべきコツ【3選】
- そもそもSPI対策はいつから始めるべきなのか?
- 「SPI対策 間に合わない」と調べる人からよくある質問
- 本記事の要点まとめ
SPI対策が間に合わないと感じても可能な限り勉強すべき
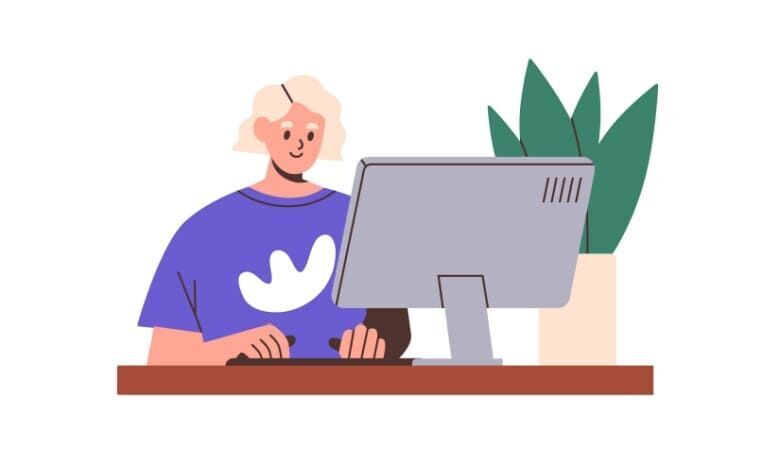
結論、SPIは時間の許す限り対策して本番に臨むことを強くおすすめします。
本番直前になって「SPI対策が間に合わない」と悩む人は少なくないですが、その状況下でも可能な限り勉強に時間をあてることが最善なんですよね。
以下ではその理由をまとめたので、ぜひさくっと確認していきましょう。
【SPI対策が間に合わないと感じても可能な限り勉強すべき理由】
- シンプルに落ちる可能性が高くなるから
- ぶっつけ本番よりも正答率が高くなりやすいから
理由① シンプルに落ちる可能性が高くなるから
SPI対策が間に合わないと思っても、対策なしで本番に臨むと結果が出にくいです。
SPIは問題の形式やパターンがある程度決まっているので、対策した上で本番に臨んだほうがよい結果にもつながりやすいんですよね。
いくら時間がないと思っても、その状態から時間の許す限りは対策をしたほうが就活での後悔を減らせる可能性が高い。
なかには、SPIはノー勉でも受かるなどと楽観的に考える人もいるかもしれません!
もちろん、もともと漢字や数学が得意な人・かつ倍率があまり高くない企業を受ける場合なら、ノー勉や少ない勉強時間でも受かる可能性はあると思います。
でも受ける企業が人気企業の場合、足切りにあう可能性も十分考えられるんですよね。
もともとの学力などは人それぞれですが、たとえ少しであっても勉強して本番に臨んだほうが自分の力を発揮しやすいことは間違いありません!
理由② ぶっつけ本番よりも正答率が高くなりやすいから
SPIは事前に問題集などを解いておくと、傾向を把握した上で本番に臨めます。
簡単な問題でも難しい問題でも、「こういう形式の問題が出るんだ」とわかった上で問題と向き合ったほうが落ち着いて対処しやすいんですよね。
初見ではやや難しく感じる問題があったとしても、一度パターンを体験しておくだけで、2回目以降はスムーズに回答できることもよくあるかと。
こうした回答の積み重ねで全体の結果が算出されるので、対策を軽視しないでSPI自体に慣れておくと全体の正答率も高くなりやすいんですよね。
また、SPIには制限時間が設けられており、時間内にどれだけ多くの問題を解けるかが重要になってきます。
その点でも、ぶっつけ本番だと一つひとつの回答に時間を要しやすいんですよね。
総合的に考えて、やはり合格率を高めたいなら対策しない理由はないと思います。
本番までに残された時間は人それぞれだと思いますが、どんな状況下でも自分が取り組める限りの対策を考えて行動を起こしてみてください。
問題の傾向やパターンがある程度決まっているゆえに、事前に少しでだけでも対策しておくと本番でもより力を発揮しやすくなるんですね。
なかには「ノー勉でも受かる」と軽視する人もいるけど、少しでも合格率を高めたいなら可能な限りの対策をして本番に臨むほうが合理的だと僕は考えているよ。
【重要】間に合わないと悩んだ時に全員がすべきは模擬練習
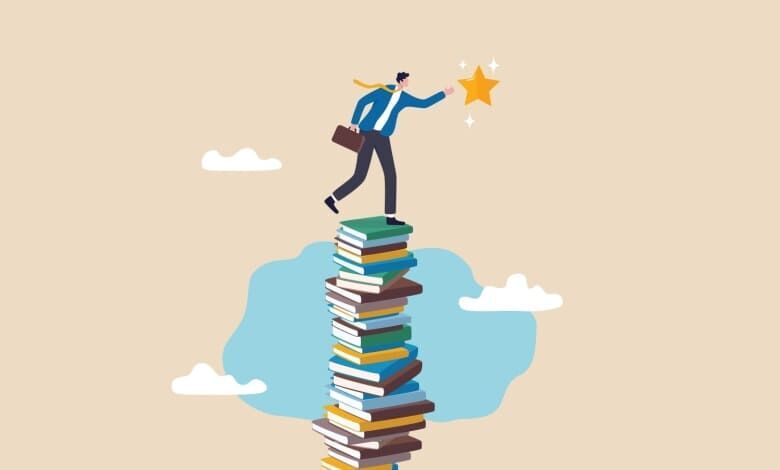
次の章からSPI試験本番までの残り日数別にやるべきことを解説します。
ですが、その前にSPI対策する上で、本番までいつであろうと全員がすべきことを先に紹介しますね。
それがSPIの模擬練習に取り組むことです!
今はネットで無料で模擬練習に取り組むことができる時代。
特に逆求人サイトのキミスカが提供するSPI模擬練習は、本番慣れすることもできるので、絶対に取り組むようにしたいところです。
合格判定と、それを受けた学生内での順位まで見れるのが最強です。
(50%ぐらいが足切りされる企業も多いので、受験者数の半分以内に入れるように勉強しておきたいところ!)

SPI対策が間に合わないと悩んだ時は、大学受験のように過去問を解いて問題に慣れることが最も有効です!
こうした有益な無料サービスをフル活用していきましょう!
無料でSPI模擬練習を受けられるのは最高ですね!
特にキミスカはプロフィール登録すると企業からのスカウトも届くから、本当に一石二鳥でおすすめだよ!
【残り日数別】SPI対策が間に合わない人がすべきこと

次にこの章では、SPI対策が間に合わない人がすべきことを紹介します。
本番までに残された日数別に、僕がおすすめしたい対策をまとめました。
日数によって内容に違いがあるとはいえ、可能な限り対策すべきことは変わりません。
僕が考える「残された時間でできる限り最大の結果を得るためのアイデア」を紹介していくので、対策が間に合わなくて悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
【残り日数別|SPI対策が間に合わない人がすべきこと】
- 本番前日:Webサービスやアプリを活用して問題を解く
- 残り3日:問題集で言語問題から取り掛かる
- 残り7日:問題集で言語→非言語の順に取り掛かる
①本番前日:Webサービスやアプリを活用して問題を解く
まずは、SPI本番の前日という人向けの対処法をお伝えしますね。
結論、本番前日の人はWebサービスやアプリを活用して問題を解くのがおすすめです。
僕はSPI対策では基本的に問題集を解くことをおすすめしていますが、本番前日の場合は問題集を用意するだけでも時間がもったいないんですよね。
いくら危機感があっても、分厚い問題集を見るとやる気も失いやすい。
こうしたときに便利なのが、ネット上で対策を完結させられるサイトなどの存在です。
SPI対策として定番なのはやはり本ですが、昨今ではネット上でSPIの問題を配布するWebサービスやアプリなども増えています。
またSPI対策ではとにかく問題に触れることが重要になってきますが、Web上で問題を解けたら短い時間でも多くの問題にチャレンジしやすいと思います。
具体的に僕がおすすめしているサイトなどは以下の記事でまとめました。
無料でもSPIの問題をダウンロードできるサイトは多く存在するので、本番まで残りの時間が限られている就活生もぜひ有効活用してみてくださいね。
②残り3日:問題集で言語問題から取り掛かる
本番まで3日以上残っている人は、ぜひ問題集を買って対策してください。
SPIではとにかく問題に多く触れることが肝になるので、数多くの問題が列挙されている問題集は対策を進める上でやはり有用なんですよね。
僕があなたと同じ立場だとしたら、下記のような問題集を活用します。
1冊目は問題集が多いのでよりじっくり対策できますが、時間が限られているとやり切れない可能性があるので、これは時間に余裕がある人におすすめですね。
2冊目は、1冊目と比べるとイラストなどが含まれていて問題数もやや少なめです。
よって、残り3日というタイミングで問題集を用意するなら僕なら後者を選びますね。
ここからは、問題集を用意してからの取り組み方についてです。
結論、時間が限られている場合は言語問題から取り組むのが僕はおすすめですね。
言語問題は漢字の意味や二語の関係理解など、少し対策するだけでも本番でスラスラ回答できるような問題が多くあるからです。
その点、非言語問題は実践が重要になる問題が多い印象なんですよね。
もともと数学が得意な人なら効率的に対策を進められるかもしれませんが、実際に計算などをする必要がある点からも対策に時間がかかりがちです。
よって、まずは言語問題の対策をしたほうが時間をより有効活用できるかと。
個々人の得意不得意や考え方によっても変わってきますが、何から対策すべきか曖昧だった人は僕のアイデアもぜひ参考にしてみてください。
③残り7日:問題集で言語→非言語の順に取り掛かる
本番まで7日以上残されている人は、3回程度の人と基本的な方針は変わりません。
まずは問題集を用意して、とにかく繰り返し問題を解いてください。
その際、やはり言語問題のほうがさくっと対策を進めやすいので、言語問題→非言語問題の順に取り掛かるのが僕はおすすめです。
非言語問題も言語問題より時間がかかりやすいとはいえ、公式や回答パターンを覚えるとスラスラ回答できる問題が多くありますよ。
非言語問題には初見では回答が難しい問題も少なくないですし、本番でスムーズに回答できる問題を増やすためにもぜひ対策を進めておきましょう。
本番前日の場合、たしかに問題集を用意するのは大変なので、ネット上で対策を進められるサイトやアプリの存在はありがたいですね。
大まかな対策の方針を決めたら、あとはとにかく実際の勉強を進めていってみてね!
SPI対策が間に合わないと感じている人が意識すべきコツ【3選】

続いては、SPI対策が間に合わないと感じている人が意識すべきコツを紹介します。
本番までの時間が限られた状況化で、できる限り高い成果をあげるために知っておくとよさそうな内容を僕なりにまとめました。
残された時間が同じでも、ポイントを意識したほうが効率的に対策を進めやすくなるので、漠然と準備をしようと思っていた人はぜひ一読してみてください。
【SPI対策が間に合わないと感じている人が意識すべきコツ】
- スキマ時間を有効活用する
- とにかく数をこなして多くの問題に触れる
- 苦手分野をできる限り減らす
コツ① スキマ時間を有効活用する
まずは、できる限り多くの時間を対策にあてるという意識を強く持ってください。
この記事を読んでくれている人の多くは、SPIの本番までに残されている時間があまり多くないという状況だと思います。
この状況下で重要になるのは、いかに多くの時間を勉強に使えるかなんですよね。
そこでポイントになるのが、スキマ時間を有効活用することです。
個々人の置かれた状況は人それぞれですが、大学の講義やバイト・就活のほかの準備など、やるべきことに追われて時間にゆとりがない人がほとんどだと思います。
むしろ、SPI対策だけに1日の時間を自由に使えるという人は稀ですよね。
このように忙しい状況下では対策も後回しになりがちですし、まとまった時間を確保しようと思っても現実的に難しい状況になりやすいかと。
そこで、ふとできる15分などのスキマ時間で勉強することが大切なわけですね。
受験勉強などと同じくSPI対策もこうした積み重ねが差になりやすいので、とくに他の予定で忙しい人ほど意識して取り組んでみてください。
コツ② とにかく数をこなして多くの問題に触れる
SPI試験を突破するためには、とにかく問題を解きまくることが重要です。
精神論のように聞こえる人もいるかもしれませんが、繰り返し問題を解いていると出題の傾向や回答の導き方などが自然と身につくんですよね。
よって僕は常々、1冊の問題集を何周も繰り返すという対策をおすすめしています。
これまで対策に時間をかけてこなかった人は、本番直前となって準備が間に合わないと悩んでいると思います。
でも、その不安な状況でも多くの問題に触れる以上の対策はないんですよね。
本番で初見の問題が減り、慣れ親しんだ問題が増える状況を作れたら、全体としてもよい結果につながりやすいことは明白です。
スキマ時間の積み重ねでも多くの問題に目を通すことはできるはずなので、ぜひ最後まで妥協することなく問題と向き合ってみてくださいね。
コツ③ 苦手分野をできる限り減らす
SPI対策を進める際には、苦手分野をできる限り減らす意識も持ってください。
本番までの時間が限られていると、苦手分野と出会ったときに「もうこの問題はいいや」などと諦めたくなるかもしれません。
でも、苦手分野が複数あると当然ながら高得点につながりにくいです。
苦手分野を克服することは簡単ではないですが、そこで失っていた点数が◯になるだけでも全体の正答率アップに大きく貢献してくれるんですよね。
SPIには難しい問題もありますが、基本的にはじっくり解説を読み込んで問題を繰り返し解けば、苦手と感じても克服できるレベル感ではあると思います。
苦手分野は大きな伸びしろとも言えるので、対策にどの程度時間をかけるかのバランスも重要ですが、ぜひ妥協せずに取り組んでみてくださいね。
SPI対策を進める上でも、スキマ時間をいかに有効活用できるかが重要になるんですね。
自由に使える時間がたっぷりある人は稀だからね。本番までの時間は限られているのだから、残りの期間だけでも集中して努力したほうが後悔を減らせるはずだよ!
そもそもSPI対策はいつから始めるべきなのか?
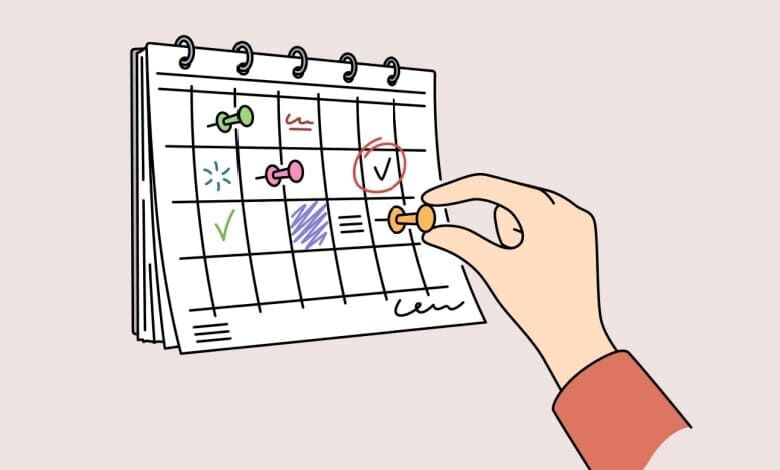
次にこの章では、SPI対策はいつから始めるべきなのか?を補足的に共有します。
直前でも対策できることは多くありますが、そもそも「SPI対策が間に合わない」という状況を作らないことが重要なんですよね。
この記事を読んでくれている人のなかには、SPI本番まで時間があるという人もいると思うので、該当する人は参考までにぜひ一読してみてください。
【そもそもSPI対策はいつから始めるべきなのか?】
- 勉強時間の目安は30時間〜60時間程度
- 大学3年の3月までには対策を始めておくべき
- 「1日15分だけ」などと決めて取り組むのもおすすめ
勉強時間の目安は30時間〜60時間程度
参考材料として、SPI対策に必要な学習時間の目安を紹介します。
SPI対策には、最低で30時間・理想では60時間程度の確保が必要だと言われています。
もちろん個々人の学力やこれまでの経験などでも時間は変わってきますが、予定学習時間を考える際には一定の参考になるかと。
毎日1時間勉強するとしても、1〜2ヶ月の確保が必要になるとわかりますね。
一日あたりの学習時間によっては、何月から対策すべきかも変わってきます。
自由に使える時間は人によって差があると思うので、自分のほかの予定などを考慮していつから対策すべきか逆算してみてくださいね。
大学3年の3月までには対策を始めておくべき
対策開始時期の目安として、僕は遅くとも大学3年の3月までにはSPIの勉強を始めることをおすすめしていますね。
就活が本格的に始まる3月は、SPI対策以外にもすべきことが多くあるからです。
3月以降にエントリーシートの準備などと同時並行で進めようと思っていると、負担になることが多い印象なんですよね。
よって、3月を迎える段階である程度の準備ができていると余裕を持ちやすいかと。
1つのイメージとして、年明けくらいからSPI対策を始めるのはアリだと思います。
1〜2月の時期を使って50時間程度の学習時間を確保できていれば、SPIの傾向や回答の流れなどはある程度頭に入れられるはずですよ。
自分に合った学習スタイルは人それぞれだと思いますが、いつから対策を始めるべきか曖昧だった人はぜひ参考にしてみてください。
「1日15分だけ」などと決めて取り組むのもおすすめ
「毎日1時間はSPI対策をする」というルールは大変に感じる人もいるかもしれません。
個人的な印象として、忙しい人ほど「毎日1時間」などのルールを設けて挫折してしまっていることが多いイメージがあります。
そこで僕がおすすめしたいのが、「毎日15分だけは対策する」と決めることです。
1時間を確保しようと思うと高いハードルになりやすいですが、15分だけならスキマ時間を活用することで達成しやすいんですよね。
毎日15分だけでも、1ヶ月で8時間・3ヶ月続けたら24時間にもなります。
時間に余裕があるときはもっと続けるのもアリですし、3ヶ月続けていると30時間程度の学習時間は自然と確保できるかもしれません。
新たな学習習慣を作るのが苦手な人は、1つのアイデアとしてぜひ取り入れてみてくださいね。
学習時間や対策開始時期の例などがあると、自分の場合にもイメージしやすいですね!
「SPI対策 間に合わない」と調べる人からよくある質問

最後の章では、「SPI対策 間に合わない」と調べる人からよくある質問に回答します。
似た疑問を感じていた人がいたら、ぜひ以下の回答を参考にしてみてください!
【「SPI対策 間に合わない」と調べる人からよくある質問】
- ノー勉や一夜漬けでもSPIは受かる?
- SPIがボロボロでも受かる人はいる?
- SPIで時間が足りない場合は適当に答えてもいい?
- SPIの足切りボーダーラインはどのくらい?
質問① ノー勉や一夜漬けでもSPIは受かる?
結論、ノー勉や一夜漬けでも受かる可能性はあります。
ただ、個々人のもともとの学力や企業の合格基準によっても大きく異なるので、「ノー勉でも受かる」などと断言することはできません。
やはり、合格率を少しでも高めたいなら愚直に対策するしかないかと。
問題に慣れたほうが確実に正答率も高くなるはずなので、SPIで落ちて後悔したくない人は勉強時間を確保しておくのがおすすめですね。
質問② SPIがボロボロでも受かる人はいる?
SPIがボロボロでも受かる人はいます。
自分の肌感覚よりも高得点を取れていたり、応募企業が設定している基準点が低かったりすることで、合格する可能性があるからですね。
これらの詳細や他に想定される理由については以下の記事で解説しました。
質問③ SPIで時間が足りない場合は適当に答えてもいい?
適当に答えることはおすすめしません。
答えがわからないと次の問題に切り替えるために飛ばしたくなりますが、正答率が悪いと全体の結果も悪くなってしまうんですよね。
よって雑な回答は避けて、いかに正確な回答をするかに意識を集中させるのがおすすめです。
質問④ SPIの足切りボーダーラインはどのくらい?
一般的なボーダーラインは、大手企業で7割・中小企業で6割程度と言われています。
もちろん企業によって詳細な合格基準は異なりますし、ボーダーラインは明確に公表されていないのであくまでも目安ですね。
よって、1つの目安として6割以上の獲得を目標に対策しておくとよいでしょう。
7割以上の正答率を出せるようになれば、ある程度どの企業が相手でもSPI試験は突破できると考えられるんですね!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
SPI対策が間に合わないと悩む人に向けて、残された日数別におすすめの対処法や限られた時間で意識すべきポイントなどを共有しました。
SPIには問題の傾向やパターンがあり、繰り返し対策すると自然と慣れます。
よって残りの時間が限られていても、できる限り多くの問題に触れる努力をしたほうがよい結果につながりやすいんですよね。
いくら忙しい人でも、スキマ時間を有効活用すれば対策を積み上げられます。
志望度の高い会社にSPIで落ちてしまうと後悔しやすいので、ぜひ今からでもできる対策に集中して愚直に行動を起こしてみてくださいね。
ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「就活マンが考える「就活を成功させるために必須の6大ポイント」を共有!」も読んでみてください。
僕が現状考えるもっとも有効な就活の攻略法を簡潔にまとめています。
就活全体を見据えてとくに重要な対策のみを厳選しているので、全体を意識した対策ができていない人はぜひ一読してみてください。
それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!
【本記事の要点】
- 対策なしで本番に臨むと正答率が低くシンプルに落ちやすくなるので、少しでも合格率を高めたいなら限られた時間内で勉強しておくべきである。
- 残り日数に応じて、Webサービスや問題集をフル活用して対策すべきである。
- 限られた時間で効率的に対策を進める上で、スキマ時間の活用・とにかく数をこなす・苦手分野をなくす意識は重要である。
- まだ時間に余裕がある人は、30時間〜60時間の確保を目安にしておくとよい。
- ノー勉や一夜漬けでは博打的なので、SPIを軽視しないで愚直に対策しておくべきである。









