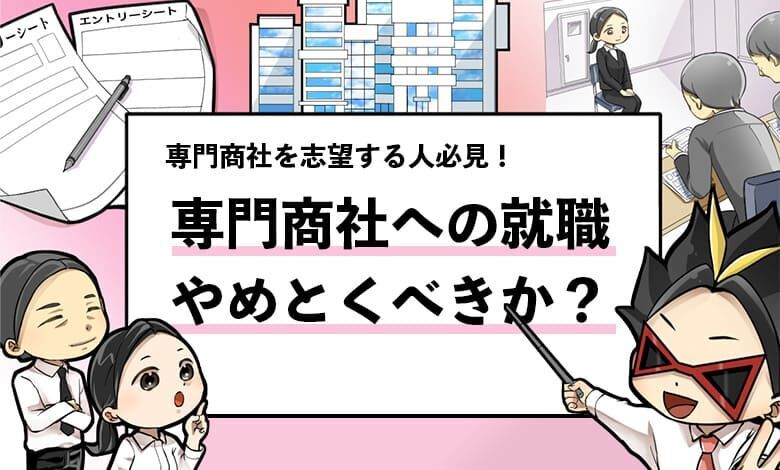
【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
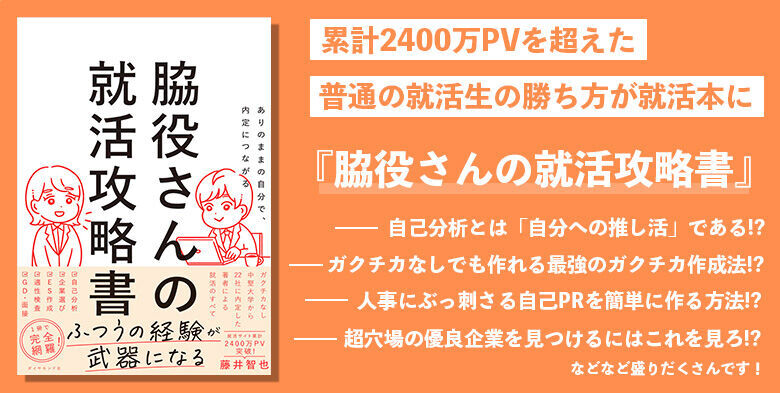
それでは本題に入っていきますね!
今回は「専門商社」について、徹底調査していきます。
ネットを見ると、「専門商社への就職はやめとけ」という声があるんですよね。
実際に、僕が新卒で入社した食品メーカーでは、食品の専門商社の方と関わる機会が多くありました。
話を聞く感じ、かなり業務量が多く、激務そうだったんですよね。
もちろんこのあたりは企業によって異なります。
よって一概に「専門商社はやめとけ」と言うのはナンセンスです。
ですが、なぜ専門商社への就職はやめとけと言われるのか?
その理由を把握しておくことは、専門商社への就職を考える上で非常に重要。
この記事を通して、専門商社に就職するメリットとデメリット、どんな人が向いているのかまで詳しく解説していきますね!
専門商社は気になっていました!激務な企業もあるとのことですが、詳しく知りたいです!
本当に企業単位で労働環境は異なるから、一概には言えない。でも傾向を押さえることは有効だから詳しく見ていこう!
- 専門商社はやめとけと言われる理由【8選】
- 【結論】専門商社への就職はやめておくべきか?
- 専門商社に就職するメリット【7選】
- 専門商社に向いている人の特徴【3選】
- 専門商社をおすすめできない人の特徴【3選】
- 専門商社への就職を後悔しないためのポイント
- 専門商社の選び方【見極めるための3つのポイント】
- 「専門商社 やめとけ」と調べる人からよくある質問
- 本記事の要点まとめ
専門商社はやめとけと言われる理由【8選】

ではさっそく、本題である「専門商社はやめとけと言われる理由」を紹介しますね。
専門商社のデメリットとしてよく言われる内容を網羅的にまとめました。
リスクを把握しておくためにも、ぜひ目を通しておいてください。
【専門商社はやめとけと言われる理由】
- 激務でハードな会社が存在するから
- 仲介業ゆえに板挟みの状態になりやすいから
- 業務を遂行する上で専門知識の学習を求められるから
- 自分のミスで取引先に大きな迷惑をかける可能性があるから
- ノルマや数字に追われやすいから
- 人間力を求められることがプレッシャーになりやすいから
- 転勤や海外駐在を余儀なくされることがあるから
- 飲み会などを含めて人付き合いがストレスになるから
なお、就活を進める上では視野を広げることも重要です。
専門商社だけでなく、他の企業にも目を向けることで本当にあなたに合う就職先を見つけやすくなります。
視野を広げるためには、逆求人サイトを活用して企業からのスカウトを獲得するのがおすすめ。
大手ナビサイトで調べるだけでは見つからなかったような、穴場企業からスカウトが届くこともめずらしくありません。
僕がいま就活生だったら、スカウトの種類で企業の本気度がわかる「キミスカ」を利用しますね。
ゴールドとシルバーのみに対応することで、効率的にあなたに興味を持ってくれている企業と繋がれますよ。
登録から退会まで無料で利用できるので、ぜひ活用してくださいね。

理由① 激務でハードな会社が存在するから
もっともよくある理由は、激務なイメージがあることです。
専門商社でも総合商社でも、商社は業務が忙しくなりやすいと言われており、そのハードさからやめとけと言われることがあるわけですね。
ただ、実際のハードさは企業によっても当然異なります。
元も子もない話ですが、実際の残業時間がどのくらいか、休日出勤はどのくらいあるかなどは環境で決まる部分なんですよね。
よって専門商社への応募を考えている人は、懸念点の1つとして把握しておき、応募企業を厳選する際に個別に調べるのがよいかと。
専門商社では業界を特化しているゆえに取引先との関係が安定しており、突発的なトラブルが発生しにくいなどの側面もあります。
噂が全企業に当てはまるとは限らないので、ぜひ柔軟に対応してみてくださいね!
理由② 仲介業ゆえに板挟みの状態になりやすいから
専門商社は、企業と企業の間に入ってその差分で利益を得るような事業モデルです。
原材料を仲介する場合、原材料を製造するメーカーから仕入れをして、それ以上の価格で原材料を必要とする会社に販売するイメージですね。
ただ、仲介する立場だからこそ板挟みの状態にもなりやすいです。
たとえば、A社を仕入れ先・B社を販売先としたとき、B社がA社の製品に不満を持ったときにはその改善要求は専門商社が受けることになります。
品質以外にも、納期や物流などの部分で調整が必要になることは少なくありません。
専門商社の担当者はA社・B社の主張を取りまとめるような動きが求められるので、両サイドからプレッシャーがかかりがちなんですよね。
ときには、不本意ながらも謝罪を求められるような場面もあるかと。
このように調整力が求められる環境をストレスに感じる人は少なくないので、商社志望の人は事前に自分の適性を判断しておくことが大切です。
理由③ 業務を遂行する上で専門知識の学習を求められるから
専門商社で円滑に業務をこなすには、専門知識の習得が欠かせません。
仕入れ先・販売先ともにその業界に特化した企業と取引することになるので、専門知識がない状態だとそもそも会話が成り立たないんですよね。
とくに、専門商社は特定の分野や業界に特化していることを強みとしています。
ゆえに、専門商社で働く社員にもその分野の知見があることは前提として求められるので、知識のキャッチアップは必須になるわけですね。
企業によっては、入社時点での専門知識の有無は重視していないこともあります。
とはいえ、入社後の知識の習得はまず必須になるので、少なくとも自分が学習することに関心を持てる領域を選ぶことも重要と言えますね。
理由④ 自分のミスで取引先に大きな迷惑をかける可能性があるから
専門商社の仕事では、自分のミスで取引先に大きな迷惑をかける恐れがあります。
わかりやすい例として、仲介の立場である専門商社が納期を間違えて仕入れ先のA社に依頼をしていた場合、販売先のB社に迷惑がかかります。
納期以外にも、発注数やその種類などを間違えていた場合にも同様ですね。
文字にすると当たり前のことに感じるかもしれませんが、これらは企業の取引に関することなので、かなり大きなトラブルに発展する可能性もあります。
そもそも金額のスケールが大きいですし、原材料などが届かないことで工場の生産体制を止めざるを得ないなどの事態にも発展する恐れがあるかと。
自分のミスが、企業単位でのかなり大きなトラブルにつながる可能性もあるわけです。
他の業界や企業でもこういったリスクは存在しますが、専門商社の大変さの1つとして事前に頭に入れておくようにしましょう。
理由⑤ ノルマや数字に追われやすいから
主に営業職の場合は、数字などのノルマに追われることが一般的です。
企業によって求められる役割はさまざまですが、新規の取引先開拓数が指標となって業務を任されるようなケースも珍しくありません。
すでに安定した取引先が確立されている場合でも、取引成立数や売上・利益などの数字が指標として置かれることは多くあります。
ノルマ制度は専門商社に限らず存在しますし、どのように感じるかも人それぞれです。
ただ、数字に追われる環境にネガティブな印象を持つ人はストレスを感じる恐れがあるので、想定されるリスクとして知っておくとよいでしょう。
理由⑥ 人間力を求められることがプレッシャーになりやすいから
商社の担当者として成果を上げるには、人間力が必要と言われることがあります。
商社自体は自社商品を持っておらず、原材料などを手掛ける会社・その原材料を必要とする会社の間に入ることで利益を得ていますよね。
そして取引先視点で考えると、自社(商社)と取引するかどうかは選択できます。
商社は他にも存在するわけですし、その上でどの商社と取引するかを決める上では担当者の人柄や人間性などが判断材料とされるケースが多々あるわけですね。
商社で働くと「人間力が付加価値」などの言葉を耳にすることがあるかもしれません。
こうした言葉からもわかるように、担当者には人間力の高さが求められやすいです。
もちろん企業や取引先によっても異なるという前提ですが、こうした部分にプレッシャーを感じる人は懸念点として押さえておくべきですね。
理由⑦ 転勤や海外駐在を余儀なくされることがあるから
専門商社では、転勤や海外駐在などを指示されることがあります。
応募時点でもこうした条件は提示されているはずですが、とはいえ実際に自分が体験すると不満を感じるという人は少なくありません。
商社は、ビジネスモデル的に数多くの企業と取引をおこなうことが必須です。
ゆえに国内外問わず拠点を設けて、各拠点に人材を配置することでグローバル全体で事業をおこなっているケースが主流なんですよね。
よって社員に対しても、引越しを伴う転勤などを命じられることがあるわけです。
とくに家族や子どもがいる場合には自分だけの話ではないですし、居住地にこだわりがある人はデメリットの1つとして意識しておくべきですね。
理由⑧ 飲み会などを含めて人付き合いがストレスになるから
商社では、社内外で飲み会や接待に参加する機会が多くあります。
シンプルに社内での交流を深める目的の飲み会はもちろん、取引先の企業と関係を深めるために接待の機会も多々あるんですよね。
商社が接待することもあれば、取引先から接待を受けることもあります。
仲介の立場として複数の企業と取引をしているからこそ、業務外の部分で飲み会などに参加する機会も多くなりがちなわけですね。
これも、なかにはむしろポジティブな要素に感じる人もいるかもしれません。
一方で、飲み会などの人付き合いが多いことをストレスに感じる人もいると思うので、相性を判断する際には1つの材料にしてみてください。
仲介する立場だからこそ板挟みの状態になりやすい、飲み会などの接待が多く発生するといった懸念点があるんですね。
シンプルに多忙になりやすいこと、ノルマに追われること、自分のミスで取引先に迷惑をかける可能性があることなどもデメリットとしてよく言われる内容だよ。
【結論】専門商社への就職はやめておくべきか?

「結局のところ専門商社はやめておくべきか?」が知りたい人も多いと思うので、先にこの問いに答えておきますね。
僕の結論は以下のとおりです。
【専門商社に対する僕の考え】
激務な傾向がある、仲介業ゆえに板挟みの状況になりやすいなどの理由から「専門商社はやめとけ」と考える人は多くいる。
一方で、総合商社と異なり自分が気になる業界を選べる、グローバルで活躍チャンスがあるなどのメリットも存在する。
つまり、よい面・悪い面の両方があるため一概に「やめとけ」と断言はできない。
どのように評価するかは個々人の価値観や感覚によって異なるため、情報を集めた上で自分なりの結論を下すことが重要と言える。
僕が考える向いている人の特徴は以下のとおり。
- コミュニケーション力や信頼関係構築力がある
- さまざまな人と関わることが好き
- 分析力がある
反対に、向いていない人の特徴は以下のとおり。
- 社交性を求められる役割に苦手意識がある
- インプットを続けることにストレスを感じる
- 広く浅い知識よりも狭く深い知識を好む
上記もあくまで傾向の話であり、同様の情報は多く出回っている。
だからこそ、各情報を鵜呑みにしないで判断材料として収集し、自分との相性を冷静に考えた上で最終的な結論を下すべきである。
専門商社に限らず、「◯◯はやめとけ」といった意見は多く存在します。
ただ、万人に共通するような結論はなくて、結局はそれらのメリット・デメリットを自分がどう判断するか?が重要なんですよね。
大事なのは「自分に向いているか?」を考えることなので、ぜひこの視点を持った上で次章以降も読み進めてみてください!
なるほど!ネットでどのように言われているかは気になりますが、それらを盲信するのではなく判断材料を増やすために情報に目を通すのが大切ですね。
まさにそのとおり。ネガティブな意見には極端なものも多いし、そうした意見ほど拡散されやすい部分もあるから、フラットな視点で情報を受け止めるべきだよ!
専門商社に就職するメリット【7選】

次にこの章では、専門商社に就職するメリットを紹介します。
専門商社に限らずですが、どんな業界や職種にもメリット・デメリットの両方が存在するんですよね。
片方だけの意見に目を通していたら、フラットな判断はできません。
自分との相性を冷静に判断するためにも、専門商社のポジティブな部分もぜひチェックしておいてください!
【専門商社に就職するメリット】
- 仕事の成果を売上などの数字として実感できる
- 総合商社と異なり自分が気になる業界を選べる
- 自分が関わる業界の専門性が高まる
- グローバルで活躍できるチャンスがある
- さまざまな人と関わる機会がある
- 経営課題の解決に関わる機会がある
- 総合商社と比べて内定を獲得しやすい
メリット① 仕事の成果を売上などの数字として実感できる
専門商社のデメリットとして、数字やノルマに追われやすいことを伝えました。
これに対してポジティブな見方をすると、自分の仕事の成果を具体的な数字として実感しやすい業務とも言えるんですよね。
自分が価値提供できていることを実感すると、日々モチベーションを感じやすいです。
逆に自分ががんばっていると思っているのに、周囲の評価につながるような明確な成果として表れないと、不満を抱く原因になりやすいんですよね。
何がモチベーションにつながるかも人それぞれですが、自分の努力が適切な評価として反映されるかどうかは重要な要素になりやすいです。
この観点で考えると、専門商社ではやりがいを感じやすいと言えそうですね。
メリット② 総合商社と異なり自分が気になる業界を選べる
総合商社に入社した場合、自分がどの業界の企業と関わるかは配属で決まります。
会社自体が多種多様な分野の企業と取引をしていて、実際に自分が関わる業界がどこになるかは会社の人事配置で決まるわけですね。
別の言い方をすると、自分が関わる業界はギャンブル的に決まるわけです。
対して専門商社は、そもそも会社自体が関わる分野を特化しているので、入社前の段階から自分にとって関心のある業界を選べるんですよね。
よって、自分が関心のない分野で業務をしないといけない事態を避けられます。
やはり自分の関心度合いによって仕事への熱量は変わりやすいですし、その観点で自分の希望を叶えやすい専門商社は魅力的と言えるかもしれません。
メリット③ 自分が関わる業界の専門性が高まる
専門商社で働くと、その会社が特化している業界の知見が深まります。
そもそも知識をインプットしないと取引先の企業と円滑にやり取りできないので、専門知識を学び続けることは欠かせません。
業界のトレンドや全体像についても、自然と理解が深まると思います。
すると転職を考えたときにも、その業界の専門性がある人材として商社以外の会社からも関心を持ってもらえやすいんですよね。
このように長期で働くことによるメリットもあるので、最初の段階で自分が気になる分野の専門商社を志望しておくことは大切です。
特定の領域の専門性を身につけたい人にとっても、専門商社はアリと言えますね。
メリット④ グローバルで活躍できるチャンスがある
専門商社では、グローバルを舞台に活躍できるチャンスも多くあります。
ビジネスモデル的にさまざま企業と取引をしているので、国内外問わず複数の拠点を構えていることが通常なんですよね。
海外で仕事をすると、公私の両面で視野が広がることが多くあると思います。
国内から海外スタッフなどとやり取りするという場合でも、世界を相手に業務ができていることにやりがいを感じられるかもしれません。
なかには、若手社員にもどんどん海外業務を任せる会社も存在します。
他の業界と比べても海外で活躍する機会を得やすい印象があるので、グローバルで活躍したい思いが強い人もぜひ候補として検討するといいですよ!
メリット⑤ さまざまな人と関わる機会がある
専門商社に勤務すると、さまざまな人と関わる機会があります。
仕入先や販売先というように考えると2社だけで完結しますが、当然ながらそれぞれ複数の企業やメーカーと関わることになるんですよね。
新規開拓の営業の場合は、どんどん新たな企業と接点を持つことになります。
新規開拓でなくとも、仕入先や販売先の関係者はもちろんのこと、社内外の打ち合わせや接待などを通じて関わる人はかなり多岐にわたるんですよね。
こうした付き合いは、自分自身の人間的な成長や成熟にもつながると思います。
人付き合いが苦手な人にとってはデメリットかもしれませんが、人間関係や知見を深めることに魅力を感じる人には相性がよいと言えますね。
メリット⑥ 経営課題の解決に関わる機会がある
6つ目は、経営課題の解決に関わる機会があることです。
専門商社の担当者は、企業の経営状況に直結するような取引に関わることもあります。
たとえば中小企業が販売先で、かつ機械や設備の導入を検討している場合。
こうした機械などはかなりの高額ですし、その投資対効果によっては企業の経営状況が大きく変わるといった事態も可能性としてあるんですよね。
上記のような状況で取引先に本質的な価値を届けるためには、その企業の経営状況などを踏まえた上で取引の提案をすることが求められるかと。
目先の利益を追っても、長期的によい関係を築くことはできないですからね。
このような機会も、人にとってはプレッシャーに感じるかと思います。
ただ、経営に近い場に関わるからこそ得られるものも多くあるので、成長や経験などの観点ではメリットが大きいと言えるでしょう。
メリット⑦ 総合商社と比べて内定を獲得しやすい
求職者視点のメリットとして、内定を獲得しやすいこともあります。
5大商社と言われる三菱商事や三井物産などの総合商社は、世間一般的に誰もが知る会社であり、その分人気や採用倍率がかなり高いです。
対して専門商社は、総合商社と比べると知名度が劣るゆえにエントリー数も少なく、採用倍率も低くなりやすいんですよね。
状況にもよりますが、内定を獲得できると余裕や自信にもつながります。
商社として働くことの優先順位が高い人は、総合商社にこだわりすぎないで専門商社への応募も検討してみてはいかがでしょうか。
自分が気になる業界に携われること、内定獲得のハードルが低い傾向にあることは、専門商社ならではのメリットと言えそうですね。
総合商社では自分が興味のなかった分野に配属されることもよくあるし、自分が関わりたい業界を選べることはとくに大きなメリットと言えると思うよ!
専門商社に向いている人の特徴【3選】

続いてこの章では、専門商社に向いている人の特徴を紹介します。
ここまでの内容を踏まえて、僕なりに専門商社と相性のよい人の特徴をまとめたので、適性の判断に迷っている人はぜひ参考にしてみてください。
【専門商社に向いている人の特徴】
- コミュニケーション力や信頼関係構築力がある
- さまざまな人と関わることが好き
- 分析力がある
特徴① コミュニケーション力や信頼関係構築力がある
専門商社の仕事は、人とのコミュニケーションがなくては成り立ちません。
相手のニーズを汲み取ったり、こちらの意見を適切に伝えたり、対話を通じてお互いの考えを深めたりとコミュニケーション能力が必須なんですよね。
そもそも取引先の企業と信頼関係を築けないと、深い会話もできないと思います。
取引先からすると別の商社という選択肢もあるわけなので、そのなかで契約を得るためには人間的に関係を築くことが重要なんですよね。
コミュニケーション力はあらゆる業界・企業で必要とされるものですが、とくに商社では優先度の高い能力です。
適性を判断する際には、第一に会話力や信頼関係構築力の有無を考えてみてください。
特徴② さまざまな人と関わることが好き
上述したとおり、商社の人材にはコミュニケーション力が求められます。
加えて向いている人の特徴を考えると、単に人付き合いが得意なだけでなく、そもそも本心から人と関わることが好きな人に適性があるかと。
やはり表面上で円滑に会話ができるだけというよりは、本心でさまざまな人と付き合いたい気持ちがある人のほうが魅力的に見えやすいんですよね。
感覚的にも、こうした思いがあるかどうかは伝わるものだと思います。
だからこそ仕事や取引先であることなどに関わらず、人間的に多くの人と関係を持ちたい人のほうがより適性があると言えるかと。
理想的な話かもしれませんが、1つの判断材料としてぜひ参考にしてみてください!
特徴③ 分析力がある
異なる視点として、分析力がある人にも向いている可能性が高いです。
専門商社は企業間を仲介する役割ですが、単にマッチングを成立させるのではなく、双方にとってWin-Winな取引を仲介することが求められます。
市場や将来性など、社会状況やトレンドを考慮しておくことも欠かせません。
そうした市況も踏まえて取引の仲介に関わっていないと、長期的に自社や関係者にとってメリットのある取り組みになりにくいからです。
そして本質的に価値を生む取引を成立させる上では、市場データや経済状況などの情報を分析してアウトプットすることが求められるわけですね。
コミュニケーション力とは毛色が違う能力ですが、ぜひ頭に入れておくといいですよ!
やはり円滑にコミュニケーションできることは必須で、かつそもそも人と関わることが好きな人ならより相性がよいと言えるんですね!
専門商社をおすすめできない人の特徴【3選】

次にこの章では、専門商社をおすすめできない人の特徴をまとめました。
僕なりに相性がよくないと考える人の特徴を整理したので、自分の適性の判断に迷っている人は本章の内容もぜひ参考にしてみてください。
【専門商社をおすすめできない人の特徴】
- 社交性を求められる役割に苦手意識がある
- インプットを続けることにストレスを感じる
- 広く浅い知識よりも狭く深い知識を好む
特徴① 社交性を求められる役割に苦手意識がある
繰り返し伝えているように、商社の社員には人間関係構築力が求められます。
仕事で成果を出すためには、さまざまな関係者とうまくコミュニケーションを取る必要がありますし、それがすべての基盤になるんですよね。
業務外でも、社内外で飲み会や接待などの機会も多くあります。
よって、こうした業務の特徴をネガティブに感じたり、接待などの機会に意味を見出せなかったりする人はストレスを感じる可能性が高いです。
これはあくまでも相性の話なので、たとえば「接待などが嫌だから向いていない」と考えたとしても決して悪いことではありません。
むしろミスマッチを防ぐ意味で大切なので、ぜひ素直な感覚で判断してみてくださいね。
特徴② インプットを続けることにストレスを感じる
専門商社の社員として成果を出すには、専門知識の学習も必須です。
対象となる分野の知識が少ない入社時点はもちろんですが、それ以降も社会や市場の変化に伴い情報収集を続けることが求められるんですよね。
こうした知識が少ないと、その業界のプロである取引先の人と会話ができません。
すると取引先の担当者からも信頼を獲得できませんし、結果的に自分も業務で成果をあげられないなどの事態につながるんですよね。
よって、インプットを続けることに苦痛を感じる人には向いていないかもしれません。
この学習意欲は対象となる分野によっても変動すると思うので、専門商社のなかでも志望する業界を考える際には意識しておくことをおすすめします。
特徴③ 広く浅い知識よりも狭く深い知識を好む
専門商社は、特定の分野や業界に特化して主に仲介業務をおこないます。
これだけ聞くと、その分野の専門知識を深く学ぶような印象を持つかもしれません。
ただ、業界全体の知識を深めることはもちろんですが、そこから細分化した分野の情報は広く浅くインプットすることが求められやすいです。
たとえば、鉄に関する専門商社に勤める場合。
前提として鉄に関する知見を深めることも大切ですが、実際に扱う商品レベルで考えるとその対象はかなり多岐にわたります。
原材料やネジ・治工具・大型機械など、さまざまな商品や素材が想定されますよね。
理想はこれらの商品単位でも深い知見を持つことですが、現実的には工数の兼ね合いからそれぞれ浅い知識の習得にならざるを得ません。
つまり、どうしても広く浅い知識を学ぶような状況になりやすいわけですね。
これも良し悪しではないですが、特定の狭い分野を追求したい人はモヤモヤを感じる可能性があるので、1つの材料として知っておくとよいでしょう。
コミュニケーション力に自信がない人はもちろん、飲み会や接待などの場を避けたい思いが強い人もやはり相性は悪そうですね。
加えて、インプットや広く浅い知識の習得を求められる環境に魅力を感じない人も、専門商社との相性は微妙と言えるかもしれないね。
専門商社への就職を後悔しないためのポイント

続いて本章では、専門商社への就職を後悔しないためのポイントを紹介します。
ミスマッチを含めて後悔を防ぐ上で僕が重要と考える内容をまとめたので、専門商社への応募を考えている人はぜひ一読してみてください。
【専門商社への就職を後悔しないためのポイント】
- 専門商社と自分の相性を冷静に判断する
- どの業界に関わりたいか?を言語化しておく
ポイント① 専門商社と自分の相性を冷静に判断する
大前提、専門商社との相性を冷静に判断することを徹底しましょう。
就活で企業を選ぶ際には、内定の得やすさ・社会からの評価の高さ・給料や待遇の良さなどを意識するものだと思います。
ただ、いくら上記などが優れていても、自分との相性が悪い企業に入ったらミスマッチや早期退職につながる恐れがあるんですよね。
これでは苦労して内定を得ても、長期的に考えると健全とはいえないと思います。
だからこそ、専門商社を迷っているならまずは相性をじっくり検討してください。
どんな業界や職種にも「やめとけ」などの声はありますが、最終的にはそれらの観点を自分がどのように感じるか?がすべてです。
すべての人が満足だけできるような業界や会社は存在しません。
だからこそ、気になる業界の良い面・悪い面の両方を踏まえて相性を判断することが肝になるので、ぜひ時間をかけて適性を判断してみてください。
ポイント② どの業界に関わりたいか?を言語化しておく
専門商社を志望すると決めたら、業界の希望も明確にしておきましょう。
総合商社と違って自分が関わりたいと思う業界を選べるので、ここを妥協して企業を選んでいてはかなりもったいないです。
業務のなかでその分野の専門性も高まっていきますし、せっかく知見を深めるなら自分が興味のある分野に越したことはありません。
専門知識を学んでいく過程でも、モチベーションには違いが生まれるはずですよ。
誰しも業界によって、自分の興味関心の大きさには違いがあると思います。
「専門商社であればどこでもよい」といった考えではなく、ぜひ志望業界にこだわりを持って企業選びを進めてみてくださいね。
たしかにミスマッチや早期退職につながる選択は確実に避けたいですね…!
相性の判断を間違えるとミスマッチなどを起こしやすいから、業界や企業選びの段階でじっくり時間をかけて冷静に判断することが大切だよ。
専門商社の選び方【見極めるための3つのポイント】

専門商社への就職を検討する上で大切になるのは、「どの専門商社を選ぶか?」です。
専門商社とひとくちに言っても、業界や企業によって環境や働き方が大きく異なります。
そこでこの章では、専門商社を選ぶ際の具体的な見極めポイントを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
【専門商社を選ぶときのポイント】
- 労働環境を事前にチェックする
- 業界や商材の将来性を調べる
- 面接で企業文化や働き方を確認する
①労働環境を事前にチェックする
まず最も重要なのは、応募する専門商社の労働環境を調べることです。
口コミサイトや就活エージェントを活用して、実際に働いている社員の声や、企業の残業時間・休日などの実態をチェックしましょう。
たとえば、以下の情報を収集しておくとミスマッチを防げます。
【労働環境を調べる際に確認すべき項目】
- 平均残業時間
- 年間休日数
- 有給休暇の取得率
- 離職率
- 社員の口コミ(飲み会や接待が多いかなど)
口コミサイトは「OpenWork」や「ライトハウス」などが口コミ数も多いのでおすすめです!
ただし、口コミはあくまでも個人の主観的な内容であることを認識しておきましょう。
よって、1つの口コミだけを信じるのではなく、必ず複数の口コミサイト・投稿を比較して判断してくださいね。
②業界や商材の将来性を調べる
次に、専門商社が取り扱う業界や商材の将来性をチェックしてください。
専門商社は特定の分野に特化しているため、その分野の市場動向が企業の成長に大きく影響します。
たとえば、成長が期待される分野として以下が挙げられます。
【将来性が期待される分野の例】
- 再生可能エネルギーや環境関連
- AIやIoTなどのテクノロジー分野
- 医薬品やバイオ関連
一方で、縮小傾向にある業界は将来的にリスクが高まる可能性があります。
興味のある分野がある場合は、その業界の市場動向や成長性をリサーチしておきましょう!
③面接で企業文化や働き方を確認する
最後に、面接時に企業の実態を確認することも効果的です。
以下のような質問をして、職場の雰囲気や働き方について具体的なイメージを掴んでみてください。
【面接で確認すべき質問例】
- 残業時間や休日の取得状況について具体的に教えてください。
- 入社後の研修やキャリアパスの支援制度はありますか?
- 若手社員の活躍事例を教えてください。
- 社員同士のコミュニケーションはどのように取られていますか?
面接は企業が採用する人材を決める場だと思いがちですよね。
しかし同時に、「その企業が自分に合っているのか?」をあなたが判断するための場とも言えます。
企業文化や働き方を確認し、自分との相性を冷静に判断してくださいね!
専門商社を選ぶ際に、具体的な見極めポイントがあると安心感が増しますね!
そうだね!選び方を知っておけば、自分に合った企業を見つけやすいし、後悔も減るはずだよ!
「専門商社 やめとけ」と調べる人からよくある質問

最後の章では、「専門商社 やめとけ」と調べる人からよくある質問に回答します。
似た疑問を抱いていた人がいたら、ぜひ以下の回答を参考にしてみてください。
【「専門商社 やめとけ」と調べる人からよくある質問】
- 専門商社の平均年収はいくらくらい?
- 専門商社は勝ち組と言える?
- 専門商社の中小企業の具体例は?
- 専門商社に将来性はないと聞いたけど本当?
- 専門商社をやめたいと感じる理由で多いものは?
- 専門商社ではスキルが身につかないの?
質問① 専門商社の平均年収はいくらくらい?
マイナビエージェントの情報によると、専門商社の平均年収は423万円でした(参考)。
年代別に見ると、20代では391万円、30代では507万円となっていました。
比較材料として、日本全体の平均年収のデータも共有しておきますね。
国税庁が公表している「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与は458万円となっていました。
よって全体平均と比べると、専門商社の平均年収はやや低めと言えます。
もちろん企業によって大きく異なる部分ですが、全体感を把握しておきたい人は上記を参考にしてみてくださいね。
質問② 専門商社は勝ち組と言える?
何を持って勝ち組と捉えるか?によるので一概に言えません。
専門商社に限らず、企業や職業に関して勝ち組・負け組と考える人は一部います。
ただ、勝ち組などと考える基準は人によるので、どんな企業や職業であっても万人に共通して言える結論はないんですよね。
個人的には、勝ち組かどうかなどは比較対象がいるという前提があるので、あまり考えてもメリットがない話だと考えています。
上を見たら切りがないですし、自分が上といった発想もやはり微妙だと思いますからね。
質問③ 専門商社の中小企業の具体例は?
【専門商社の中小企業の具体例】
- 西本Wismettac HD
- 遠藤科学
- 東京貿易HD
- ミツウロコグループHD
- アイナボHD
- OUG HD
- エービーシー商会
- 島田商会
- 伊藤忠TC建機
- 岩井産業
- レスターHD
- ENEOSウイング
- ほくやく・竹山HD
- 森六HD
- 井田両国堂
- CBグループマネジメント
- セイエル
- 小泉
- 吉田石油店
- ティーエムシー
ここでは、四季報を中心に年収や売上が優れた会社をピックアップしました。
専門商社の中小企業をエントリー候補として考えている人は、ぜひ気になる企業がないか個別にチェックしてみてくださいね。
質問④ 専門商社に将来性はないと聞いたけど本当?
結論、専門商社の将来性は扱う領域や商材によると考えています。
極端な例として、市場の発展が著しいAIなどの分野と古くから存在するレガシーな分野があったら、将来性を感じるのはきっと前者ですよね。
総合商社と異なり専門商社は特定の分野や業界を対象としているので、事業の対象によって企業の将来性には違いがあるわけですね。
よって将来性が気になる場合は、候補企業の対象領域を確認すべきかと。
その分野の将来性が明るければ候補の専門商社も同様の可能性が高いので、判断材料としてぜひ参考にしてみてください。
質問⑤ 専門商社をやめたいと感じる理由で多いものは?
長時間労働や板挟みの状況がつらい、人間関係を構築することや接待などが多い環境にストレスを感じるなどがあげられますね。
労働環境に関しては、企業によって大きく異なる部分です。
板挟みになりやすい、接待などが多いといった点は、程度に差はあれど商社なら共通して起こりやすい内容ですね。
よって前者なら企業次第で改善可能、後者は商社との相性の問題と言えるかと。
これから専門商社へのエントリーなどを考えている人は、自分も似た状況にならないように事前に相性を考えておきましょう。
質問⑥ 専門商社ではスキルが身につかないの?
専門商社で働くと、次のようなスキルが身につくと考えられます。
【専門商社で身につくスキルの例】
- コミュニケーション能力
- 信頼関係構築力
- 調整力
- 交渉力
- 提案力
- リーダーシップ
- 分析力
- 論理的思考力
たとえば、ITエンジニアなどのようにわかりやすいスキルはないかもしれません。
ただ、業務で成果をあげようと取り組む過程では、上記のように多岐にわたるスキルを自然と習得できる可能性が高いんですよね。
「専門商社ではスキルが身につかない」とは僕は思わないので、1つの意見になりますがぜひ参考にしてみてください。
専門商社の将来性を判断する際に、扱う業界や分野の見通しを考えるという発想はまさにそうだと納得しました!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
専門商社の概要や結論どうか?を伝えた上で、やめとけと言われる理由や求職者視点でのメリットなどを網羅的に共有しました。
また専門商社だけでなく、総合商社については別記事で書いているので、ぜひ合わせて読んでみてください。
» 【総合商社はやめとけ?】事前に確認すべきデメリットを調査!
専門商社は、仲介する立場ゆえに板挟みの状態になりやすいなどの懸念があります。
ただ、自分が気になる業界に携われる、総合商社と比べて内定獲得のハードルが低い傾向にあるなどのメリットもあるんですよね。
よってこれらの両面を押さえた上で、自分との相性を判断すべきかと。
専門商社に限らず一般的な意見が自分にも当てはまるとは限らないので、情報を集めた上で自分にとってはどうか?をぜひじっくり考えてみてくださいね。
ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「就活マンが考える「就活を成功させるために必須の6大ポイント」を共有!」も読んでみてください。
僕が現状考えるもっとも有効な就活の攻略法を簡潔にまとめています。
就活全体を見据えてとくに重要な対策のみを厳選しているので、全体を意識した対策ができていない人はぜひ一読してみてください。
それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!
【本記事の要点】
- 専門商社は、特定分野に専門性を持ちトレーディングをメイン事業とする会社である。
- 専門商社はやめとけと言われる理由には、仲介する立場だからこそ板挟みの状態になりやすい、飲み会や接待が多く発生するなどがある。
- 総合商社と違い、自分が興味のある領域や分野を選べることはメリットである。
- 適性を考える上で、コミュニケーション能力の有無はやはり重要度が高い。
- ミスマッチや早期退職を防ぐためにも、自分との相性を冷静に判断すべきである。







