
今回の記事では、逆質問とは何か?についてバシッと解説します!
(概要だけでなく、企業側の質問意図やおすすめ例一覧・考え方まで共有するよ!)
こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。
逆質問とは、面接の最後に「何か質問はありませんか?」と聞かれる質問のこと。
面接官に対してこちらが質問をするので、逆質問と呼ばれていますね。
慣習的に何となく聞かれているだけと考える人もいますが、企業側も意図を持って逆質問を求めているので軽視するのは危険です。
むしろポイントを押さえれば高評価につなげられるチャンスにもなりますし、事前にできる限りの対策をしておくのが理想ですね。
この記事では、逆質問の概要と妥協すべきではない理由を共有した後に、企業側の質問意図やおすすめの質問例を一覧で紹介します。
逆質問の具体的な考え方やマイナス評価を避けるための注意点も共有するので、逆質問の対策が十分できていない人はぜひ最後までご覧ください!
逆質問に不安があります。
慣れないからこそ不安があるよね。なぜ企業側は逆質問をするのか、どんな質問をすべきなのか、この記事ではそれぞれ詳しくお伝えするよ!
- 面接における逆質問とは?
- 逆質問を求める企業側の意図
- 就活面接で使える逆質問のおすすめ例一覧【1位〜20位】
- 逆質問の具体的な考え方【3ステップで解説】
- 逆質問でマイナス評価を避けるための注意点
- 逆質問に力を入れて対策しておくメリット
- 逆質問に関してよくある質問
- 本記事の要点まとめ
面接における逆質問とは?

冒頭でもお伝えしたとおり、逆質問とは面接の最後に面接官からされる「何か質問はありませんか?」という質問のこと。
これだけを聞くと、ただ何となく聞かれているだけで特別力を入れる必要はないと感じる人もいるかもしれません。
ただ結論、逆質問は軽視せず事前に対策をしておくべきですよ。
最初の章では逆質問の対策に力を入れるべき理由をまとめたので、前提知識としてさくっと見ていきましょう。
【逆質問への対策を妥協すべきではない理由】
- 志望度や熱意の高さを探る参考にされているから
- 最後の質問ゆえに面接後の印象を左右しやすいから
理由① 志望度や熱意の高さを探る参考にされているから
最大の理由は、志望度や熱意を探る参考にされているからです。
逆質問は企業への志望度が高い人ほど、より具体的で熱のこもった質問をする傾向があるんですよね。
これは恋愛に置き換えて想像するとわかりやすいかと。
仮に異性に何かしらの質問ができるとなったとき、自分が気になる人とどうでもいい人の2人が相手だとしたら質問内容は変わってきませんか?
気になる人が相手のときのほうが、よりじっくり考えて質問を投げかけるはずです。
面接の場でも同様で、企業側もこの点を理解しているからこそ逆質問の中身によって志望度を探っている側面があるわけですね。
企業は面接全体を通して志望度の高さを探っていますが、逆質問も判断材料にされているので妥協せずに対策しておくべきですよ!
理由② 最後の質問ゆえに面接後の印象を左右しやすいから
面接後の印象を左右しやすい点も理解しておくといいですね。
「終わりよければすべて良し」という言葉があるように、最後の印象は面接全体が終わってからの印象にも影響しやすいです。
逆質問はまさに面接最後に聞かれるものなので、この質が低いと全体の印象にも悪影響が生じてしまう可能性があるわけですね。
それまでの回答がしっかりできていたのに適当に逆質問して低評価を受けるのはもったいなすぎるので、ぜひ事前に対策しておきましょう。
たしかに質問する相手や企業の気になり具合が高いときほど、聞きたい内容の深さや熱量は高くなりそうですね。
面接官は数多くの就活生を相手にしているからこそ、質問内容が浅いとすぐ見抜かれるし、その場を乗り切るような気持ちだけで質問を考えるのは避けるべきだよ。
逆質問を求める企業側の意図

次にこの章では、逆質問を求める企業側の意図を紹介します。
逆質問に限らず、企業はすべての質問において何かしらの意図を持っています。
この意図を知っておいたほうが、評価につながる対応を考えやすくなるんですよね。
面接官に刺さる逆質問をするためにも、相手の意図をさくっと確認しておきましょう。
【逆質問を求める企業側の意図】
- 志望度の高さを判断する材料にするため
- 単純に就活生の疑問を解消するため
- 自然なコミュニケーション能力を確認するため
意図① 志望度の高さを判断する材料にするため
繰り返しになりますが、まずは志望度を判断する材料にする意図があります。
極端な話、志望度が低い人なら質問しない可能性すらありますし、対応によって応募者の熱意を探るヒントにできるんですよね。
この意図を踏まえると、単に疑問を解消するだけというよりは「どうしたら熱意を伝えつつ逆質問できるか?」を考えるのが理想といえるかと。
その点で「大丈夫です」「結構です」などと伝えるのは論外なので、何かしらの熱意が伝わる質問を考えておくようにしましょう。
意図② 単純に就活生の疑問を解消するため
純粋に就活生の疑問を解消する機会にしたいという意図も考えられますね。
企業側もミスマッチは避けたいと思っているので、自社のことを応募者に把握してもらった上で入社を決めてほしいと考えています。
その点、直接質問を募れる逆質問の場はいい機会になるんですよね。
企業内部の人と直接話せる機会って意外とないですし、面接官も評価を下したいだけではなく応募者側に寄り添う気持ちもあるわけです。
よって、本当に聞きたいことがあればときにはそのまま質問するのもアリかと。
ただし、後述する注意点など意識すべきこともあるので、ほかの意図やポイントも把握した上で最終的な質問を考えるようにしてくださいね!
意図③ 自然なコミュニケーション能力を確認するため
志望動機や自己PRなどと比べると、逆質問は超定番の質問ではありません。
逆質問とは何か?を知らない人もいますし、応募者のなかには本番のその場で思いついた質問をする人も少なくないですからね。
ゆえに逆質問は、その人の本来のコミュニケーション能力を探る機会にもなります。
確実に事前に対策する志望動機などと比べてガチガチに準備する人は少ないので、リアルな会話力が試されるわけですね。
よって応募側は、円滑なやり取りをすることも意識しておくべきです。
質問して返事をもらって終わるだけでなく、ときにはその後のリアクションや深掘り質問が必要になるので、質問以外も気を抜かないようにしましょう。
志望度や熱意の高さを探る以外にも、企業側はいくつかの意図を持っているのですね。
気になることを聞くだけでは微妙だから、ほかの意図も確実に押さえておくといいよ!
就活面接で使える逆質問のおすすめ例一覧【1位〜20位】
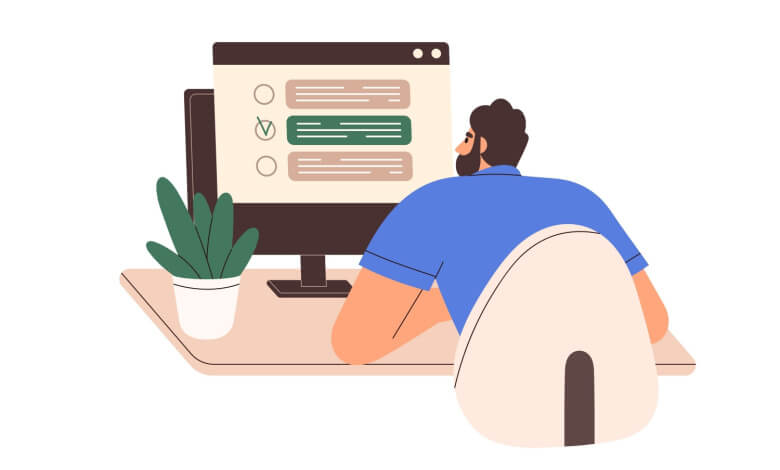
逆質問の概要や企業側の質問意図を共有しました。
企業視点も踏まえて逆質問の位置づけを知ったことで、理解が深まり重要性も認識してもらえたかと思います。
続いてこの章では、逆質問の具体例を一覧にして共有しますね。
僕が就活生におすすめしている逆質問ランキングは以下のとおりです。
| 順位 | おすすめの逆質問例 | 質問場面(質問対象者) |
|---|---|---|
| 1位 | 面接を通しての私の印象はどうでしたか? | 全選考 |
| 2位 | 私は◯◯な性格で◯◯な方と合うと考えているのですが、そういった社員さんは多いですか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 3位 | 御社にこんな商品があればいいなと思った商品を考えてきました。披露しても宜しいでしょうか? | 二次・最終(人事・役員) |
| 4位 | 私の最大の強みは◯◯なのですが活かせる場面は多いでしょうか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 5位 | 今のうちから絶対にやっておくと入社後に役立つと思うことがあれば教えて頂きたいです | 二次・最終(人事・役員) |
| 6位 | 御社で活躍している社員さんの特徴はありますか? | 二次・最終(人事・役員) |
| 7位 | 競合他社と比較した際の御社の最大の強みは◯◯だと考えているのですが、いかがでしょうか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 8位 | 入社後に一番に感じたギャップがあれば教えてください | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 9位 | 御社に入社する前に意識しておくべきこと、覚悟しておくべきことはありますか? | 二次・最終(人事・役員) |
| 10位 | いつか◯◯職への配属を希望しているのですが、◯◯職に必要な経験やスキルは何でしょうか? | 二次・最終(人事・役員) |
| 11位 | 今後注力していこうと全社的に考えている事業はどのような事業でしょうか? | 二次・最終(人事・役員) |
| 12位 | 御社の若手の社員さんに多い性格の特徴があれば教えてください | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 13位 | 今後どのような人材を特に採用したいと考えていますか?理由とともにお聞かせ願いたいです | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 14位 | ◯◯職の1日の仕事の流れをザックリでも教えて頂きたいです | 一次(現場社員) |
| 15位 | お酒が大好きなのですが、飲み会は多いでしょうか? | 全選考 |
| 16位 | 御社の人材評価はどこを重視されているか教えて頂きたいです | 二次・最終(人事・役員) |
| 17位 | 仕事を通して最もやりがいや達成感を感じる場面を教えてください | 一次(現場社員) |
| 18位 | 活躍されている女性社員の方はどのような方でしょうか?復職された方はいらっしゃいますか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 19位 | 部門間の交流は活発でしょうか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
| 20位 | ジョブローテーションは比較的活発に行われているでしょうか? | 一次・二次(現場社員・人事) |
面接フェーズによって担当する面接官や企業側の視点は変わるので、逆質問もフェーズによって使い分けられると理想的ですね。
上記それぞれの質問意図、なぜおすすめか?などは別記事にてまとめています。
背景まで知ると質問が有効な理由や、そのほかの逆質問を考える際の参考にできるはずなので、ぜひあわせて一読してみてくださいね!
逆質問を万全に対策したいなら第三者の客観的な意見をもらうべし
補足として、プラスαのおすすめ対策も共有しておきますね。
結論、逆質問を含めた面接対策を万全にして本番に臨みたいなら、ぜひ模擬面接を受けて第三者から客観的な意見をもらってみてほしいです。
どうしても自分ひとりだけで対策していると、主観的な意見だけで視野が広がりにくくて改善の幅にも限界があるんですよね。
よってひとりで対策→ぶっつけ本番ではなく、模擬面接で客観的な意見をもらって改善してから本番に臨んでほしいと僕は考えています。
ただ、模擬面接のいい感じの相手がいなくて諦めている人が多い印象なので、面接相手のおすすめも紹介しておきますね。
結論、無料で次のような支援をしてくれる就活エージェントの活用がおすすめです。
【就活エージェントのサービス内容】
- 就活相談
- 自分に合った求人の紹介
- 選考支援(ES添削や面接対策)
- 企業との面接のセッティング
- 面接後のフィードバック共有

面接対策に限らず、企業紹介や応募書類の添削まで幅広く対応してくれます。
そもそも就活生の内定獲得をサポートしてくれる存在なので、模擬面接や逆質問のブラッシュアップにも対応してくれるんですよね。
無料で使えるのは企業側が手数料を支払う仕組みがあるからなので、就活生にとっては至れり尽くせりですが怪しむ必要はないですよ!
▼就活エージェント利用者の声

僕はこれまで50以上の就活エージェントを見てきました。
そんな僕が今就活生なら、まずは「ミーツカンパニー就活サポート」と「
キャリアチケット」の2つに登録しますね。
(そのほかのおすすめエージェントは「就活エージェントおすすめランキング【1位〜21位】」にて紹介しています!)
上記は利用者の口コミが優れていて、サポートの質も高いと評判です。
オンライン支援対応で、全国の就活生が使える点も押しポイントですね。
ただし、就活エージェントの利用価値は担当者に依存しやすいので、最初から1つに限定しないで複数併用→相性のよい人を探すのがベストです。
理想は3社以上の登録ですが、少なくとも最初から2つには登録しておくべきですね。

エージェントでは専任の担当者がつく仕組みがあるため、枠が埋まってしまうとサポートを受けられない可能性があります。
よって機会損失を避けるために、後回しにせず早めに登録を済ませておくべきですよ。
なお、ここでは面接対策の質アップのために就活エージェントを紹介しましたが、そのほかにも僕が現役だったら使うサイトはいくつかあります。
結局どれを使うか?の5つだけをまとめた記事で共有しているので、興味を持ってくれた人はぜひさくっとチェックしてみてくださいね!
逆質問の具体例を知ることも大切だけど、本質的には模擬面接で場数を踏む・客観的な意見をもらうことが重要だよ。本気で就活を成功させたい人はぜひ実践してみてね!
逆質問の具体的な考え方【3ステップで解説】
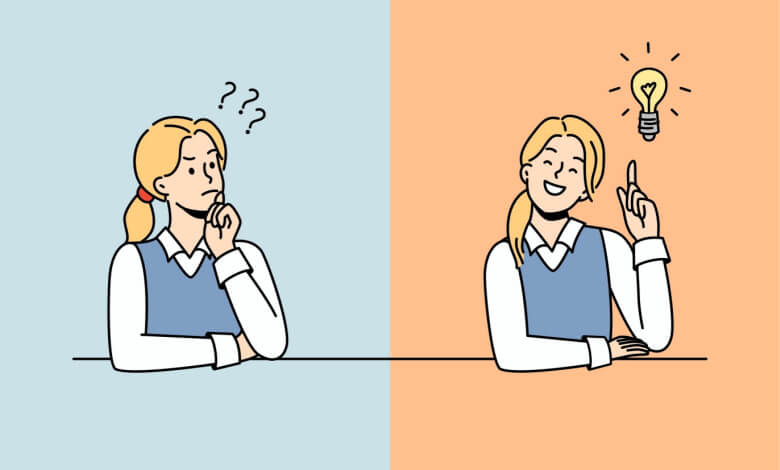
次にこの章では、逆質問の具体的な考え方を共有していきます。
具体例から抜粋するのも1つの方法ですが、自分が考えたアイデアを面接で質問したいという人もいると思いますからね。
ここでは、前提となる考えと僕がおすすめしたい3ステップをまとめたので、ぜひ順に見ていきましょう。
【逆質問の中身を考える際の3ステップ】
- 逆質問を通して実現したいゴールを考える
- ゴールから逆算しつつ疑問も踏まえて質問アイデアを考える
- 面接フェーズも踏まえて本番用の逆質問を2.3個に絞る
前提:「自分が一番知りたいこと=最適な逆質問」ではない
前提として、自分が知りたいことの質問が必ずしもベストではないと理解すべきです。
「自分が本当に一番知りたいこと」を聞くのもアリですが、すべての企業でそれが最適な質問になるとは限らないんですよね。
企業側は逆質問を求めることで、志望度や熱意・コミュニケーション能力の判断材料にするといった意図を持っているからです。
よって単に自分の疑問をそのままぶつければいいのではなく、目的意識や企業側の意図も考慮しておくべきなわけですね。
以下では、この前提を踏まえてステップをまとめたので続けて見ていきましょう。
ステップ① 逆質問を通して実現したいゴールを考える
逆質問を考える際は、その質問を通して実現したいゴールをまず決めましょう。
ゴールが明確だと、そこから逆算して的確な質問を考えやすくなります。
【逆質問を通して実現したいゴールの例】
- 入社意欲や志望度の高さを伝えたい
- 自分の人柄を気に入ってもらいたい
- 企業理解を深める質問をして入社の判断材料を増やしたい
- 企業との適性を測る質問をして相性を判断したい
- 自分の強みや性格を再度確認してもらいたい
複数のゴールを設定して、そのゴール別に質問を整理しておくのもアリですね。
また、面接フェーズごとに別のゴールを意識できると、逆質問をより効果的に使えますよ。
ステップ② ゴールから逆算しつつ疑問も踏まえて質問アイデアを考える
2つ目は、ゴールから逆算して質問アイデアを考えるステップです。
単純に自分が気になっている質問を候補にするのもいいですし、ゴールありきで質問例を考えてみるのもいいですね。
もしすぐにアイデアが浮かばない場合は、前述した僕の逆質問例を見ると視野が広がって新たな発想が生まれるかもしれません。
アイデアベースでOKなので、自由に発想して候補を書き出していきましょう。
ステップ③ 面接フェーズも踏まえて本番用の逆質問を2.3個に絞る
候補を書き出せたら、本番用の逆質問を2,3個に絞ります。
あまりに多く用意しても記憶が難しいですし、ほかの質問への回答にも支障があるので、〜3個ほどに整理しておくのがおすすめですね。
一次面接と最終面接では面接官の見方も変わりますし、フェーズごとに逆質問リストを整理しておけるとベストです。
企業間では流用できる逆質問もあるはずなので、その点も意識して整理してみてくださいね!
最初にゴールや目的を明確化しておくと、たしかに質問を考えやすくなりますね!
逆質問でマイナス評価を避けるための注意点

続いて本章では、逆質問でマイナス評価を避けるための注意点を紹介します。
高評価を得るための視点も大切ですが、反対に減点を防ぐための視点も持っておくとより好印象を残しやすいですよ。
細かい内容も多いので、より確実に対策したい人はぜひチェックしておきましょう。
【逆質問でマイナス評価を避けるための注意点】
- ネットで簡単に調べられることは質問しない
- 面接中に話題に上がったことは再度質問しない
- 1つではなく複数の質問を用意しておく
- 福利厚生や給料など待遇面に関する質問をしない
- 意図がよくわからない謎の質問をしない
- 相手の立場や役職も意識して質問する
- 絶対に何かしらの質問はする
注意点① ネットで簡単に調べられることは質問しない
大前提、ネットで調べられるような質問は避けましょう。
「企業研究していません」と言っているようなものですし、それでは企業に対する熱意は伝わりませんよね。
質問機会を無駄にするのももったいないですが、質問によってマイナス評価を受けてしまっては本当に最悪です。
逆質問を整理した後は、質問する価値があるかどうかを十分吟味しておきましょう。
注意点② 面接中に話題に上がったことは再度質問しない
面接に臨んでいると、事前に考えていた逆質問の回答にあたるような内容が話題にあがることもあると思います。
この場合は、別の逆質問に切り替えるようにしてください。
再度質問すると面接官は「話を聞いていなかったのか?」と思うはずですし、それでは確実に悪印象です。
意外とこういったケースは珍しくないので、もし本番で遭遇しても焦ることなく柔軟な対応を心がけてくださいね。
注意点③ 1つではなく複数の質問を用意しておく
逆質問は、必ず複数個を用意しておきましょう。
面接途中で話題に上がってしまうケースもあれば、時間に余裕があって複数の質問を求められるようなケースもあるからです。
個人的には、2,3個の用意は必須だと考えていますね。
柔軟な対応ができるように、いろんなジャンルの質問を用意しておくとより安心です。
注意点④ 福利厚生や給料など待遇面に関する質問をしない
応募側からすると、給料や福利厚生などの条件面は非常に重要な話だと思います。
でもこれらを逆質問で問うと、企業側は「条件面だけに惹かれて志望しているのでは?」などとネガティブな印象を持ちやすいんですよね。
条件面で志望する人は、もっと待遇がよい他社があるとすぐ退職しそうですし、本質的に熱意や志望度が高いとは思えないからです。
もしどうしても入社前に質問したかったら、内定獲得後にメールなどで確認するのが個人的には賢いと思っていますね!
注意点⑤ 意図がよくわからない謎の質問をしない
意図がわからない質問は、面接官を困らせてしまいます。
面接官は就活生の疑問を解消したいと思っているのに、何に答えたらよいかわからないときっと不安な気持ちになりますよね。
謎の質問をすることでコミュニケーション能力が乏しいと思われて、全体の評価にもマイナスの影響が生じてしまう恐れもあるかと。
目的意識を持って逆質問を考えることも大事ですが、質問される側にその意図が伝わるかどうかも意識しておきましょう。
注意点⑥ 相手の立場や役職も意識して質問する
逆質問する際は、面接官の立場や役職も意識しておいてください。
たとえば人事の方に対して、現場社員の仕事内容や求められる能力などを深掘りしても、専門ではないので答えにくいですよね。
そのほか、現場社員の方に対して会社全体の方向性や今後の戦略などを聞いても、いまいち現実味がなくて相手を困らせてしまうかと。
相手の立場を考えて話すことはコミュニケーションの基本なので、逆質問ではその相手にふさわしい内容か?も意識してみてください。
注意点⑦ 絶対に何かしらの質問はする
逆質問を求められたら、絶対に何かしらの質問はしましょう。
質問しないことはその企業に興味がないと言っているようなものですし、それでは志望度の高さや熱意が伝わりません。
企業側の立場を想像すると、前のめりに質問してくる応募者のほうが自社への本気度があってよい印象を受けるのは明白ですよね。
面接で逆質問の時間があれば、確実に何らかの質問はするようにしましょう。
何でも質問していいわけではなく、自分で調べられることや待遇面に関することなどは聞かないほうが無難なんですね。
面接官の視点に立つとよい印象を抱かないのはよくわかるはずだよ。数は多いけどどれも基本的な話ばかりだから、不要な減点を避けるためにもぜひ意識してみてね。
逆質問に力を入れて対策しておくメリット

次にこの章では、逆質問に力を入れて対策しておくメリットを紹介します。
改めてメリットを把握すると、対策にもモチベーション高く取り組めるかと。
以下3つのメリットについて、さくっと確認していきましょう。
【逆質問に力を入れて対策しておくメリット】
- 熱意の高さを伝えるチャンスが増える
- 疑問を解消することで企業理解を深められる
- ほかの就活生との差別化につながる
メリット① 熱意の高さを伝えるチャンスが増える
最大のメリットは、熱意の高さを伝えるチャンスを増やせることかと。
本来、志望度の高さを伝えられるのは志望動機などを語ったときだけですが、逆質問に力を入れることでその機会を増やせるんですよね。
企業側からすると、長期的にモチベーション高く働いてくれる人材は魅力的なので、選考時には確実に志望度の高さを確認するものです。
このメリットだけでも逆質問に力を入れる価値は大いにあるので、最後の質問だと軽視しないでぜひ対策しておきましょう。
メリット② 疑問を解消することで企業理解を深められる
逆質問は、単純に自らの疑問を解消する機会にもできます。
「ネットで調べられることは聞かない」などの注意点はありますが、その場でしか聞けない質問があれば企業理解を深めることにつながるかと。
応募側からしても企業との相性は適切に判断したいものですし、そのために気になる疑問があれば逆質問はそれを解消するいいチャンスです。
とくに質問する機会がなくて困っていた人は、ぜひ逆質問をうまく活用してみてくださいね。
メリット③ ほかの就活生との差別化につながる
逆質問に力を入れると、ほかの就活生との差別化につながります。
たとえば、志望度の高さを伝えるために逆質問に力を入れていれば、ほかの就活生よりも熱意を伝える機会は多くなるかと。
志望動機などの回答に加えて、逆質問の場もアピールの機会にできるからですね。
逆質問は超定番の質問ではないからこそ十分な対策をして臨む人も少ないので、差別化を図るためにもぜひ力を入れてみてください!
改めてメリットを知れるとたしかにモチベーションが上がりますね!
熱意の高さのアピール機会を増やせるだけでもメリットは大きすぎるし、ぜひ妥協することなく対策に取り組んでみてね!
逆質問に関してよくある質問

最後の章では、逆質問に関してよくある質問にまとめて回答します。
もし似た疑問を感じていた人がいたら、ぜひここでの回答を参考にしてみてください!
【逆質問に関してよくある質問】
- 面接で使える面白い逆質問といえば?
- 面接で聞いてはいけない逆質問はある?
- 逆質問を求められなかったときはどうすべき?
- 逆質問の数はいくつくらいがいい?
- 逆質問の内容を事前にメモしておくのはアリ?
- 逆質問の終わり方は?
質問① 面接で使える面白い逆質問といえば?
面白いの感じ方は人によって異なりますが、個人的には「面接での自分の印象を聞く逆質問」がおすすめですね。
これは、前述の逆質問ランキングでも1位として共有しました。
これは面接全体のフィードバックをもらうのではなく、「自分に対する面接官の認識は正しいかどうか」を確認するための質問です。
もし認識が合っていそうなら「まさにそのとおりです、短い時間の中で深く理解いただきありがとうございます!」などと伝えられるんですよね。
面接は企業側にも応募側にとっても、互いの適性を把握するための場です。
よって正しく認識されていないことは企業側にとっても損なので、この意図を持って質問すると逆質問をかなり有意義な時間にできるはずですよ!
質問② 面接で聞いてはいけない逆質問はある?
関心がないと捉えられたり、ネットで調べられたりする質問はNGですね。
条件面に関すること、ネガティブな印象を持たれやすい質問なども避けるべきかと。
【面接で聞いてはいけない逆質問の例】
- 特にありません(関心がなさそう)
- 土日休みでしょうか?(ネットで調べられる)
- 社員から評判の良い福利厚生はありますか?(条件面の質問)
- 退職理由で多い理由を教えてください(ネガティブな質問)
- 御社の繁忙期を教えてください(質問意図が謎)
質問③ 逆質問を求められなかったときはどうすべき?
求められなかったときは、無理に逆質問をする必要はありません。
面接時間が押したことで、逆質問の時間がなかっただけの可能性が高いからです。
よって「逆質問がなかった=低評価だったから質問機会をもらえなかった」などと悲観的に捉える必要はありません。
意外とよくある話なので、1つのケースとして知っておくと安心ですね!
質問④ 逆質問の数はいくつくらいがいい?
正解はないが前提ですが、個人的には1〜2個がベストだと考えています。
ゼロは関心がないと思われるので論外ですが、数が多すぎても面接時間が長くなりすぎて企業側に迷惑をかける恐れがあるんですよね。
また、単純に数が多いほど熱意があるという話でもなく、質の低い逆質問をするとかえって減点対象になってしまうリスクもあるかと。
もし数で迷ったら事前に3個ほど用意しておき、本番では1〜2個質問することを僕はおすすめしますね。
質問⑤ 逆質問の内容を事前にメモしておくのはアリ?
事前にメモしておくのもアリですよ。
事前準備していることは企業への本気度が高い証拠ですし、もし質問を忘れてしまったら許可を取った上でメモを見るのもアリかと。
一生懸命さが伝われば、年上の面接官もきっと前向きな印象を持ってくれますよ!
質問⑥ 逆質問の終わり方は?
僕はいつも「ご回答いただきありがとうございます!こちらからの質問は以上です」と答えて終わることをおすすめしていますね。
難しいことを考える必要はなくて、シンプルに終えればOKですよ!
面接後の印象を聞いて、認識を正しく共有できているか確認するのは面白いですね!
意図を持っていれば面接官にも受け入れてもらえるし、ほかの就活生にはなかなかない発想だから差別化にもつながるはずだよ!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
逆質問の概要や企業側の質問意図、おすすめの質問例一覧やマイナス評価を避けるための注意点などを網羅的に共有しました。
逆質問を求める企業は、志望度や熱意の高さを確認する意図を持っています。
よって単に質問機会をもらえているだけと考えず、事前に目的を整理した上で質問リストを準備しておくべきですよ。
自己PRや志望動機などと比べると逆質問に力を入れる人は少ないですし、だからこそ本気で対策すれば差別化にもなります。
コツを押さえれば対策難易度も決して高くないので、ぜひこの記事を参考に対策して逆質問をアピール機会に変えてくださいね!
ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「【一次面接でおすすめの逆質問13選】質問の意図からNG質問例まで徹底解説!」も読んでみてください。
一次面接に特化して、おすすめの逆質問を具体的に13個紹介しています。
一次面接向きの逆質問の特徴やNG例なども共有しているので、一次面接に向けて逆質問の対策をしていた人はぜひ一読してみてくださいね。
それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!
【本記事の要点】
- 逆質問とは、面接最後に聞かれる「何か質問はありませんか?」という質問のこと。
- 企業側は、志望度の高さやコミュニケーション能力の判断材料にする意図を持っている。
- 逆質問を含めた面接対策を万全にしたいなら、就活エージェントなどで模擬面接を受けて第三者から客観的な意見をもらうべきである。
- 「自分が一番知りたいこと=最適な逆質問とは限らない」と認識しておくとよい。
- ネットで調べられること、待遇面に関することなどを逆質問するのは避けるべきである。









