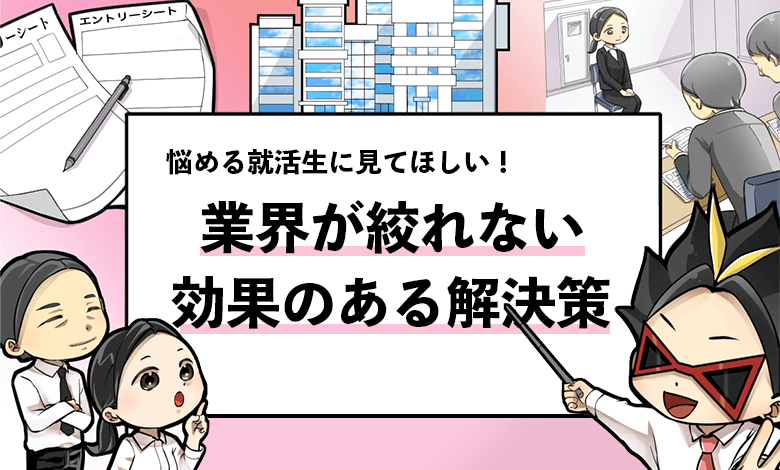
こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。
これから就活を始める学生の中には「業界が絞れない…」「どうやって絞っていけばいいのかわからない」という人も多いかと思います。
ほとんどの就活生が業界を絞れない理由は簡単です。
それは「業界の絞り方・決め方を知らないから」という単純な理由。
要するに情報がないだけなのです。
しかし、業界が絞れていないと最終的な企業選びも難しくなってしまいます。
そこで本記事では、「業界の絞り方」をご紹介していきます!
業界が絞れないと悩んでいる就活生がとるべき行動もお伝えしていくので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
そもそもどうやって業界を絞ればいいのかわからないです…。
「業界」について今まで学んだことがなかったからこそ、なかなか絞れない人が多いけど簡単だから安心してね!
- 業界はある程度絞った方がいい
- 就活での業界の絞り方【業界が絞れない人必見!】
- 業界を絞るときの注意点
- 業界を絞れない就活生が取るべき4つのアクション
- 「業界」ではなく「職種」で絞るのもアリ
- 業界を絞らないメリット・デメリット
- 就活で業界を絞れないときによくある質問
- 本記事の要点まとめ
\就活攻略論から求人サイトが生まれました!/
(僕が就活生の時に感じていた「働きやすい条件の良い企業だけを丁寧に紹介してくれるサイトはないのかな」を形にした求人サイトです!)


業界はある程度絞った方がいい

「そもそも業界を絞るべきなのか」と考える就活生もいるかと思います。
結論からいうと、ある程度は業界を絞った方がいいです。
日本だけでもおよそ400万もの企業が存在しています。
その中から、エントリーする企業を決めるためにもさまざまな基準を自分なりに設ける必要があるのです。
そこで一つの基準となるのが「業界」というわけですね。
業界をある程度絞って就活を行うことで、エントリーする企業を決めやすくなります。
5業界くらいに絞るのがベスト
目安としては5業界ほどに絞るのがベストです。
実際に僕も就活生時代は、5つの業界を志望していました。
理由は以下の2点。
【5つの業界に絞る理由】
- 1つ1つの業界研究をしっかりできるから
- 中小企業までチェックできるから
志望する業界が多すぎると、一つひとつの業界への理解が薄くなってしまいます。
業界理解が甘いままだと志望動機も薄くなってしまうんですよね。
また、多くの業界を志望していると、やはりその業界でも知名度の高い大企業ばかりが目についてしまいます。
悪いことではありませんが、大企業の選考ばかり受けると内定がなかなか取れずに余裕がなくなってしまうでしょう。
そのため、一つひとつの業界をしっかり研究でき、中小企業まで目を向けられる5業界程度に絞るのがおすすめというわけです。
いつまでに絞らなければいけないという基準はない
業界を絞れない就活生は、「いつまでに絞ればいいのかな」と不安に思っている人もいるでしょう。
しかし、業界をいつまでに絞らなければいけないという基準はありません。
むしろ早く絞りすぎると、自分に合う他の業界を見逃してしまう可能性もあります。
業界を絞る前にまず「どんな業界があるのか、どのような業界なのか」といった業界研究をしっかり行った上で、志望業界を決めていきましょう。
業界研究の具体的なやり方については、以下の記事で解説していますのでぜひ読んでみてくださいね。
【補足】知っておくべき8つの業界分類
補足として、就活生が知っておくべき業界分類をご紹介しておきます。
まずは世の中にどんな業界があるのかを把握しないと、選択肢が限られますからね。
業界は「役割」ごとに大きく以下の8つに分類されます。
【業界の役割ごとの8分類】
- メーカー
└モノをつくる役割 - 商社
└モノを動かす役割 - 小売
└モノを売る役割 - サービス
└かたちのないモノを売る役割 - 金融
└お金を動かす役割 - マスコミ
└情報を大衆に伝達する役割 - ソフトウェア・通信
└情報に付加価値をつけて売る役割 - 官公庁・公社・団体
└国や地方団体の基本的な活動を進める役割
上記の8つの大きな分類のなかで、さらに扱う商品やサービスでより細かく業界が分けられます。
例えば、メーカーであれば「自動車業界」「食品業界」「化粧品業界」などに分けられるということです。
各業界については以下の記事で詳しく解説しているので、まずは大きく分けた業界分類について知りたいという人は読んでみてください。
5業界くらいに絞るのが目安なんですね!
業界が絞れないと悩んでいる就活生は、かなり少なく絞ろうとする人も多いけど、ある程度絞れればOKだよ!
就活での業界の絞り方【業界が絞れない人必見!】

業界が絞れない就活生の多くが「業界の絞り方がわからない」のではないでしょうか?
そこで、業界が絞れない人向けに僕が考えた6ステップを共有していきますね!
業界が絞れないと悩んでいる人は、以下のステップで少しずつ絞っていってみてください。

上記のステップで、僕も業界を絞っていきました。
まずは業界知識を深めた上で、上記の6ステップで絞っていきましょう。
ステップごとの詳しい解説は以下の記事でまとめています。
他のサイトよりも、かなり細かく具体的に手順を解説していますよ。
絞るときのポイントについても紹介しているので、業界が絞れずに悩んでいる就活生は必ず読んでくださいね!
内定獲得には自分に合う企業探しが重要!
ここまで業界の絞り方についてお伝えしましたが、内定を獲得するには「自分に合う企業」を見つけられるかが重要です。
業界が決まっても、なかなか自分に合いそうな企業を見つけられず苦戦する就活生は多い。
そこで、業界を絞る段階から逆求人サイトや就活エージェントに登録しておくことがおすすめです。
逆求人サイトはプロフィールを登録しておくと、企業からスカウトが届く仕組みのサイト。
就活エージェントは、面談を通してあなたに合う求人を紹介してくれるサービスです。
逆求人サイトや就活エージェントを利用することで、いままで視野に入れていなかった業界や企業を知れるきっかけになります。
また、あなたの特性を把握した上でスカウトや紹介をうけるので、適性が高い企業と出会いやすい。
僕はこれまで200以上の就活サイトを見てきましたが、中でも「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「
」と「ミーツカンパニー就活サポート」はとくにおすすめですね。
内定をはやく獲得したい人は、今のうちから上記2サイトには登録しておきましょう!
ちなみになんですけど、今まで頂いた内定すべてOfferBox経由です🎁
— おねむちゃん (@onemuchan22) April 4, 2021
まさかこんなにオファボに世話になるとは思ってなかった 😂
散々死ぬほどエントリーしてるのにオファボ居なかったら死んでるワ
ちなみに、以下の記事で「僕がいま就活生だったらこれだけは使う!」と思うサイトを6つ紹介しています。
あなたに合う企業からの内定獲得に役立つはずなので、一度チェックしてみてくださいね。
この6ステップを参考にすれば、業界も絞っていけそうですね!
うん!別記事でステップ一つひとつを詳しく解説しているから、合わせて読んでみてね!
業界を絞るときの注意点

ここで業界を絞るときの注意点をお伝えしていきます。
業界の絞り方を間違えてしまうと、就活中だけでなく就職後もつらい思いをしてしまうかもしれません。
以下の注意点をきちんと意識して業界を絞っていきましょう。
【業界を絞るときの注意点】
- はじめから絞りすぎない
- イメージで絞らない
- 業界を1つに絞らない
注意点① はじめから絞りすぎない
はじめから業界を絞りすぎるのはNGです。
業界知識がまだ浅い段階で絞りすぎてしまうと、その業界の悪い部分が見えづらくなってしまいます。
焦って絞って受けた業界が自分にまったく合わないと、就職した後にずっとつらい思いをして働き続けることになってしまいます。
業界研究や自己分析をしっかり行った上で業界を絞っていくようにしましょう。
注意点② イメージで絞らない
イメージで絞らないというのも大事なポイントです。
詳しくは知らなくても業界に対するイメージを持っている人は多いかと思います。
しかし、世間のイメージと実際の働き方が全く違うことも少なくありません。
イメージで業界を絞ると入社後のミスマッチにつながってしまう可能性があります。
就活エージェントから詳しい内情を教えてもらったり、セミナーやOB訪問で社員に話を聞くなどしてリアルな情報を集めるようにしてくださいね。
注意点③ 業界を1つに絞らない
業界を絞った方がいいとはいえ、1つの業界に絞るのは危険です。
「自分にはこの業界が合っている!」と思い込んで同じ業界ばかり受けていても、実際に入社すると相性が悪かったなんてこともあり得ます。
また、1つの業界の企業ばかり受けていてすべて落ちてしまった場合は、また新たに業界を絞るところから始めなければいけません。
そうならないためにも、業界は5つ程度に絞って就活を進めましょう。
なんとなく持っているイメージで決めてはだめですね。
イメージのまま最初から業界を絞ってしまうのはもったいない。調べていくと「おもしろそう!」と興味を持つこともあるからね。
業界を絞れない就活生が取るべき4つのアクション

業界の絞り方のステップをお伝えしましたが、絞るためにはまず業界を知る必要があります。
自分に適性がある業界を見つけるためにも、さまざまな業界の情報と自分について知ることが重要。
業界を絞れないと悩んでいる人は、以下の4つに取り組んでみてください。
【業界を絞れない就活生が取るべきアクション】
- 業界研究ノートを作成する
- 業界研究セミナーに参加する
- 自己分析で自分のタイプを把握する
- 就活エージェントを活用する
行動① 業界研究ノートを作成する
まずは「業界研究ノート」を作成しましょう。
業界研究ノートとは、業界研究で得た情報をまとめるノートのことです。
さまざまな業界を比較できるので、情報を整理しつつ自分に合った業界を見つけやすくなります。
また、ノートにまとめた情報をもとに自己PRや志望動機の質を高めることもできます。
就活生は必ず作成しておきましょう。
業界研究ノートの書き方については、以下の記事で解説しているのでぜひ参考にして作ってみてくださいね。
行動② 業界研究セミナーに参加する
次に、業界研究セミナーに参加しましょう。
インターネットで調べられる業界の情報は限りがあります。
そこで業界研究セミナーに参加し、リアルな業界の情報を収集しましょう。
より具体的な業界知識が得られるだけでなく、一度で多くの企業の話が聞けるというメリットもあります。
以下の記事でおすすめの業界研究セミナーも紹介しているので、チェックしておいてくださいね!
行動③ 自己分析で自分のタイプを把握する
さまざまな業界についての知識が得られたところで、次に「自己分析」を行いましょう。
自己分析ができていないと、業界の知識はあっても自分がどの業界に向いているのか判断できません。
徹底的に自己分析を行い、自分の長所や短所、そして企業選びの軸を把握しましょう。
自己分析は就活において、あらゆる作業の土台となります。
自己分析と業界研究で得た情報を照らし合わせて、適性のある業界を見つけてみてくださいね。
なお、自己分析のやり方は別の記事でかなり詳しく解説しています。
どの就活サイトよりも具体的にわかりやすくまとめているので、「自己分析って何から始めればいいのかわからない」という就活生はぜひ参考にしてください!
行動④ 就活エージェントを活用する
自分で業界研究や自己分析を行った後は「就活エージェント」を利用するのがおすすめです!
就活エージェントとは、面談をもとに自分に合った求人を紹介してくれる無料サービスのこと。

就活エージェントは、就活のプロなのでさまざまな業界の知識があります。
面談の結果をもとに客観的にあなたに合った業界について教えてもらえるでしょう。
また、業界選びのサポートだけでなく、ESや面接対策なども行ってもらえます。
自分だけではどうしても業界を絞れないという人は、就活エージェントを利用してみてくださいね。
ちなみに僕はこれまで50以上の就活エージェントを利用してきましたが、いま就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」と「
キャリアチケット」を併用しますね。
どちらもオンライン面談に対応しているので全国の学生が利用できますし、特別選考ルートや非公開求人を持っています。
業界選定から内定獲得までしっかりサポートしてもらえるので、ぜひ利用してみてくださいね。
なお、他におすすめの就活エージェントについては以下の記事でまとめています。
他のエージェントと比較して検討したい人はこちらもチェックしてみてください。
確かに自分で調べるのも大事ですけど、就活のプロから情報をもらえるのはありがたいですね!
ネットだけじゃ業界の動向も調べきれないからね。就活エージェントだと客観的に向いている業界を教えてもらえるし、そのまま選考もサポートしてもらえるから使わないと損だよ!
「業界」ではなく「職種」で絞るのもアリ

ここまでで業界の絞り方についてお伝えしていきましたが、「業界」ではなく「職種」で絞るのもアリです。
業界を絞るのは、エントリーする企業を選ぶための基準として重要。
しかし、あくまでも基準の一つなので、それ以外の部分を基準に企業を絞れるのであればOKなんです。
業界で絞れないと悩んでいる人も、職種で考えてみると絞れることもあります。
職種とは、仕事内容のことですね。
自分が興味のない業界であっても、仕事内容が自分に合っていれば楽しく働くことができます。
業界を絞れない就活生は、やりたい職種から絞っていくのもひとつの方法です。
一般的な職種には以下のようなものがあります。
【職種一覧】
- 総務職
- 経理職
- 研究開発職
- 購買職
- 技術職
- 生産技術職
- 営業職
- 販売職
- 広報職
- 企画職
- 経営企画職
- エンジニア職
上記のように、世の中にはさまざまな職種があるので、業界が絞れずに悩んでいる人は「向いている職種はなんだろう?」と考えてみてください。
各職種については以下の記事で紹介しているので、職種選びの参考に読んでみてください。
業界だけでなく職種も絞り込むことで、企業へのエントリーへと進んでいこう!
業界を絞らないメリット・デメリット

職種でエントリーする企業を絞れるのであれば、業界を無理に絞る必要はありません。
ここでは業界を絞らないで就活するメリット・デメリットをご紹介しますね!
業界を絞らないメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 業界を絞らないメリット | 業界を絞らないデメリット |
|---|---|
| ・出会える企業数が多い ・さまざまな業界を比較できる ・エントリーできる企業数が格段に増える |
・業界理解が甘く志望動機が薄くなる ・企業探しが難しくなる ・優先順位を付けづらくなる |
業界を絞らずに就活を進める上でもっとも注意すべきなのが、業界理解が甘くなってしまうことです。
絞らないで複数の業界の企業にエントリーする場合は、その分さまざまな業界研究を行う必要があります。
そうすると、一つひとつの業界への理解が薄くなるので志望動機が浅いものになってしまうでしょう。
面接で業界について質問された場合もうまく答えられない可能性もあります。
よって、5つ程度には業界を絞って就活を進めるのがベストですよ。
絞らないメリットもあるんですね!
そうだよ。ただ自分なりの企業選びの軸が定まっていないと、いつまでもエントリーする企業を決められなくなる。まずは業界研究や自己分析をしっかり行った上で業界を絞るか決めてみてね。
就活で業界を絞れないときによくある質問

最後に、業界を絞れない就活生からよくある質問に回答していきますね。
業界をなかなか絞れず悩んでいる人はぜひ参考にしてください!
【業界を絞れないときによくある質問】
- 就活で志望する業界はバラバラでもいいですか?
質問① 就活で志望する業界はバラバラでもいいですか?
結論からいうと、志望業界はバラバラでも問題ありません!
ただ、バラバラの業界を志望するとしても、その理由はしっかり答えられるようにしておくことが大事です。
たとえば、面接で他に受けてる企業などを聞かれたときに別の業界の企業を答えると「なぜ◯◯業界を志望しているんですか?」と質問されるでしょう。
このときに志望理由を答えられないと、企業を選ぶ軸がなく志望度が低いと思われてしまいます。
よって、業界はバラバラでもこの記事でお伝えしたとおり「5業界」程度に絞って1つ1つの業界をていねいに研究しておくことが大事です。
業界をバラバラに選択するときの注意点やメリット・デメリットについて、以下の記事でくわしくまとめたので読んでみてください!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
自分に合った企業にエントリーするためにも、ある程度は業界を絞るのがおすすめです。
業界をなかなか絞れない就活生は今回ご紹介した行動に取り組んでみてください。
一つひとつ行っていくことで、必ず業界を絞れるようになります。
また、業界で絞れない人は企業選びの軸として、職種を基準にするのもひとつの方法です。
自分なりの「企業選びの軸」をしっかりと持ち、あなたに合った企業を見つけてくださいね。
ちなみに、この記事を読み終わったら「【ホワイト業界12選】僕がおすすめするホワイト業界を紹介!」も読んでみてください。
ホワイト企業が多い業界を紹介しています。
ホワイト業界に入社するメリット・デメリットや探す方法もまとめているので、業界選びの参考にしたい就活生はぜひ目を通してみてくださいね。
では最後に本記事の要点をまとめて終わりましょうか。
【本記事の要点まとめ】
- 業界は5つ程度に絞るのがベスト。
- まずは業界知識を得た上で絞っていくのがおすすめ。
- 業界を絞れない就活生は「業界研究ノートの作成」「業界研究セミナーに参加」「徹底的な自己分析」「就活エージェントの活用」の4つを行うべきである。
- 業界で絞れなくても「職種」で選ぶのも一つの基準。







