
【2025年9月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。
(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!
今回は税金の支払い確認や徴収などをおこなう国税専門官について調査していきます。
年収の水準も高いので、一部からはおすすめだとされる一方で、滞納者とのやり取りはとにかくストレスが半端じゃないという否定的な声まで見られます。
そこでこの記事では「国税専門官はやめとけ」と言われる理由を中心に、国税専門官に就職するメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
国税専門官について、少しでも興味がある方は、情報収集のためにぜひ読み込んでもらえると嬉しいです!
国税専門官は気になっていました!やめとけと言われる理由が知りたいです。
国税専門官が向いているかどうかは本当に人によって異なる。自分が向いているかどうか考え抜くことが重要だよ!
- 国税専門官とは?
- 【結論】国税専門官になるのはやめとくべきか?
- 国税専門官はやめとけと言われる理由【4選】
- 国税専門官として就職するメリット【3選】
- 国税専門官に向いている人の特徴【4選】
- 「国税専門官 やめとけ」と調べる人からよくある質問
- 本記事の要点まとめ
国税専門官とは?

まずは国税専門官とは何か、簡単に解説していきます。
国税庁の公式サイトから引用すると、国税専門官とは以下のとおりです。
要するに、個人や会社の納税が行われているか調査したり、滞納者に対して督促をおこなったり、悪質な脱税者に対して捜査・差押等の強制調査をおこなう職種です。
国税専門官は、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使し、国税調査官、国税徴収官、国税査察官といった職種に分かれて活躍しています。
国税調査官
納税義務者である個人や会社等を訪れて、適正な申告が行われているかどうかの調査・検査を行うとともに、申告に関する指導などを行います。
国税徴収官
定められた納期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うとともに、納税に関する指導などを行います。
国税査察官
裁判官から許可状を得て、悪質な脱税者に対して捜査・差押等の強制調査を行い、刑事罰を求めるため検察官に告発します。
引用:国税庁|業務内容
国税専門官は、税金をしっかりと徴収して国を回すための重要な仕事ですね!
そうなんだよ。そんな国税専門官はやめとけと一部から言われる理由について、次の章から詳しく見ていこう!
【結論】国税専門官になるのはやめとくべきか?

もったいぶらないで結論をお伝えしていきますね。
国税専門官への就職はやめておくべきか?という問いへの結論は、以下のとおりです。
【国税専門官への就職に対する僕の結論】
結論、税法などに専門性を持って働きたい人にはおすすめと言える。
年収水準も高く、勤続23年で税理士資格を得られるなどのメリットも魅力的。
業務内容との相性を考えたときには、分析力や言語化能力が優れている人、誠実性が高く忍耐力に自信がある人には適性がある可能性が高い。
一方、納税者とのやり取りがストレスの要因になる、専門知識を身につける必要があるなどのデメリットも存在する。
よって、これらの観点を総合的に踏まえて相性を判断することが大切である。
個人的には、国税専門官はストレス耐性が高い人は向いていると思いますが、僕は税金の滞納者とのやり取りは大きなストレスを感じるので絶対に向いていないと思います。
(その場合は、「国税調査官」を選択するという手もあるので一概には言えないですが)
一方で、平均年収は高めなのは魅力。
経験を積むほど専門性が高まる点も魅力的ですね。
ただし、「国税専門官はやめとけ」といった声が一定見られるように、懸念点となるような部分もいくつか存在します。
そのため、よい面・悪い面の両方を把握した上で適性を判断することが重要です!
これは他の業界・職種への応募を検討する場合においても同様です。
最終的には「一般的な意見がどうか?」ではなく「自分との相性はどうか?」が肝になるので、あくまでも自分の適性をじっくり考えてみてくださいね!
懸念点もあるものの、年収水準が高めであることや働き続けると税理士資格を得られる可能性があることはやはり魅力的ですね。
次章からは国税専門官の懸念点やメリットを個別に解説していくから、より理解を深めた上で相性を判断するためにもぜひ続けてチェックしてみてね!
国税専門官はやめとけと言われる理由【4選】
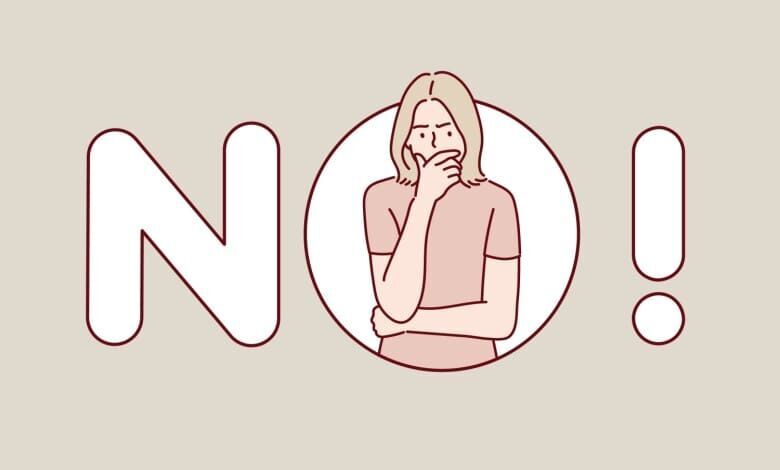
次にこの章では、国税専門官はやめとけと言われる理由を紹介します。
デメリットとも言い換えられる内容であり、これらの懸念点を把握しないで就職を決めるとミスマッチや早期離職につながりかねません。
後悔しないキャリア選択をするためにも、ぜひ事前に確認しておきましょう。
【国税専門官はやめとけと言われる理由】
- 納税者とのやり取りがストレスになりやすいから
- 正確性を求められる仕事にプレッシャーを感じるから
- 税法の専門知識を身につけることが負担になるから
- 年功序列により若手時代は給料が高くないから
理由① 納税者とのやり取りがストレスになりやすいから
否定的な意見としてよく言われるのは、業務上ストレスを感じやすいことです。
国税専門官は立場上、期限までに納付されない税金を回収するために滞納者と直接接する機会があります。
こうした機会には、滞納者からネガティブな声を浴びせられることがあるんですよね。
滞納者からすると国税専門官はお金を回収する立場の人間なので、滞納者にとってうれしいことというよりは嫌なことをする対象として見られます。
ゆえに、自然と嫌われ役のような立場になりがちなんですよね。
滞納者からすると、自分に余裕のない状況下で税金の支払いを迫ってくる相手なので、暴言や嫌味などを言いたくなるものかもしれません。
就職前はとくに問題ないと想像していたものの、実際にそうした場面に何度も出くわすなかでストレスが蓄積する人は少なくありません。
国税専門官としての就職を考えている人は、基礎知識として把握しておきましょう。
理由② 正確性を求められる仕事にプレッシャーを感じるから
国税専門官の仕事は、ミスが許されないような重要度の高い業務です。
税金について適切な申告がおこなわれたかを確認したり、期限までに納付されない税金の督促をしたりと、専門性が求められる立場なんですよね。
当然ですが、こうした業務を担う職員には正確性が求められます。
仮に間違いを見過ごしたりミスをしたりすると、重要な問題に発展するなどトラブルにつながる可能性も考えられるんですよね。
どんな仕事でもミスは0にすることが理想ですが、国税専門官の場合はミスをなくすことへのプレッシャーがどうしても大きくなりがちです。
業務や立場の特性上、プレッシャーを感じる可能性があることは知っておきましょう。
理由③ 税法の専門知識を身につけることが負担になるから
国税専門官の業務を遂行するには、税法に関する専門知識が必要になります。
正確性を求められる重要な仕事というだけでなく、これらをミスなく実行するには前提として専門知識を頭に入れておく必要があるんですよね。
税法にまつわることを教えたり、誤りがあったときに指摘したりする立場なので、税法などに精通していることは業務上の基盤となるわけです。
ただ、こうした知識は専門性が高く簡単に習得できるものではありません。
就職してから最初の数年だけ頑張ればよいわけでもなく、長期間に渡って継続的に学習することも求められるんですよね。
よって、知識の習得や継続的な学習に負担を感じやすい人は挫折しやすいかと。
税法に関するそもそもの興味関心も、学習のモチベーションに影響しやすいですね。
国税専門官として活躍するには長い期間学び続けることが重要になるので、相性を判断する際には参考材料として把握しておくとよいでしょう。
理由④ 年功序列により若手時代は給料が高くないから
国税専門官は、税務のスペシャリストとして国税庁などに勤務する国家公務員です。
大枠は公務員という立場なので、国税専門官も年功序列の環境なんですよね。
ゆえに、年齢や勤続年数を重ねると待遇面は右肩上がりに向上していきます。
しかし、勤続年数が短い若手社員のころは、国家公務員にも関わらず給与面などで不満を感じる人も一定いるんですよね。
これは国税専門官に限らず、年功序列を採用する他の企業でも同様のことが言えます。
年功序列制度は崩壊したと言われているものの、昔の名残で上記のような文化が残っている会社はまだまだ多いんですよね。
よって国税専門官だけのデメリットではないですが、上記を把握しないで就職を決めるとギャップに感じる要素になり得るかもしれません。
国家公務員でも最初から高給ではないので、注意点としてぜひ知っておきましょう。
税金を回収する立場を担うことから、滞納者などを直接相手にしているなかではストレスを感じることも多くあるんですね。
重要度が高い仕事ゆえにプレッシャーを感じる人もいるね。専門知識の習得も確実に求められるから、学習面での自分との相性もじっくり考えておくといいよ。
国税専門官として就職するメリット【3選】

続いてこの章では、国税専門官として就職するメリットを共有します。
国税専門官に限らず、自分の志望業界や職種を検討する際には、それらのメリット・デメリットの両方を確認しておくことが重要なんですよね。
その上でメリットのほうが大きいと感じるなら、相性はよい可能性が高いかと。
万人にとって完璧な就職先はないからこそ、網羅的に情報を集めた上で自分はどう感じるか?をぜひじっくり考えてみましょう!
【国税専門官として就職するメリット】
- 平均年収が高い
- 勤続23年で税理士資格が得られる
- 勤続年数に応じて専門性が高まる
メリット① 平均年収が高い
国税専門官のメリットとして、平均年収が高いことは押さえておくとよいかと。
人事院が公表している「令和5年度国家公務員給与等実態調査」によると、国税専門官の平均年収は約706万円でした。
比較材料として、国税庁が公表している「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与は458万円となっています。
よって、日本全体の平均と比べると国税専門官はかなり高給とわかりますね。
「国税専門官はやめとけ」といった意見のなかには、年功序列制度によって若手時代に待遇面が微妙なことを指摘している人がいました。
ただ、全体で見ると国税専門官の待遇はかなり手厚いと言えそうですね。
メリット② 勤続23年で税理士資格が得られる
国税専門官は、勤続年数が長くなると税理士試験を免除できる制度があります。
具体的には、10年以上の勤務で税法3科目、23年以上勤務すると全試験科目の免除を申請できるルールとなっているんですよね。
つまり、勤続23年以上になると税理士資格を得られるわけです。
そもそも国税専門官として23年働き続けることも簡単ではないと思いますが、それでも税理士資格の難易度を考えると十分メリットといえる内容かと。
ただ補足もしておくと、国税専門官の口コミを見る限り、実際にこの制度を利用して税理士になる選択を取る人は少ないようです。
税理士として独立後、ゼロから開業して生計を立てることにはハードルがあるようですね。
税理士資格が得られることだけを理由に国税専門官を志望する人は少ないかもしれません。
とはいえ、志望する上で間違いなくプラス要素にはなると思うので、応募や就職を考えている人は確実に把握しておくとよいでしょう。
メリット③ 勤続年数に応じて専門性が高まる
国税専門官として就職すると、スペシャリストとして専門性を高めていけます。
比較材料として、たとえば地方公務員へ就職した場合を想定すると、3年前後の周期で異動となることが通常なんですよね。
その点、同じ職種として働き続けられる国税専門官は知見を深めていけるわけです。
また、国家公務員かつ税法の知見が必要となる職種だからこそ、就職先自体の学習・研修環境もかなり整っているんですよね。
受け入れ側としても職員には専門性を高めてもらいたいと思っているはずなので、学習環境の整備には力を入れていると予想できます。
こうした環境で長く働き続けていたら、税務の専門性は嫌でも高まっていくかと。
税法に関する知見が深ければ、選択肢としては民間企業への転職も十分可能です。
ジェネラリストにも良さはありますが、スペシャリストとして専門分野を持てることは国税専門官として就職するメリットになるでしょう。
高年収のイメージはありましたが、給与所得者の全体平均と比べるとその水準の高さがよくわかりますね!
長く働き続けると試験免除を申請できる制度があること、同じ職種として専門性を高めていけることも魅力的な要素と言えるよ!
国税専門官に向いている人の特徴【4選】

次にこの章では、国税専門官に向いている人の特徴を紹介します。
ここまでの内容を踏まえて、僕なりに適性があると考える人の特徴をまとめました。
複数の項目に当てはまる人ほど相性はよい可能性が高いと思うので、とくに国税専門官への就職を迷っている人はぜひ参考にしてみてください!
【国税専門官に向いている人の特徴】
- 分析力がある
- 倫理観があり誠実性が高い
- 精神力や忍耐力に自信がある
- 言語化力やコミュニケーション力がある
特徴① 分析力がある
国税専門官として業務をおこなう上では、分析力が重要になります。
税務調査を進める際には、申告書や決算書の内容を見て問題点を見出す必要があり、的確な判断をするためには分析力が必要になるんですよね。
最悪の場合、分析を誤るとミスやトラブルにも発展する可能性があります。
こうした事態を避ける上ではもちろんのこと、より質の高い調査をする上でも高い分析力を持っていると成果につながりやすいわけですね。
的確な分析をするためには、税法などに関する知見がそもそもの基盤となります。
こうした知見をもとに申告書などを見て的確な判断を下すことが求められるので、実際の業務内容も想定してぜひ自分の適性を考えてみてください。
特徴② 倫理観があり誠実性が高い
国税専門官には、倫理観や誠実性も求められます。
税金が正しく納められているかを確認すること、正確に徴収することが役割なので、その立場を担う職員自体の信頼性も重要になるんですよね。
たとえば国税専門官が脱税をしていたら、その人は確実に信頼できなくなります。
そして脱税をした本人だけに限らず、脱税をするような人が在籍していた国税専門官全体に対しても、信頼低下につながってしまう恐れがあるかと。
これは極端な例ですが、このような不信感を抱かれることをなくすためにも、常に誠実さを忘れず公正な振る舞いが求められるわけですね。
倫理観などは意識をすればある程度改善できる部分ではあると思います。
とはいえ、もともとの感覚や考え方が基盤とはなるので、自身の性格面などを踏まえて相性を考えておくことは大切ですね。
特徴③ 精神力や忍耐力に自信がある
国税専門官として業務をしていると、罵声などを浴びせられることがあります。
滞納者からするとお金を徴収する側の人間なので、ネガティブな言葉をかけられる機会も少なくないんですよね。
メンタルが弱いと、こうした業務が大きなストレスの要因になりやすいです。
ゆえに、相手から圧力を受けた場面やプレッシャーを感じる場面であっても、心を強く保てるような精神力は重要になりますね。
細かい書類の確認や修正などの作業も多いので、緻密かつ正確性を求められる業務を根気強くこなせるような忍耐力も求められます。
簡単な職種ではないからこそ、精神力や忍耐力については相性を考えておきましょう。
特徴④ 言語化力やコミュニケーション力がある
国税専門官には、言語化力やコミュニケーション能力も欠かせません。
納税者とやり取りをする際には税法に関する専門知識を説明し、その上で間違いがあった点などを理解してもらう必要があります。
専門的な説明は難しくなりがちだからこそ、そうした知見を持った上で相手に伝わるようなわかりやすい言語化が求められるわけですね。
また、説明相手のなかには意図的に脱税などをしている人もいる可能性があります。
こうした相手は威圧的な態度を取るケースもありますが、国税専門官は冷静さを保ち、相手の理解を得られるように対話を進めないといけません。
つまり、関わる相手によって柔軟に会話を展開することが必須なんですよね。
専門的な知見が必要なだけでなく会話力もかなり重要な職種なので、国税専門官を志望する人は必要スキルとして事前に把握しておきましょう。
税法に関する専門知識が必要とは思っていましたが、それ以外にも分析力や誠実性などの強み・資質を知っておくとよさそうですね。
コミュニケーション能力も確実に必要だから、軽視することなく自分が円滑に業務をこなせそうかはイメージしておくといいよ。
「国税専門官 やめとけ」と調べる人からよくある質問

最後に本章では、「国税専門官 やめとけ」と調べる人からよくある質問に回答します。
似た疑問を感じていた人は、ぜひここでの回答を参考にしてみてください!
【「国税専門官 やめとけ」と調べる人からよくある質問】
- 国税専門官になるにはどうしたらいい?
- 国税専門官の仕事は楽しい?
- 国税専門官が不人気なのはどうして?
- 国税専門官のきつい部分は?
質問① 国税専門官になるにはどうしたらいい?
他の国家公務員になる場合と同様に、人事院が実施する試験への合格が必要です。
具体的には、人事院が実施する「国税専門官採用試験」に合格した上で、採用されることが必要となりますね。
同試験の最終合格者は、採用候補者名簿に記載されることとなっています。
そして、この名簿のなかから毎年の採用状況を考慮して、東京・名古屋・大阪をはじめとする全国の国税局に採用されるといったイメージです。
具体的な採用ステップや受験資格は、国税庁のホームページ「国税専門官に関するQ&A」にてまとめられていました。
より詳細な情報を得たい人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
質問② 国税専門官の仕事は楽しい?
何に楽しさを感じるかは人によるので、一概に回答することはできません。
ただ、国税専門官として働く人の声を見ていると、専門知識やコミュニケーション力などを求められる難しい仕事だからこそ、やりがいや達成感があるようですね。
公共のための仕事であること、スケールの大きな仕事を任せてもらえることにやりがいを感じている人もいました。
国税庁のホームページにて「先輩職員からのメッセージ」が公開されているので、関心がある人は上記にも目を通してみるといいですよ!
質問③ 国税専門官が不人気なのはどうして?
そもそも、不人気かどうか?の考え方は人によって異なるかと。
その上で国税専門官が人気になりづらい理由を考えると、やはり業務上プレッシャーを感じる場面が多いことがあげられると思います。
正しく税金を納めてもらうために納税者とやり取りをする場面が多くあり、その際にネガティブな言葉を浴びせられることは少なくないんですよね。
専門性やコミュニケーション力など、求められるレベルが高いことも就職先として選ぶ際のハードルが上がっている要因といえるかもしれません。
質問④ 国税専門官のきつい部分は?
納税者とのやり取りにストレスを感じること、緻密かつ正確性を求められる仕事が精神的にプレッシャーになることなどがあげられます。
学習が苦手な場合、専門知識の習得にきつさを感じる人もいるかもしれません。
こうした部分を想定せずに就職を決めると、後悔につながる恐れがあります。
もちろん良い部分も多くありますが、国税専門官を志望する場合は上記のような懸念点は確実に押さえておきましょう。
実際に国税専門官として働く方のインタビューは、やりがいや大変さなどの業務理解を深める上でかなり参考になりそうですね!
国税庁が用意している記事だし、国税専門官が気になっている人は一度は目を通しておくといいよ!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
国税専門官への就職はやめておくべき?と悩む人に向けて、僕なりの結論や一般的にやめとけと言われる理由などを網羅的に共有しました。
結論、個人的には国税専門官への就職は十分アリだと考えています。
年収水準もかなり高めですし、勤続年数に応じて税法への専門知識を深めることができスペシャリストとしてキャリアを積める点はやはり魅力的です。
一方、専門知識の習得の大変さなど想定される懸念点も事前に把握しておくべきかと。
自分にとって良い面・悪い面のどちらが大きいと感じるか?が大切なので、情報を集めた上で総合的にどうかをじっくり検討してみてくださいね!
ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「就活マンが考える「就活を成功させるために必須の6大ポイント」を共有!」も読んでみてください。
僕が現状考えるもっとも有効な就活の攻略法を簡潔にまとめています。
就活全体を見据えてとくに重要な対策のみを厳選しているので、全体を意識した対策ができていない人はぜひ一読してみてください。
それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!
【本記事の要点】
- 税法などに専門性を持って働きたい人には、国税専門官はおすすめの職種である。
- 納税者とのやり取りや正確性を求められる仕事、専門知識の学習を続ける必要があることなどにストレスを感じる可能性は想定しておくとよい。
- 平均年収が高いこと、スペシャリストとして専門性を高められることはメリットと言える。
- 国税専門官との相性を判断する際には、分析力・倫理観と誠実性・精神力と忍耐力・言語化力とコミュニケーション能力の有無を考えるとよい。
- 国税専門官への応募を迷っている人は、国税庁が公表する先輩社員のインタビュー記事を確認しておくべきである。







