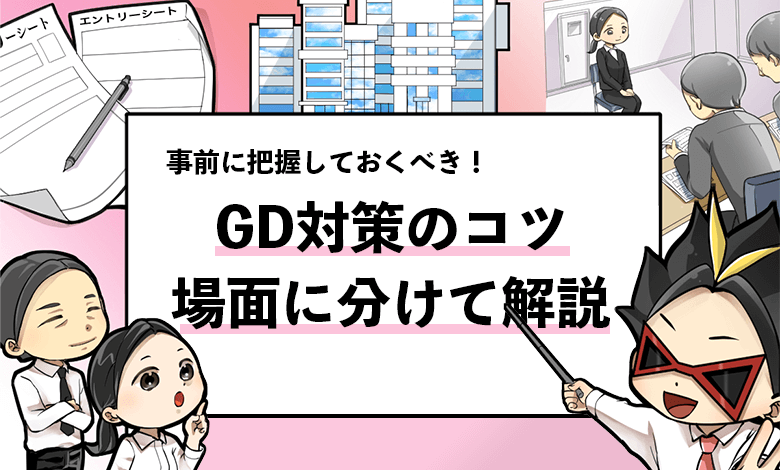
【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
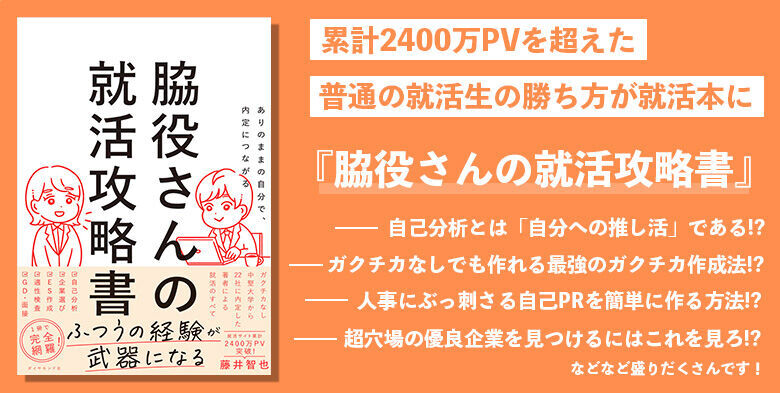
それでは本題に入っていきますね!
グループディスカッションに苦手意識を持っている人は多いのではないでしょうか?
僕も大学1年生で初めて参加したときは苦手意識が強かったです。
ただ、グループディスカッションは“対策できる選考”です。
面接やESは評価ポイントが企業ごとに違うので、通過率を100%にすることは不可能。
しかし、グループディスカッションは明確に評価ポイントが決まっているので、通過率を100%にすることができるんですよね。
僕も苦手を克服しようとグループディスカッションについて研究し尽くした結果、就活中のグループディスカッションの通過率は100%でした。
そこで今回は、僕が実践していたグループディスカッションのコツをご紹介していきます!
本記事のコツを実行するだけで、通過率が跳ね上がることは間違いないので、ぜひ参考にしてくださいね!
グループディスカッションってなんだか難しそうなのでコツがあるならぜひ知りたいです!
任せて!僕が実際に行っていた必ず役に立つコツだけをまとめたよ。
- グループディスカッションのコツ|事前準備編
- 【必見】グループディスカッションを回避する方法
- グループディスカッションのコツ|本番編
- グループディスカッションのコツ|オンライン編
- グループディスカッションで企業が評価するポイント
- 本記事の要点まとめ
グループディスカッションのコツ|事前準備編

では、僕が意識していたグループディスカッションのコツを紹介します。
事前準備・選考の本番中・オンラインと場面ごとに対策のコツをまとめました!
まずはグループディスカッションの選考前にすべき対策のコツを共有していきます。
【グループディスカッション本番前の対策のコツ】
- 全体の進め方を把握しておく
- 役割ごとの立ち回りを理解しておく
- 反論の仕方をマスターしておく
- 論理的思考をクセづけておく
- 発表のポイントを把握する
- 経験者の声を聞く
- とにかく場数を踏む!
ちなみに、「そもそもグループディスカッションを受けたくない…」という人は、逆求人サイトを活用してみてください!
逆求人サイトは、プロフィールを登録しておくと企業からスカウトが届く求人サイト。
スカウトが届いた企業では、いきなり個人面接から始まるなど選考をスキップできることも少なくないんですよね。
つまり、グループディスカッションを受けずに選考を進められる可能性があるということ!
利用するなら、大手の「キミスカ」がベストです。
スカウトが3種類あるので、企業の本気度が高いゴールドとシルバーのみを狙ってみてくださいね!

コツ① 全体の進め方を把握しておく
まずグループディスカッションがどのような流れで進むのか、「全体の進め方」を把握しておきましょう。
グループディスカッションの進め方は、以下のとおり。
【グループディスカッションの進め方】
- 役割分担
- 時間配分の決定
- テーマの本質を見抜き前提を決める
- グループでの目標設定
- 話し合い
- 結論まとめ
- 発表
まずはお互いに自己紹介をしたうえで、役割分担に入っていきます。
役割分担はグループディスカッションの工程のひとつなので、必ず役割を決めてから話し合いに入っていきましょう!
コツ② 役割ごとの立ち回りを理解しておく
役割ごとの立ち回りも理解しておきましょう。
グループディスカッションでの役割は、主に以下の5つに分けられます。
【グループディスカッションの役割】
- 司会(ファシリテーター)
- 書記
- タイムキーパー
- 発表者
- 役割なし
役割分担は、立候補することもあれば指名されることもあります。
よって、どの役割も対応できるように立ち回り方を事前に把握しておきましょう。
役割ごとに評価されるポイントや注意点も違います。
以下の記事でそれぞれの役割についてまとめているので、読んでおいてくださいね!
コツ③ 反論の仕方をマスターしておく
次に紹介するコツは「反論の仕方をマスターしておくこと」です。
話し合いをしていると、必ず「こいつ何言ってんねん!」と思うことがあります。
僕もグループディスカッションをする中で、的外れな意見ばかり言う人に遭遇したことがよくあります。
そんな時に「お前何言ってるの!」と言うのは当然NG。
うまい反論の仕方を知っておくことで、協調性をアピールできますよ。
【うまい反論の仕方】
「たしかにそういう意見(見方・アイデア)もありますよね!」
=まずは相手に共感を示す。否定はしない。
「他にも◯◯という見方ができるかもしれないですよね!」
=あくまで他の見方があるというスタンスで反論する。
まずは相手の意見に共感したうえで、別の意見を提示するという方法ですね。
この反論の仕方はプライベートでも役立つので、良好な人間関係を作るためにぜひマスターしておいてください。
コツ④ 論理的思考をクセづけておく
次に大切なのは、論理的思考をクセづけておくこと。
グループディスカッションにおいて論理的思考は重視されます。
論理的思考とはかんたんに言うと、発言に対する「理由」が明確であること。
たとえばアイデアが浮かんだときに、「なぜそのアイデアが有効なのか?」をしっかり回答できることが重要。
さらに、そのアイデアが現実可能なのか?といったことまで考えられると、納得性が高まりますよね。
反対に「理由」がない思いつきのアイデアをいってしまうと、論理的思考ができていないと判断されてしまいます。
自分のアイデアや発言に対して、常に「理由」をセットで持っておくこと意識してグループディスカッションにのぞんでくださいね。
ちなみに、論理的思考について知識を深めたいという人には、「考える技術・書く技術」という本おすすめ。
大ボリュームですが、第1章〜第3章まで読むだけで論理的思考について理解が深まるので、そこだけでもぜひ読んでみてくださいね!
コツ⑤ 発表のポイントを把握する
グループディスカッションでは、必ず最後にグループの結論を発表します。
評価される発表のポイントは以下の5つ。
【評価される発表のポイント】
- まずは結論から述べる
- 一人称を「私たち」にする
- とにかく「なぜ」を明確に説明する
- 他のメンバーをさりげなく褒める
- 前向きな言葉で締める
この5つの発表のコツを押さえておくことが重要です!
とくに論理的思考に繋がる「とにかくなぜを明確に説明すること」は重要ですね。
またどんな時でも結論ファーストで話すように心がけてください。
この5つのコツの詳細については別記事で詳しく解説しています。
そちらを参考にしてください!
コツ⑥ 経験者の声を聞く
グループディスカッションを勝ち抜くには、経験者の声を聞くことも重要!
どんなことにつまずいたのか、どこが難しかったのかなどを事前に知ることで対策が取れるからです。
僕の方でグループディスカッションに参加した3名の方から体験レポートを頂いたので紹介しますね。
(今回は3名とも現役の就活生なので、大学名のみの紹介とさせていただきます。)
【質問内容】
グループディスカッションを経験した感想を何でも構わないので記載してください。
(合わせてグループディスカッションの経験回数だけ記載をお願いします)
日本大学 (20卒)男性
今回はグループディスカッションを初めて経験しました。
正直志望度が低い企業の選考だったにで事前の対策を全くしておらず、とにかく受け身で参加してしまいました。
その結果は惨敗です。
お祈りメールを頂きました。
振り返ってみると、グループディスカッションで行ったことと言えば意見を2回言う程度でした。
その2回の意見もありきたりな内容で、特にそこからの会話の展開もなく対策してこなかったことを後悔しました。
私は人と会話することが得意だと考えていたので対策をしなかったのですが、全く歯が立ちませんでした。
同じグループで活躍していた人を思い出すと、流れがすべて頭に入っているようでしたね。
役割決めから時間配分の決定、意見が言えていない僕らへのヒアリング含めて完璧な立ち回りでした。
大人しいタイプのように見えていたのですが終了後に話を聞いたところ、グループディスカッションの経験回数はこれで6回目とのことでした。
納得です。
名城大学 (20卒)女性
先日グループディスカッションに2回目の参加をしました。
1回目は書記として大人しく参加していたのですが、もっと目立つべきかなと考えて「司会」の役割に立候補することにしました。
結果としては不採用となってしまいました。
理由を考えると、司会を立候補したにも関わらずあまり積極的にやることを指示できなかったことにあると思います。
私自身、もともと大人しい性格なのでいきなり司会をして目立とうとしても上手く立ち回ることができないと実感しました。
次にグループディスカッションがある時はまた書記として立ち回ろうと思います。
愛知県立大学 (20卒)男性
先週、3回目のグループディスカッションに参加してきました。
結果は通過でした。
1回目は全く対策をしてなかったので惨敗してしまい、その後、就活攻略論のグルディスの記事を読んで対策しました。
2回目、3回目からはグルディスの流れと評価される展開の流れが事前に分かっていたのでそれに従って書記として立ち回っていたところ、各テーブルを回っていた面接官から「課題の本質が分かっているね」と褒められました。
1回目で惨敗してから事前対策の重要性を強く感じました。
協力してくれた3名は改めて本当にありがとうございました。
コツ⑦ とにかく場数を踏む!
グループディスカッションでもっとも大事なのが、場数を踏むことです!
よく「練習でできないことは本番でもできない」と言いますよね。
グループディスカッションに関して、まさにこれが言えます。
とくに「参加したことがない」と「1度参加したことがある」のは大きく違います。
一度も経験していない人と、複数回経験がある人では立ち回り方も変わってくるんですよね。
ただ、場数を踏むために志望度の低い企業の選考を受けようとするのはやめてください。
効率が悪いですし、そもそも企業の方に失礼ですからね。
そこで僕がおすすめしているのが、中小規模の合同説明会に参加する方法です。
中小規模の合同説明会とは、数社の企業と数十人の就活生で行われる説明会のこと。
中小規模の合同説明会では、グループディスカッションが行われることも多いです。
そして、その様子を見ている企業から直接スカウトされることもあります。
▼中小規模の合同説明会の様子

とくにおすすめなのは、「ミーツカンパニー」です。
僕も就活生時代に2度参加して、2社から内定をもらいました。
オンラインイベントもあるので、全国の就活生が参加できますよ。
開催頻度も高いので参加できるイベントがあるかチェックしてみてくださいね!
【ミーツカンパニーの参加方法】
- 「
ミーツカンパニー公式サイト」にアクセス
- 30秒無料エントリーをクリックし参加したいイベントを選択
- メールの案内に沿って当日イベントに参加する
たしかに知識として覚えていても実際には動けない、なんてこともありますもんね。
グループディスカッションはまさにそう!知識で覚えるよりも場数を踏んで体で覚えるのが有効だよ。
【必見】グループディスカッションを回避する方法

ここまででグループディスカッションのコツを共有しました。
ただ実際は、「グループディスカッションは本当に受けたくない…」という人も多いのではないでしょうか?
そんな人は、グループディスカッションを避けるのもひとつの手です。
グループディスカッションを避けるには、以下の2つの方法があります。
【グループディスカッションを避ける方法】
- 就活エージェントを利用する
- 逆求人サイトに登録する
避ける方法① 就活エージェントを利用する
まず1つ目は、就活エージェントを利用する方法です。
就活エージェントは、面談を行いあなたの要望に合う求人を紹介してくれるサービス。
就活エージェント経由で選考を受ける場合は、基本的に個別対応です。
つまり、グループディスカッションを避けられるということ!
また、就活のプロが選考対策もサポートしてくれるので内定獲得にも一気に近づきます。
グループディスカッションを避けて自分に合う企業から内定をもらいたい人は、必ず就活エージェントを利用しましょう!
僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」
サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。
ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。
就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。
またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。
運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。
就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。
▼就活エージェント利用者の声
初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑
— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020
なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな
もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう
(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)
避ける方法② 逆求人サイトに登録する
2つめの方法は、逆求人サイトに登録すること。
逆求人サイトとは、プロフィールを登録しておくと企業側からスカウトが届くサイトです。
就活生のプロフィールを読んだうえで自社に合いそうだなと感じた学生に、企業はスカウトを送っています。
よって、スカウトを経由してすぐに面接に進む場合も多いんですよね。
そうするとグループディスカッションを受ける必要はありません。
▼逆求人サイトで内定を獲得した人の声
@Kimisuka1
— shi*26卒 (@Ooo_river_) January 17, 2023
キミスカさん経由でつながった企業さんから初めての内定をいただきました😭ありがとうございます😭今後もお世話になります…!
僕としては、とくに「キミスカ」がおすすめ。
キミスカはスカウトが3種類あり、企業の本気度を見極めやすいのがメリット。
また、僕の会社で運営している「ホワイト企業ナビ」は、一定の条件を満たしたホワイト企業からしかスカウトが届きません。
自分では見つけきれなかった優良企業と出会いたい人は、ぜひ登録してくださいね!

ちなみに、逆求人サイトごとに利用している企業が違うので、いくつかを同時に利用するのが一番効果的な方法です。
以下の記事で、おすすめの逆求人サイトをランキング形式で紹介しているのでチェックしてみてください!
グループディスカッションを避ける方法もあるんですね!
そうだよ!グループディスカッションを避けたい人は、就活エージェントと逆求人サイトの登録は必須だよ!
グループディスカッションのコツ|本番編

つづいては、グループディスカッション本番中に意識すべきコツを共有していきますね!
たくさんのコツを覚えるのは難しいので、本当にやるべきコツだけを厳選して紹介します。
【グループディスカッション本番中のコツ】
- メンバーと雑談しておく
- タイムキーパーはしない
- 時間配分は「バッファ」を設ける
- 課題を具体化する
- 話し合いのゴールを明確化する
- 他のメンバーに共感する
- 発言できていない人をフォローする
- アイデアをいう場合は「理由」もセット
- 常に時間を気にかける
コツ① メンバーと雑談しておく
まず僕が意識していたことは、話し合いが始まる前に「雑談」をしておくこと。
グループディスカッションは初対面の人同士で話し合いをすることになります。
友だちと話し合いをするよりも、初対面の人と話す方がむずかしいですよね?
つまり、心を許している相手との方が会話はしやすいんですよ。
よって、少しでもグループメンバーと心を許し合うために、事前に雑談をしておきましょう。
自分から積極的に声をかけることがポイントです。
雑談の内容は何でも良いのですが、例を紹介しておきますね。
【雑談の振り方】
-
皆さん、今日はどちらからいらしたんですか?
(→どこの大学なのか?のような話に広げることが可能)
-
皆さん、グループディスカッションは何度かされたことがあるんですか?
(→緊張しますよね〜といった感じで共感し合うことが可能)
ちなみに雑談の内容として、「どの業界を受けているんですか?」とか「他にどの企業受けてますか?」といった話は控えるべきです。
人事に聞かれると、「他の企業の話をしているのか」とネガティブに捉えられてしまう可能性があるからです。
よって雑談はプライベートな話をしたり、グループディスカッション自体の話をするのがベスト!
雑談によって心を開く作業は、あらゆる場面で効果的ですよ。
コツ② タイムキーパーはしない
グループディスカッションで役割分担は必須ですが、タイムキーパーはおすすめしません。
就活サイトを見ていると、「タイムキーパーは難易度が低いのでおすすめ」とか書かれていることがありますが、それは違いますね。
難易度が低い、つまりやることが決まりきっているからこそ、アピールすることができない役割でもあるのです。
タイムキーパーは「時間」を常に意識する必要があります。
やってみると分かりますが、残り時間と経過時間を把握することって意外にも重労働。
他のことが手に付きません。
よってタイムキーパーの役割をすると、何もアピールできずに終了となる可能性が高いので避けることをおすすめします!
コツ③ 時間配分では「バッファ」を設ける
グループディスカッションでは、最初に「時間配分」をすることが重要です。
そして時間配分をするときには、必ず「バッファ(空き時間)」を設けましょう。
例えば与えられた時間が15分の場合、下記のように時間配分しがちです。
1分:役割分担
1分:課題をより具体的にする
1分:課題に対するゴールを設定する
10分:話し合い
2分:発表のまとめ
しかし、実際には話し合いが長引いたりと、最初に決めた時間配分の通りにいかないことがほとんど。
そんな時のために、例えば「バッファ:1分」を設けることが重要です。
1分:役割分担
1分:課題をより具体的にする
1分:課題に対するゴールを設定する
9分:話し合い
2分:発表のまとめ
1分:バッファ
空き時間を設けると、話が長引いたり計画通りにいかなかった時の穴を埋めることができます。
「空き時間がある」というのは、話し合い中の余裕にも繋がるので意識してくださいね!
コツ④ 課題を具体化する
課題を具体化することもコツのひとつ。
グループディスカッションで与えられるテーマは、抽象的であることが多いです。
たとえば、「コンビニの売上を2倍にしてください」というテーマ。
この課題は「いつまでに2倍にするのか?」「どの店舗の売上を2倍にするのか?」「地域はどこなのか?」といった具体的なことが抜けていますよね。
グループディスカッションでは、課題が具体的であるほど話し合いがしやすくなります。
テーマがあいまいだった場合は、具体的な課題へと落とし込みましょう。
【抽象的な課題】
コンビニの売上を2倍にしてください
↓
【具体的な課題】
全国にあるコンビニ1チェーンの売上の合計を、1年以内に2倍にしてください
【発表の仕方】
「私達のグループでは、課題を『全国にあるコンビニ1チェーンの売上の合計を、1年以内に2倍にしてください』とより具体化して考えました」
このように発表すれば、面接官からの評価は上がります。
抽象的な課題は、具体化してから話し合いを進めましょう!
ちなみに、グループディスカッションで出題されるテーマを70例紹介している記事を用意しています。
ぜひそちらも参考にしてくださいね!
コツ⑤ 話し合いのゴールを明確化する
次に、話し合いのゴールを明確にしておくことが大切です。
たとえば「コンビニの売上を2倍にするための具体的なアイデアを1つ導き出そう」といった感じです。
つまり「話し合いのゴールはどこまでなのか」を明確にするということ。
そんなの決めなくても良くない?と思う人もいるかも知れません。
しかし、人によっては「2倍にするためのアイデアをとにかく出しまくろう!」と思っている人がいたりするんですよね。
人それぞれで話し合いの「ゴール」の認識が違うことはよくあります。
ディスカッションを始める前に、グループとして「◯◯しましょう」というゴールをしっかり設定することがおすすめです!
コツ⑥ 他のメンバーに共感する
話し合いの最中は、他のメンバーに共感することも忘れずにいましょう。
メンバーが出した意見やアイデアに対して、まずは前のめりで話を聞くこと。
そしてすぐに否定するのではなく、共感しようということです。
そもそも、企業がわざわざ選考にグループディスカッションを導入するのには理由があります。
まず1つ目は短時間に複数人を選考することができるから。
そして2つ目は、会社で活躍できる人材を見極めるためです。
そしてグループディスカッションを通して、見極めるポイントの中で「協調性」は非常に大きい評価点となります。
会社は人の集まりなので、協調性がないとなかなか活躍できない。
一匹狼タイプの人を採用したいという企業は、わざわざグループディスカッションをしないですからね!
グループディスカッションで「協調性」を示すためにも、メンバーへ共感を示すことを大事にしてください。
コツ⑦ 発言できていない人をフォローする
話し合いの中で「発言できていない人をフォローすること」も評価されるためのコツですね。
「協調性」をアピールするにも最適ですし、発言できていない人をサポートすることで「積極性」もアピールすることができます。
そもそも数人集まったら、会話が得意な人と苦手な人が必ずいます。
会話が得意な人がバンバン意見を出していく流れになりやすいので、意見があまり言えていない人が必ず出てくるんですよ。
その時に「◯◯さんはどう思いますか?」とさりげなくフォローしてあげる。
これは別に司会の役割じゃない人がしても、全く問題ありません!
この行動をするだけで、「協調性」や「積極性」がアピールできるので本当におすすめのテクニックですよ!
コツ⑧ アイデアをいう場合は「理由」もセット
アイデアを言うときに、必ず「理由」もセットで話すのも重要なコツです。
「◯◯とか面白そうじゃない?」「◯◯ができそうだよね!」アイデアだけを放り投げる人も多くいます。
しかし、アイデアだけでは意味がありません。
なぜならグループディスカッションは最終的に発表するもので、グループで出した結論を面接官に伝えることが目的だからです。
グループで出した結論には、第三者を納得されるための理由が必要なのです。
よって、どんなアイデアにも必ず理由をセットで発言するようにしましょう。
また、アイデアだけを放り投げる人に対しては、「うんうん」と共感するだけでなく、以下のように理由をみんなで深堀りしていくことが重要です!
【アイデアに対しての掘り下げ方】
「売上を上げるために◯◯って企画やるのはどうかな?面白そうじゃない?」
→「うんうん、たしかに面白そうだね。でもなんでそれに対して面白いって直感的に思うんだろう!そのアイデアがウケる理由を深堀りしてみない?」
このようにアイデアに対する「理由」をグループで深堀りしていく。
これは会話も広がるので本当におすすめのコツですよ!
コツ⑨ 常に時間を気に掛ける
話し合い中には常に時間を気にかけることも大切です。
グループディスカッションではタイムキーパー役がいるので、「時間はタイムキーパーに任せれば良いや!」となりがち。
しかし、タイムキーパーに頼りきりにならず「話し合いの時間はあと何分ほどですか?」と聞けるような人は評価されます。
社会人になると「時間」への意識を高くもつ必要があります。
よって「私は時間を大事にしている人だよ!」とアピールするためにも、常に時間を意識するようにしましょうね。
グループディスカッションのコツ|オンライン編

近年は、グループディスカッションもオンラインで行われることが増えてきました。
そこでオンラインでのグループディスカッションのコツも共有していきますね!
【オンラインのグループディスカッションのコツ】
- 視線はカメラに向ける
- リアクションはオーバー気味にする
- 挙手してから発言する
- イメージを共有する
コツ① 視線はカメラに向ける
オンライングループディスカッションでは、「視線」を意識することが重要です。
つい画面に映っている人の顔を見てしまいがちですが、相手からはうつむいているように見えてしまいます。
よって、カメラを見るように気をつけましょう。
ただ、ずっとカメラだけを見つめていると発言している人の表情などがわかりませんよね。
ですので、少なくとも自分が発言をするときにはカメラを見るように意識しましょう。
コツ② リアクションはオーバー気味にする
リアクションはオーバー気味にするのも大事なコツです。
オンラインだと対面よりもリアクションが伝わりづらくなります。
相づちをうっているつもりでも、画面越しだと反応が伝わらないこともあるんですよね。
たとえばあなたが発言しても相手が反応してくれていないと感じると、それ以降は話しづらくなってしまいますよね。
相手に「きちんと話は伝わっているし聞いているよ」と伝えるためにも、リアクションはオーバー気味にするように意識してください。
具体的には以下の点に注意しましょう。
【意識すべきリアクション】
- 表情はいつもよりはっきり作る
- 声は大きめに出す
- 話すスピードはゆっくり
- 滑舌よく話す
とくに他のメンバーが発言しているときは、笑顔を意識したり大きくうなずくとしっかりと反応が伝わりますよ。
コツ③ 挙手してから発言する
オンラインでのグループディスカッションだと、発言するタイミングが被ってしまうことも少なくありません。
そこで、話し合いをはじめる前に「発言するときには手をあげる」と決めてしまうのがおすすめです。
メンバーみんなが話すタイミングを見計らっていると、なかなかスムーズに話し合いも進みませんからね。
オンラインでのグループディスカッションの場合は、挙手してから発言するように決めましょう。
コツ④ イメージを共有する
イメージを共有するのも重要なコツです。
対面のグループディスカッションであれば、紙やホワイトボードに話し合いの内容を目もできます。
しかし、オンラインだとできませんよね。
話している内容をメモできないと、結論を整理するのも難しくなってしまいます。
そこで、オンラインの場合はイメージを共有するのが有効です。
具体的には以下のような方法があります。
【オンラインでのイメージ共有方法】
- 画面共有でメモ帳を他メンバーに共有する
- 紙にメモを書いて画面に映しこむ
- 描画ツールが使える場合は簡単なイラストを書いて公開する
- Googleドキュメントで議事録をとる
上記のような方法を用いることで、オンラインでも話し合いの内容をまとめやすくメンバーにもイメージを明確に共有できます。
また、オンラインでも試行錯誤してイメージを共有する姿は、企業からも評価されるでしょう。
ここまででオンラインのグループディスカッションのコツをお伝えしましたが、より詳しい解説や注意点は以下の記事でまとめています。
こちらも併せて読んでおいてくださいね!
たしかにオンラインだと表情とかも見えづらいですよね。
そうなんだ。普段よりも意識して表情をつくるのもオンラインのコツだよ。
グループディスカッションで企業が評価するポイント

グループディスカッションを通過するには、「どんな点が評価されるのか?」を事前に把握しておくことが大事です。
企業がどのような部分をみて評価しているのかを知ることで、適切な立ち回りがしやすくなります。
【グループディスカッションで企業が評価するポイント】
- 積極性、自発性
- 協調性、周りへの気遣い
- コミュニケーション力
- 論理的思考力
- 戦略性
- グループディスカッションに参加する姿勢
上記の能力がある人は「社内で活躍できそうだ」と判断されやすい。
グループディスカッションにおいても、これらの能力があると判断されれば通過しやすいと考えることができますね。
以下で現役の人事にきいた「グループディスカッションで重視するポイント」をまとめているので、ぜひ読んでください!
グループディスカッションで落ちる人の特徴
グループディスカッションで評価されるポイントと共に、落ちる原因についても把握しておきましょう。
評価ポイントと落ちる原因どちらも知っておくことで、グループディスカッションの通過率を高められますからね。
グループディスカッションで落ちる人の特徴は、以下のとおり。
【グループディスカッションで落ちる人の特徴】
- 周りの意見をまったく聞かない
- 論点がズレている
- 他人の批判ばかり言う
- 人の意見に同調してばかりいる
上記のような人は、グループディスカッションで落ちる可能性が高いです。
人の意見を聞かなかったり批判ばかりしていると、「協調性がない」と思われてしまいます。
自分の意見を言わなかったり、テーマの本質を理解できていないこともマイナス評価につながります。
グループディスカッションでの通過率を高めるためにも、「自分の意見を持つこと」「人の意見を聞くこと」「課題の本質を把握すること」を意識してくださいね!
以下の記事で、グループディスカッションで落ちる原因について詳しく解説しています。
グループディスカッションに参加する前に、一度は目を通しておいてください!
ただグループディスカッションに参加するよりも何を見られているかを意識することが大事ですね。
そう!企業が重視するポイントを知ることで評価される立ち回りができるからね。
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました!
グループディスカッションは本番だけでなく、事前準備にもコツがあります。
今回ご紹介したコツを参考にしてくださいね。
中小規模の合同説明会で場数を踏むことで、グループディスカッションの進め方や立ち回り方のコツも体感的につかめますよ。
あなたがグループディスカッションで通過し、希望の会社からの内定を獲得できることを心から願っています。
また「これだけ読めばグループディスカッション対策が完了する」というまとめ記事も別で用意しています。
ぜひこちらの記事と合わせて読んでくださいね!
では最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう。
【本記事の要点まとめ】
- グループディスカッションはしっかり対策すれば通過率100%を狙える。
- グループディスカッションを受ける前にはとにかく場数を踏むことが何よりも重要。
- グループディスカッションの本番中は時間配分やゴールを明確にしつつ、周りの人の発言へのリアクションやフォローも意識する。
- オンラインでのグループディスカッションの場合はとくにオーバーリアクションを心がける。
- グループディスカッションを避けたい人は就活エージェントと逆求人サイトの利用がおすすめ。









