
【2025年9月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。
(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!
最近はグループディスカッションを実施する企業が増えています。
グループディスカッションで何をすればいいか、どう動けばいいのか分からず不安を感じている人も多いのではないでしょうか?
グループディスカッションでは、役割ごとに行うべきことも違います。
そこで今回は、グループディスカッションの役割についてまとめました!
役割によっては立ち回り方を間違えると、マイナス評価につながってしまうこともあります。
各役割の評価ポイントと注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
グループディスカッションでどんな役割が必要なのかわからないです。司会と書記くらいしか…。
大きく5つの役割が必要だよ。それぞれどんなことをするのか、どこを評価されるかを伝えていくからしっかり把握してね!
- グループディスカッションで役割を決めないのはNG
- グループディスカッションの役割
- グループディスカッションでの役割分担の方法
- グループディスカッションを避けるのも戦略
- グループディスカッション前に行うべき5つの対策
- グループディスカッションで企業がみている評価ポイント
- グループディスカッションの役割についてよくある質問
- 本記事の要点まとめ
グループディスカッションで役割を決めないのはNG

役割分担はグループディスカッションの工程の一つなので、役割を決めずに話し合いを進めるのは絶対にNG。
役割分担を行わずに話し合いを進めようとすると、工程を飛ばしたことになるのでマイナス評価につながる可能性があります。
また、グループディスカッションは話し合いの時間が決まっているんですよね。
役割を決めずに話し合おうとしても、うまくまとまらなかったり気づいたら時間が過ぎていたりする場合があるでしょう。
決められた時間内にスムーズに話し合いを進めて結論まで導き出すためにも、必ずはじめの段階でそれぞれの役割を決めておいてください。
グループディスカッションの流れ
グループディスカッション全体の流れを把握することで、役割分担の重要性もわかるかと思います。
グループディスカッションは、以下の流れで進んでいきます。
【グループディスカッションの流れ】
- 役割の決定
- 時間配分の決定
- 課題の本質を見抜き前提を決める
- グループでの目標設定
- 話し合い
- 結論まとめ
- 発表
はじめにお互いに自己紹介をしたあと、各役割を決めていきます。
グループディスカッションの最初の工程である、役割分担をせずに進めても不採用となる場合がほとんどです。
まず最初にしっかり役割を決めた上で話し合いを進めていきましょう。
グループディスカッションの実施時間は、平均30〜45分ほどです。
全体の流れを把握していないと、「前半で時間を費やしてしまった…!」なんてことになりかねません。
グループディスカッション全体の流れはしっかり覚えておいてくださいね。
流れを把握して進めないと時間切れになってしまいそうですね。
そうなんだ。制限時間の中で、どこにどれくらい時間をかけるか考えて進めることが大事だよ。
グループディスカッションの役割

ではグループディスカッションでの役割についてご紹介していきますね。
グループディスカッションでは、主に以下の5つの役割に分類されます。
【グループディスカッションの役割】
- 司会(ファシリテーター)
- 書記
- タイムキーパー
- 発表者
- 役割なし
グループディスカッションでは目立つ役割の方が有利といったイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。
どの役割も必要であり、それぞれ評価されるポイントも違います。
それぞれの役割で評価されるポイントと注意すべき点も合わせて解説していくので、しっかり読み込んでくださいね!
役割① 司会(ファシリテーター)

司会は、話し合いの進行を担う役割です。
決められた時間内に、話し合いをして結論を出すところまで進める役割なので難易度の高いポジションと言えます。
司会は自らが積極的に発言するというより、周りの人の意見を引き出しまとめていけるかがポイントです。
難しい役割である分、うまく活躍できると高く評価してもらえます。
【司会で評価されるポイント】
「段取り力」「積極性」「協調性」「本質理解力」「発想力」の5つ。
司会には、制限時間が設けられている中で効率的に話し合いを進めていく能力が求められます。
「意見の少ない人への気遣い」「制限時間への配慮」の2つができれば、間違いなく評価されますよ。
注意点
司会というと「積極性」ばかりをアピールしがち。
しかし、自分ばかり発言したり無理やり結論をまとめようとすると、「自己主張が強い」とマイナス評価を受けてしまうので要注意です。
また、話し合いを進めることばかりに意識をとられ、時間がオーバーしないように注意してください。
役割② 書記

書記は、話し合いの内容を紙にまとめていく役割です。
僕がグループディスカッションの中で最もおすすめする役割でもあります。
議論の要点をわかりやすくまとめる能力が求められます。
全体の意見を把握できる書記だからこそ、積極的に意見をまとめる時間を作るなどうまく立ち回ることで高い評価を得られますよ。
【書記で評価されるポイント】
「積極性」「本質理解力」の2つ。
話し合いの中で要点を把握してまとめる能力が大切。
誰が見てもわかりやすいよう工夫してまとめられると、高く評価されます。
また、グループの意見をまとめながら自分自身も積極的に発言していくことが大切です。
注意点
ただ紙に話し合いの内容をそのまま書くだけではNGです。
メンバーや人事の人、誰が見ても議論内容が分かるようにまとめましょう。
また、議事録を取るのに夢中になりすぎて意見を出さない、なんてことにならないよう注意してください。
役割③ タイムキーパー
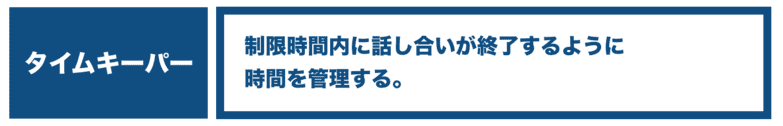
タイムキーパーは、ディスカッションの時間を管理する役割です。
話し合いが盛り上がると、熱中して時間を忘れてしまいがち。
その中で、定期的に経過時間を知らせ、ディスカッションの進行をコントロールするのがタイムキーパーの役割です。
【タイムキーパーの評価ポイント】
「段取り力」「協調性」の2つ。
タイムキーパーは、経過時間を意識して進行が押しているときには「次にいきましょう」と呼びかける必要があります。
よって、段取り力が問われる役割なのです。
また、時間を管理しながら積極的に意見を出したり他の役割のサポートをすると、「時間管理だけじゃなく、グループ全体を見て動けているな」と評価されます。
注意点
タイムキーパーは、常に時間を気にしなければいけないので意外と大変です。
しかし、大変な割には時間管理の能力というのは評価されない。
よって僕は、タイムキーパーの役割につくことはおすすめしません!
ただ、タイムキーパーをするしかない状況になることもあります。
その場合は、議論が盛り上がっていてなかなか時間を言い出せない…なんてことにならないようにしっかり時間管理を行ってくださいね!
役割④ 発表者

発表者は、グループでまとめた結論を代表して発表するのが役割です。
ディスカッションでまとまった意見を、聞く人に伝わりやすいように論理的に解説するのがポイント!
また、結論を発表するだけでなく、グループでの話し合いの過程やメンバーへの称賛を加えられると評価は高くなるでしょう。
【発表者の評価ポイント】
「積極性」「協調性」の2つ。
発表者を担う上で、協調性をアピールできるテクニックがあります。
同じグループで役割なしだった人に、「みんなで発表しませんか」と呼びかける方法です。
役割なしの人がいなくなるように呼びかけるだけで、「周りに気遣いができる協調性のある人材だ」と高評価をもらえます。
注意点
発表者は積極性をアピールできる役割ではありますが、自分ばかり前に出過ぎると「協調性がない」と思われてしまう可能性もあります。
先述の「みんなで発表する」というテクニックを使うことで、積極性と協調性どちらもアピールすることが可能ですよ。
役割⑤ 役割なし

どの役割の担当にもなれない場合もあります。
「役割なしだと評価されないんじゃないか」と不安になる人もいると思いますが、安心してください。
役割がないからこそ意見やアイデア出しに注力できます。
また、役割なしだからこそ、他の役割をサポートできるのです。
【役割なしの評価ポイント】
「積極性」「協調性」「本質的思考力」「発想力」の4つ。
役割なしだからこそ、積極的に発言したり周りの人をサポートすることで協調性もアピールできます。
とくにおすすめなのは、司会をサポートすること!
司会の人はディスカッションの進行で手一杯になってしまう場合が多いです。
そこで、司会の人ができていない部分を補うように立ち回れるとめちゃくちゃ評価されます。
たとえば、時間配分を提案したり、意見が言えていない人に話を振るなど、グループ全体をみて司会の人ができていない部分をサポートしましょう。
他の役割なしの人と違う動きを見せることで、差別化を図ることができますよ!
注意点
役割がないからと、他の人に話を進めるのを任せっきりだと評価はマイナスです。
話し合いに参加していないのと同じですからね。
役割なしの時ほど、必ず意見やアイデアを積極的に出していきましょう!
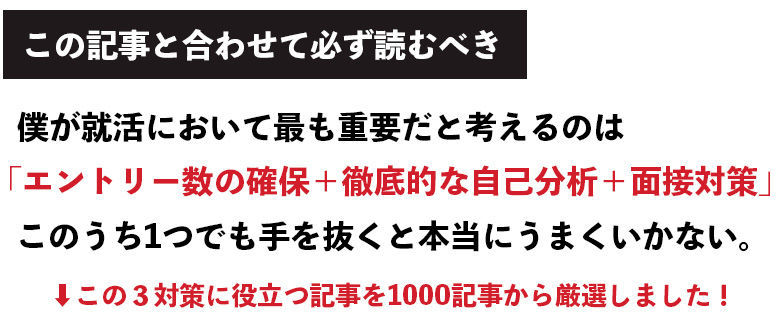
必読記事①:エントリー数を確保するための“ホワイト企業の探し方“の最適解
必読記事②:マンガで分かる自己分析のやり方【徹底的に自己理解が深まる】
必読記事③:面接頻出質問42問【就活マンが考えた回答例もすべて共有】
これまで書いてきた1000記事の中でも、この3記事は最も就活をうまくいかせるのに重要な記事だから絶対に読み込んでくださいね!
グループディスカッションでの役割分担の方法

各役割についての詳細がわかったところで、具体的にどう分担すればいいのかを解説していきますね。
グループディスカッションでの役割分担は、以下の2ステップで完了です。
【グループディスカッションの役割分担の方法】
- はじめに司会を決定する
- 司会が役割を振る or 役割に立候補する
グループディスカッションには制限時間があるので、役割分担に多くの時間を割けません。
そこでまずは、司会を決定していきましょう。
司会が決まったら、次に「書記」「タイムキーパー」を決めていきます。
やりたい人がいれば、自ら立候補してください。
立候補者がいない場合は、司会が指名して役割を決めていきます。
役割が早く決まれば、その分ディスカッションに時間を割けます。
グループディスカッションでの役割分担はサクッと決めていくことが重要です。
グループディスカッションでは役割を指定されることもある
グループディスカッションでは、自分の得意な役割を選んでアピールしたいと思いますよね。
ただ、中には自分で立候補できずに、企業側から役割を指定されることもあります。
つまり、自分の苦手な役割になってしまう可能性があるということ。
自分が立候補しようと思っている役割の対策だけしていても、役に立たない場合もあるのです。
どんな役割になっても対応できるように、各役割の立ち回りと評価ポイントはしっかり頭に入れておきましょう。
グループ内で決めるだけではなく役割を指定される場合もあるんですね。
そうなんだ。苦手な役割を避けてばかりもいられないから、すべての役割に対応できるよう各立ち回りや注意点をしっかり把握しておこう!
グループディスカッションを避けるのも戦略

「苦手な役割を振られるのはいやだ…」と不安な就活生は、あえてグループディスカッションを避けるのもひとつの戦略です。
グループディスカッションを避けるには、以下の2つの方法があります。
【グループディスカッションを回避する方法】
- 就活エージェントを利用する
- 逆求人サイトに登録する
GDを回避する方法① 就活エージェントを利用する
グループディスカッションを受けずに内定を獲得したい人は、就活エージェント経由で選考を受けるのがおすすめ!
就活エージェントとは、面談を元にして自分にあった求人を紹介してくれるサービスのこと。

就活エージェント経由の場合、基本的には個別の選考となります。
つまり、グループディスカッションが課されることはほぼないということ!
「苦手な役割が振られるのは避けたい」「そもそもグループディスカッションに参加したくない」という人は、就活エージェントを利用しましょう。
僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」
サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。
ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。
就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。
またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。
運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。
就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。
▼就活エージェント利用者の声
初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑
— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020
なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな
もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう
(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)
GDを回避する方法② 逆求人サイトに登録する
2つ目の方法は、逆求人サイトに登録すること。
逆求人サイトとは、プロフィールを登録しておくと企業側からスカウトが届く形の求人サイトのことです。
スカウトが届いた企業はいきなり面接から始まることも少なくないので、グループディスカッションを回避できるんですよね。
また、企業はプロフィールを読んだうえで気になった学生にスカウトを送っているので、あなたに合った企業と出会いやすいのもメリット。
僕のおすすめは、「Offerbox(オファーボックス)![]() 」です。
」です。
企業探しの効率も上がるので内定獲得にもグッと近づけますよ!
グループディスカッションを避けて効率よく内定を獲得したい人は、必ず登録しておきましょう。
1日でもはやく登録することで、より多くのスカウトを獲得できるので早めの行動がおすすめです。
グループディスカッションを避けるのもひとつの手というわけですね!
そのとおり!就活エージェントならマンツーマンでサポートしてもらえるしね。エージェント経由で内定が取れれば、その後にグループディスカッションに参加するときも心に余裕ができるよ。
グループディスカッション前に行うべき5つの対策

では、グループディスカッション前に行うべき対策をお伝えしていきます。
選考前に以下の5つの対策は行っておきましょう。
【グループディスカッション前に行うべき対策】
- 場数を踏んで慣れておく
- グループディスカッションのコツを押さえる
- グループディスカッションで落ちる人の特徴を知る
- クラッシャー対策をしておく
- グループディスカッション関連の本を読む
対策① 場数を踏んで慣れておく
グループディスカッションは、場数を踏んで慣れることが重要です。
役割ごとの立ち回りを頭に入れていても、本番では緊張したり場の空気に飲み込まれ思うように動けません。
知識だけではなく実践練習が必要なのです。
ただ、何度もグループディスカッションに参加するのは非効率的。
そこでおすすめなのが「中小規模の合同説明会」に参加することです。
中小規模の合同説明会とは、数十人の就活生と数社の企業が行う合同説明会のこと。
中小規模の合同説明会では、グループディスカッションが行われることが多いので、練習の場としてはうってつけです。
▼中小規模の合同説明会の様子

また、グループディスカッションの様子をみている人事から、直接スカウトの連絡をもらうこともあります!
グループディスカッションの練習もでき、内定につながるチャンスも得られる。
まさに一石二鳥のイベントなので、ぜひ参加しましょう。
中小規模の合同説明会の中では、「ミーツカンパニー」が圧倒的におすすめです!
僕自身も、このイベントに参加してグループディスカッションの実践力を磨きました。
その結果、グループディスカッションの通過率は100%。
加えて、そこで評価をいただいた2社から内定をもらうことができました!
完全無料で参加できるので、ぜひチェックしてみてください。
【ミーツカンパニーの利用方法】
- 「
ミーツカンパニー公式サイト」にアクセス。
- 「30秒無料エントリー」をクリック。
- 名前や大学など、必要情報を入力。
- 参加希望のイベントを選択。
- 登録と参加予約完了。
なお、その他の練習方法については以下の記事でまとめています。
グループディスカッションの実践練習を積みたい人は、必ず読んでくださいね。
対策② グループディスカッションのコツを押さえる
次に、グループディスカッションのコツを押さえておくことも大切です。
ただやみくもに参加し続けても、通過率が急に上がるなんてことはありません。
僕自身、グループディスカッションが苦手だったので、どうすれば攻略できるのかをめちゃくちゃ研究しました。
その結果、以下の16のコツが重要だとわかったのです。
【グループディスカッションのコツ】
- とにかく場数を踏む
- 評価される能力を把握する
- メンバーと雑談しておく
- タイムキーパーはしない
- 役割ごとの立ち回りを理解しておく
- 時間配分ではバッファを設ける
- まずは課題を具体化する
- 話し合いのゴールを明確化する
- 他のメンバーに共感する
- 発言できていない人をフォローする
- 反論の仕方をマスターしておく
- 論理的思考を意識する
- アイデアを言う場合は理由もセット
- 常に時間を気にかける
- 評価される発表法を把握する
- 経験者の声を聞く
上記のコツを実践したことで、就活中のグループディスカッションは通過率100%でした。
より詳しい解説は以下の記事でまとめています。
確実に通過率がアップするので、グループディスカッション前に読み込んでおいてくださいね!
対策③ グループディスカッションで落ちる人の特徴を知る
次に、グループディスカッションで落ちる原因についても知っておきましょう。
落ちる原因を把握することで対策が立てやすくなり、通過率もアップします。
グループディスカッションで落ちる主な原因は以下の5つです。
【グループディスカッションで落ちる原因】
- 評価ポイントを把握していない
- 議論の流れを意識していない
- 自分の役割を理解できていない
- 企業が「本年度に求める人物像」ではなかった
- まったく話せていない
上記の5つのいずれかに当てはまっていると、グループディスカッションで落ちる可能性が高いです。
原因をふまえて対策した上で、選考に臨む必要があります。
具体的な対策については、以下の記事でかなり詳しくまとめています。
グループディスカッション前に必ず読んでおいてくださいね!
対策④ クラッシャー対策をしておく
クラッシャー対策をしておくこともかなり重要です!
クラッシャーとは、話し合いをめちゃくちゃにする人のこと。
同じグループにクラッシャーがいると、話し合いが進まなかったりグループ全体がマイナス評価を受けてしまう可能性があります。
クラッシャーは主に以下の5つのタイプに分けられます。
【グループディスカッションのクラッシャー5タイプ】
- 自己主張型クラッシャー
- 超否定型クラッシャー
- 仕切り下手型クラッシャー
- アイデア出しすぎ型クラッシャー
- もはや何言っているかわからない型クラッシャー
さまざまなタイプのクラッシャーがいるんですよね。
そして、各タイプごとに対策方法は変わってきます。
各クラッシャーへの対策は、別記事で細かくご紹介しています!
僕も就活生時代にクラッシャーと同じグループになりましたが、対策を取ったことで無事通過できました。
本番にならないと同じグループにクラッシャーがいるかどうかは分からないので、事前に対策は頭に入れておきましょう。
対策⑤ グループディスカッション関連の本を読む
グループディスカッションに関連する本を読むのもおすすめです。
役割ごとの立ち回りの他にも、「論理的思考力」「積極性」「傾聴力」なども必要になってきます。
これらの知識は、グループディスカッション当日だけ発揮しようとしても難しい。
そこで、本を読んで普段から実践して身につけておくことが大事です。
読書に慣れていない人は、すべて読まなくても気になる部分だけ読む形でもOK!
グループディスカッションで役立つ知識を身につけていきましょう。
僕はこれまで1500冊以上もの本を読んできたので、その中からおすすめの本を以下の記事で厳選して紹介しています。
グループディスカッションを控えている就活生は、ぜひ読んでみてください。
どれもかなり重要な対策ですね!
この5つは必ずやっておくべきだよ。とくに、場数を踏んでおくのはかなり重要。「知っている」より「やったことがある」方が確実にうまく立ち回れるからね。
グループディスカッションで企業がみている評価ポイント

グループディスカッションでの人事の評価ポイントを把握しておきましょう。
何を評価しているのかを知ることで、どう立ち回ればいいのかがわかってきます。
そこで実際に、現役の新卒採用の方に聞いたところグループディスカッションでは以下の点を見ているとのことでした。
【採用担当者がグループディスカッションで見ているポイント】
- 自発性、積極性
- 協調性、周りへの気遣い
- コミュニケーション力
- 論理的思考力
- 戦略性
- グループディスカッションに対する姿勢
評価ポイントを把握せずに間違った立ち回りをしてしまうと、マイナス評価につながってしまうこともあります。
以下の記事で、評価ポイントについてより詳しく解説しています。
グループディスカッション前に必ず確認しておいてくださいね!
役割ごとの立ち回りを知っておくのも大切だけど、グループディスカッションを通過するには人事がなにを評価しているかを知っておくことが大事だよ。
グループディスカッションの役割についてよくある質問

最後に、グループディスカッションの役割についてよくある質問と解答を共有しますね!
グループディスカッションを受ける前に気になる点がある人は、ぜひ参考にしてください。
【グループディスカッションの役割についての質問】
- グループディスカッションで「役割なし」はありなのか?
- グループディスカッションでおすすめの役割は?
- 役割分担がうまく進まないときはどうすればいい?
質問① グループディスカッションで役割なしはアリ?
グループディスカッションでは役割なしもOKです。
役割がないことでアイデア出しに注力できますが、僕のおすすめは司会のサポートを行うこと。
たとえば、話が脱線していたら本題に戻したり、時間を決めずに進もうとしたら時間配分を提案するなど、さりげなくサポートしましょう。
役割がなくても上記の行動をとることで、積極性をアピールできます。
役割がないからといって何も発言しないなど、話し合いに参加しないのはNGですよ!
質問② グループディスカッションでおすすめの役割は?
グループディスカッションの役割で僕のおすすめは、「書記」です!
書記は議事録の取り方や、アイデアをまとめるために話し合いの流れを作ることで評価されやすくなります。
【書記の立ち回りのポイント】
- 箇条書きで議事録を取るのではなく樹形図で議事録を取ること。
- 途中で一度まとめの時間を作ること。
この2点を実行すれば、高確率でグループディスカッションを通過することができるようになります。
具体的な書記の立ち回り方については、以下の記事で詳しくまとめているのでこちらを読んでくださいね。
質問③ 役割分担がうまく進まないときはどうすればいい?
役割分担がうまく進まないときもあるでしょう。
役割分担の方法として、まず司会を決めて役割を振っていく方法を先ほど共有しました。
もし、司会を決めるまでにまず時間がかかってしまう場合は、あなたが立候補してください。
司会に苦手意識があったとしても、役割が決まらずグダグダして時間を無駄にしてしまうとそれだけでグループ全体の評価がマイナスになってしまいます。
何もせずにマイナス評価を受けるのはかなりもったいない!
苦手な役割でもチャレンジする方が企業の人事からは評価されます。
司会になったら立候補者がいるかを確認し、いなければあなたがそれぞれの役割を振っていきましょう。
役割が決まらなかったり役割なしになったときも、積極的に動くことが大事ってことですね!
そのとおり!グループディスカッションで一番ダメなのは、何も発言しなかったり誰かがやってくれるだろうと傍観していること。積極的にディスカッションに参加する意欲的な姿勢を見せていこうね!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
グループディスカッションでは役割分担も評価されるので、役割を決めずに進めるのは絶対にNGです。
本記事でお伝えした各役割の立ち回りや評価ポイント、注意点をしっかり頭に入れて本番で動きましょう。
一人の選考ではないからこそ、自分だけをアピールするのではなくグループ全体の評価を上げることが大切ですよ。
また、企業側が役割を指定することもあるので、苦手な役割でも対応できるように準備しておいてください。
グループディスカッションは知識ばかり増やすだけでは意味がありません。
通過率を上げるためにも、中小規模の合同説明会などに参加して場数を踏むのがおすすめですよ。
ちなみに、この記事を読み終わったら「グループディスカッションのテーマ70例【対策法や解答例まで”僕が持つ全知識”を共有!】」も読んでみてください。
グループディスカッションで出題されるテーマについてまとめています。
事前にどんなテーマが出題されるのかを把握しておくことで、本番でどう話し合いを進めればいいのかのイメージを掴みやすくなりますよ。
こちらもグループディスカッション前にぜひ読み込んでおいてくださいね!
では最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう。
【本記事の要点まとめ】
- グループディスカッションの役割は主に「司会」「書記」「タイムキーパー」「発表者」「役割なし」の5つ。
- 役割ごとに評価されるポイントや注意点は違う。
- 役割分担は、まず司会を決めて立候補or指名でサッと決めていく。
- 企業側から役割を指名されることもあるので、どの役割もできるように準備しておく。
- 就活エージェント経由の選考でグループディスカッションを避けるのも一つの方法。
- グループディスカッション前に「場数を踏む」「コツを押さえる」「落ちる原因を把握する」「クラッシャー対策をする」「関連書籍を読む」といった5つの対策を行っておくべき。







