
こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1500以上の就活マンです。
就活生の中には、グループディスカッションに苦手意識を持っている人も意外と多いです。
グループディスカッション対策情報って意外と少ないので、困りますよね。
対策をする上で、重要なのは”グループディスカッションに落ちる原因”を知ること。
原因に沿った改善策などを実践すれば、通過率は格段に上がります。
そこで本記事では、まずグループディスカッションに落ちる原因を共有します。
その上で、原因に沿った攻略法も共有するので、ぜひ参考にしながら実践してみてください!
面接などと違って模擬対策にも人数がいるので、対策しづらいんですよね。
そうだよね。まずは落ちる原因を知った上で、一人でもできる対策法や実践的な攻略法まで踏み込んで解説していくよ!
- グループディスカッションで落ちる割合
- グループディスカッションで落ちる5つの原因
- グループディスカッションで落ちる人の特徴
- グループディスカッションを通過するための攻略法【実践編】
- グループディスカッションを通過するための攻略法【座学編】
- 本記事の要点まとめ
\就活攻略論から求人サイトが生まれました!/
(僕が就活生の時に感じていた「働きやすい条件の良い企業だけを丁寧に紹介してくれるサイトはないのかな」を形にした求人サイトです!)


グループディスカッションで落ちる割合
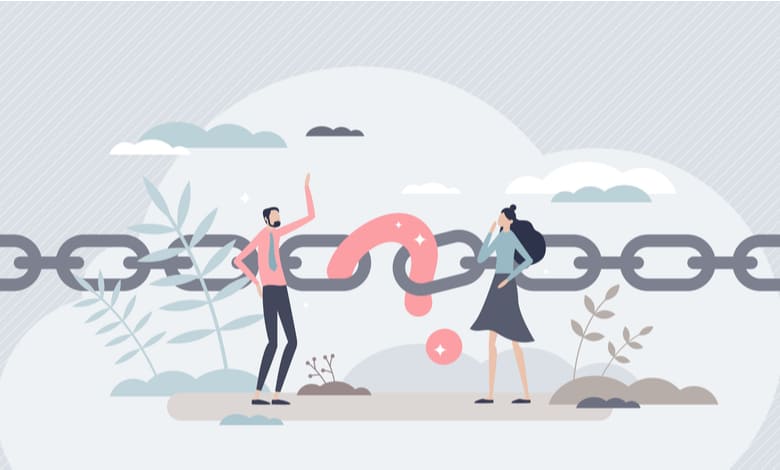
就活生から先日、グループディスカッションに関してこんな質問を頂きました。
「グループディスカッションで落ちる割合はどのぐらいでしょうか?」
企業ごとに倍率が異なるため、明確に◯%ですと回答することは当然できません。
僕が入社した大手食品企業を例に取って話すと、全体の倍率は800倍程度です。
その中でもグループディスカッションでの通過倍率は100〜200倍とのことでした。
仮に200倍だとすると、全選考の中の25%(200/800)の重要度があるということになります。
つまりグループディスカッションには、エントリーシートや面接と同程度の重要度があるということです。
グループディスカッションは、話し合いする相手が同じ就活生なので個人の「素」が出やすい選考です。
更には短い時間でその人の持つ能力の特徴を把握することができます。
よって企業はグループディスカッションに重きを置いているので、落ちる割合はその分高いと言えるでしょう。
選考の中でもかなりの重要度があるんですね!
そうだよ。だから、ESや面接と同じようにしっかり対策をして臨むべきなんだ!
グループディスカッションで落ちる5つの原因

では本題である”グループディスカッションで落ちる原因”をご紹介していきます。
原因を把握していないまま行う対策は無意味です。
まずは自分の課題を把握することで、効果的な対策が可能になるので、原因は誰しもが知っておくべきことです。
グループディスカッションで落ちてしまう主な原因は、以下の5つです。
【グループディスカッションで落ちる原因】
- 評価ポイントを把握していない
- 議論の流れを意識していない
- 自分の役割を理解できていない
- 企業が「本年度に求める人物像」ではなかった
- まったく話せていない
落ちる原因① 評価ポイントを把握していない
グループディスカッションの評価ポイントを把握していないと、落ちてしまうことがあります。
企業がグループディスカッションを通して何をみているかを知らなければ、間違ったアピールをしてしまう可能性があるからです。
たとえば、企業が協調性をみているのにも関わらず、一人だけ発言しまくって目立とうとしてしまうとNG。
自分では頑張ってアピールしているつもりでも、逆にマイナス評価につながってしまうのです。
グループディスカッションの評価ポイントは、以下の5つだと僕は考えています。
【グループディスカッションの評価ポイント】
- 「段取り力」
- 「積極性」
- 「協調性」
- 「本質理解力」
- 「発想力」
これらはグループディスカッションにおける役割でも変わってきます。
各評価ポイントについては「グループディスカッションで評価される5ポイント」で詳しく解説しています。
グループディスカッションの予定がある就活生は必ず目を通しておいてくださいね!
落ちる原因② 議論の流れを意識していない
議論の流れを意識していないのも落ちる原因になります。
企業ごとに細かい流れは違っても、グループディスカッションの基本的な流れは一緒です。
グループディスカッションの一般的な流れを知らなければ、話し合いを止めてしまったり制限時間をオーバーしてしまうかもしれません。
そうすると、あなただけでなくグループ全員に迷惑がかかります。
必ずグループディスカッションの流れは把握しておきましょう。
落ちる原因③ 自分の役割を理解できていない
自分の役割を理解できていないことも、落ちる原因の一つです。
グループディスカッションでは司会や書記、タイムキーパーなど、一人ひとりの役割を決めます。
自分の役割を理解せずに参加していると、グループの話し合いはうまく進みません。
たとえば、タイムキーパーの役割を忘れていたりすると、「もう時間がない…!まだ意見がまとまっていないのに」なんてことになりかねません。
役割を理解しないで参加していると「入社後も自分の仕事を理解しないまま、なんとなく働くのかな」とマイナスイメージを与えてしまう可能性があります。
どの役割につくかばかりでなく「自分は何をすべき役割なのか」を理解しておきましょう。
落ちる原因④ 企業が「本年度に求める人物像」ではなかった
企業が求める人物像と合わなかった場合も落ちます。
これは、ただ単にその企業が求めている能力や人物像とマッチしなかったというだけのこと。
グループディスカッションで司会を務めて、バリバリに発言している人は絶対に通過すると思っている人は多いのではないでしょうか?
しかし、それは違います。
受けた企業が求める能力が「深い思考力やアイデアの発想力」だったら、普通に落ちるからです。
「バリバリに司会していた彼」よりも、「ずっと考え込んで一言だけ素晴らしい新規アイデアをぶち込んだ他の就活生」が評価されるかもしれません。
多くの学生が「就活には正解がある」と思い込みがちですが、就活においてこの考えは捨ててください。
なぜなら企業ごとに求めるものが違うので、どれだけ優秀な学生でもすべての企業から内定を取れるわけではないからです。
どうしても選考を通過したい!と強く志望する企業がある人は、事前にその企業が求める人物像を把握しておきましょう。
落ちる原因⑤ まったく話せていない
グループディスカッションでまったく話せていないと、高確率で落ちます。
いわゆる話し合いに参加できなかった。
空気のような存在になってしまった場合ですね。
考えてみればわかることですが、「とにかく大人しく、会話ができない人」を求める企業はグループディスカッションを選考に取り入れません。
グループディスカッションをわざわざ選考で取り入れるということは、企業は何かしらの能力を判定したいという思惑があります。
だからこそ「あー、全く参加できなかったなぁ」で終わるのは絶対にNGです。
グループディスカッションを受けずに内定を獲得する方法
ここまでグループディスカッションに落ちる原因や共通する特徴を解説しました。
ただ、どうしてもグループディスカッションが苦手で、できれば受けずに内定を獲得したい人もいるかと思います。
そんな人におすすめなのが、就活サイトをうまく活用してグループディスカッションを避ける方法です!
グループディスカッションをできるだけ受けたくない人は、「逆求人サイト」と「就活エージェント」を活用しましょう。
逆求人サイトは、プロフィールを登録しておくとあなたに興味をもった企業からスカウトが届くサイトです。
スカウトが届いた企業の選考は、いきなり個人面接からはじまることも少なくありません。
就活エージェントは、専任のサポーターが企業紹介から選考対策までサポートしてくれるサービスのこと。
エージェント経由の選考は、基本的には個別に選考が進んでいきます。
つまり、グループディスカッションが課されることはほとんどありません。
よって、グループディスカッションをどうしても避けたい方は、逆求人サイトと就活エージェントをぜひ活用してくださいね!
僕のおすすめは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「
」と「ミーツカンパニー就活サポート」ですね。
これまで200以上の就活サイトを見てきましたが、ダントツでおすすめできるサービスです。
グループディスカッションを避けられる可能性があるだけでなく、内定獲得にも有効ですよ!
もちろん2サイトとも無料で利用できるので、まだ使ったことがない人は登録してみてくださいね。
▼オファーボックスで内定を獲得した人の声
内定2社ゲット〜オファーボックスいいな
— 一盃口@24卒 (@CCKDck5dFMSUVO3) December 12, 2022
オファボで内定決めた24卒です。
— えびかに (@abcanichang) September 11, 2023
お祝いギフト申請せずにそのままいたら、内定先から連絡きて『お祝いギフトくれるらしいので是非確認して下さいね』ってきたぁ〜🌟🌟御社sukiです。
なお、以下の記事では就活に役立つ有益なサイトを6つまとめています。
僕がいま就活生だとしたら絶対に使うサイトだけを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
あえてグループディスカッションを避けるのも1つの方法ですね。
これも戦略の1つだよね。エージェント経由で内定を獲得できれば、その後の選考は精神的な余裕も生まれて、グループディスカッションで緊張しなくなる人もいるからね!
グループディスカッションで落ちる人の特徴

僕は毎年多くの就活生を見てきましたが、グループディスカッションに落ちる人には共通する特徴があるんですよね。
原因とともに、この特徴についても把握しておけば、対策の効果が高まりますよ。
【グループディスカッションで落ちる人の特徴】
- 周りの意見を全く聞かない
- 論点がズレている
- 他人の批判ばかり言う
- 人の意見に同調してばかりいる
落ちる人の特徴① 周りの意見を全く聞かない人
まずグループにいると困るのが、周りの意見を全く聞かないタイプの人ですね。
自分の意見が絶対に正しいとして、他の人が別の案や意見を言っても全く曲げようとしません。
もちろんこういうタイプを評価する企業も一定数いることは確かです。
周りの意見を聞かないで突っ走ることは行動力が高いとも言えますからね。
ですが、グループディスカッションを実施する企業の多くは「協調性」を重視している企業が多いので、落ちやすい傾向にあります。
よって改善策を用意しました。
【改善策】
他人が何か言ったら、「なるほど!そういう考えもあるのですね!」と言いまくる。
(自分の意見を信じ切っていても問題ありません。この発言を取り入れるだけで、一気に協調性が増します。)
落ちる人の特徴② 論点がズレている人
次によく落ちるのは、論点がズレている人ですね。
論点がズレているとはかなりオブラートに包んだ言い方ですが、要するに「お前何言ってるの?」という意見ばかり言う人です。
例えば「お店Aの売上を2倍にしてください」というテーマを与えられ、皆が建設的に意見を交わしている中で、いきなり「ユーチューバーを採用しよう!」と発言したりします。
根拠が明確だったら良いのですが、思ったことを口にするだけの場合も多いです。
もし自分がよく周りの友人から「お前何言っているの?」や「言ってることがよくわからない」と言われる人は要注意。
【改善策】
おとなしく「書記」をする。
落ちる人の特徴③ 他人の批判ばかり言う人
“代案なく”他人の意見に反対ばかりする人は確実に落ちます。
“代案なく”という部分がポイント!
他人の意見をとにかく批判するタイプの人は、批判が口から溢れるほど出てきますが、その理由を聞くと「なんとなく」と言います。
「うーん、なんとなくそれは違うかな」というのが口癖ですね。
改善策を提供するので、これを徹底しましょう。
でなければ問答無用でグループディスカッションでは落ちます。
【改善策】
批判する場合は代案を用意する。代案が用意できないなら批判しない。
落ちる人の特徴④ 人の意見に同調してばかりの人
周りの意見に同調してばかりの人も落ちてしまう可能性が高いです。
グループディスカッションにおいて人の意見をきちんと聞くことは大切ですが、同じように自分の意見を伝えることもまた大切なこと。
人に合わせて自分の意見を変えたり同調してばかりだと、「自分の頭では何も考えない人」と思われてしまいます。
【改善策】
場数を踏んで意見をいう練習を積む。
ちなみに、上記のようなマイナス評価につながる立ち回りをする人のことを「クラッシャー」と呼びます。
クラッシャーと同じグループになると、あなたまでマイナス評価を受けて落ちてしまう可能性も…。
以下の記事でクラッシャー対策について詳しくまとめています。
万が一に備えて、事前に目を通しておいてくださいね!
たしかに、とにかく批判していたり逆に同調して自分の意見を言わないでいると印象はマイナスですよね…。
ディスカッションができない人とみなされてしまうからね。慣れるためにも次の章で紹介する実践的な攻略法を試してみてほしい!
グループディスカッションを通過するための攻略法【実践編】

ここからは具体的な攻略法について解説したいと思います。
僕自身、グループディスカッションがはじめから得意だったわけではありません。
大学1年時に参加したときには「自己主張が強すぎる!」と言われてへこんだ思い出もあります…。w
しかし、そこから研究し尽くして結果的に就活中のグループディスカッション通過率は100%でした。
そんな僕が考え抜いた攻略法を「実践編」と「座学編」に分けてご紹介していきます。
グループディスカッションに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
ではまず実践編から解説していきましょう!
【グループディスカッション攻略法(実践編)】
- とにかく場数を踏んで練習する
- 友達と一緒に練習する
- すぐにフィードバックをもらう
実践編① とにかく場数を踏んで練習する
グループディスカッションは、「場数を踏む」ことが一番の練習になります。
知識を学ぶことも大切ですが、いざ実際に参加すると思っていたようにうまくできないもの。
一度経験するだけでも、立ち回りや意見のまとめ方を肌で感じられます。
しかし、選考のグループディスカッションに何度も参加して場数を踏むのは非効率。
そこで僕がおすすめしているのが「中小規模の合同説明会に参加すること」です。
中小規模の合同説明会とは、数十人の就活生と数社の企業で行われる会社説明会のこと。
▼中小規模の合同説明会の様子

大規模なものと違い、中小規模の合同説明会ではグループディスカッションが行われることが多いんです。
つまり、練習の場としてはうってつけなわけです。
また、グループディスカッションの様子をみて気になった学生には、企業の人事から直接スカウトの連絡が来ることもあります。
まさに一石二鳥のイベントなので、ぜひ参加してください!
中小規模の合同説明会の中で僕が圧倒的におすすめするのは「ミーツカンパニー」です。
僕自身、このイベントに参加してグループディスカッションの実践力を磨きました。
その結果、グループディスカッションで落ちたことはありません。
加えて、そこで評価をいただいた2社からも内定をもらうことができました!
完全無料で利用できるので、ぜひ一度参加することをおすすめします。
なお、その他の練習方法については以下の記事でまとめています。
グループディスカッションを絶対に通過したい就活生は、必ず参加して経験を積んでおきましょう!
実践編② 友達と一緒に練習する
友達と一緒に練習するのも有効な方法です。
グループディスカッションの練習は一人じゃできません。
友達同士であれば何度でも練習できますし、率直に意見を言い合えますからね。
ただし仲良しだからといってゆるい雰囲気になってしまうのには注意しましょう。
実際の選考と同じようにテーマを決め、時間を測りながら真剣にディスカッションしてみてください。
できれば4人以上で集まり、それぞれ役割をローテーションしながら練習できると良いでしょう。
実践編③ すぐにフィードバックをもらう
本番後にフィードバックをもらうのも、有益な方法の一つです。
企業によってはグループディスカッションが終わってから、良かったところや改善したほうがいいところをフィードバックしてもらえます。
実際に行った後のフィードバックなので、次の選考で確実に役立ちます。
自分の立ち回りだけでなくグループ全体の評価を聞けるといいですね!
怖い気持ちもあるかもしれませんが、より通過率を高めていくためにもアドバイスをもらえる機会があれば必ず聞いておきましょう。
他の選考対策と違って、自分ひとりで練習するのは難しいですよね。
知識を入れるのも大事だけど、グループディスカッションではとにかく実践で練習することが大事だよ!
グループディスカッションを通過するための攻略法【座学編】

では次にグループディスカッションの攻略法【座学編】について解説していきます!
選考前に以下の対策は必ず行っておきましょう。
【グループディスカッション攻略法(座学編)】
- 全体の流れを把握しておく
- 各役割について理解する
- よく出るテーマを把握しておく
- 対策におすすめの本を読む
座学編① 全体の流れを把握しておく
まずグループディスカッション全体の流れを把握しておくことが大切です。
流れを知らないと、話し合いを止めてしまったり制限時間に間に合わずに落ちる原因になってしまいます。
そうならないためにも、前提知識として全体の流れはしっかり把握しておきましょう。
グループディスカッションは主に、以下の流れで進みます。
【グループディスカッションの流れ】
- 役割の決定
- 時間配分の決定
- 課題の本質や前提決め
- グループでの目標設定
- 話し合い
- 結論まとめ
- 発表
議論の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
各フェーズのポイントや会話形式のディスカッションの例もご紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね!
座学編② 各役割について理解する
各役割についても理解しておきましょう。
グループディスカッションでの役割を理解していないと、本番でうまく立ち回れずマイナス評価を受けてしまいます。
グループディスカッションでは、基本的に以下の4つの役割を決めておけばOKです。
【グループディスカッションでの役割】
司会:話し合いの司会進行を行う
書記:議事録を書く
タイムキーパー:時間を管理する
発表者:結論を発表する
最低限、上記の4つは決めましょう。
グループディスカッションでは役割分担の工程もチェックされているので、役割を決めずに進めるのは絶対にNGです。
役割分担の具体的な方法については、別記事にてまとめています。
役割ごとにアピールできる能力や注意点も解説しているので、事前にチェックしておいてくださいね!
座学編③ よく出るテーマを把握しておく
グループディスカッションでよく出るテーマを把握しておくことも重要です。
どんなテーマが出るのかを事前に知っておくことで、対策もしやすくなりますからね。
もちろん企業ごとに出されるテーマはちがいます。
ただ、グループディスカッションでよく出るテーマは大きく以下の4つにわけられるんです。
【グループディスカッションのテーマ】
- 課題解決型のテーマ
└スーパーの売上を2倍にするための案を考えてください
自社の商品の再購入率が低いことを改善してください - 選択肢型のテーマ
└「お金」か「友情」どちらの方が大切か?
企業で大事なのは「売上」か「商品価値」か? - 討論型のテーマ
└テレビCMとYouTube広告はどちらが有効か?
資本主義か社会主義どちらの国が幸せか? - 自由発想型のテーマ
└10年後の日本はどうなっている?
未来に行けるとしたら未来で何をする?
種類ごとにテーマの例も挙げました。
どの種類にも対応できるように、よく出るテーマと回答のコツを把握しておきましょう。
それぞれの種類によって回答のコツはあります。
ただ、すべてのテーマに共通するのは「出した結論に対する理由をはっきりと答えられるか」が重要だということ。
以下の記事で、種類ごとによく出るテーマの例と回答のコツを解説しています。
注意点もまとめているので、とくにこれから初めてのグループディスカッションに臨む人は必読です!
座学編④ 対策におすすめの本を読む
グループディスカッションに必要な知識を得られる本を読むのもおすすめです。
グループディスカッションでは、「論理的思考力」「積極性」「傾聴力」が必要になります。
それぞれの知識がまとめられた本を読むことで、グループディスカッションだけでなくその後の人生にも役立ちますよ。
読書に慣れていない人は全て読もうとせず、まずは気になる章だけ読んでみるのがおすすめです!
これまで1500冊以上もの本を読んできた僕が厳選したグループディスカッションに役立つ書籍を以下の記事で紹介しています。
グループディスカッションを控えている就活生は、ぜひ読んでみてください!
他人と一緒に行う選考だからこそ、事前に最低限の知識は入れておくべきですね!
そのとおり!特に本を読むのはグループディスカッションの知識だけじゃなく、その後の人生にも役立つ知識が得られるからおすすめだよ!
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
グループディスカッションの対策は、面接などに比べるとどうしても優先度が下げられがち。
しかし、通過することができなければ面接さえ受けられません。
考え方を変えれば、しっかりと対策を行うことで他の就活生と大きく差別化できます。
今回ご紹介したグループディスカッションで落ちる原因と落ちる人の特徴をふまえた上で、しっかりと事前に練習を行いましょう。
ちなみにこの記事を読み終わったら「グループディスカッション対策完全版【9ステップで完了!】」も読んでみてください。
落ちる原因に限らず、グループディスカッションの対策について、僕が持ってるノウハウを全てこの記事にまとめています。
誰もが嫌がる選考だからこそ、得意にすれば大きな差別化に繋がるのがグループディスカッションです。
この記事も合わせて参考にしていただければ、かなり実力がつきますよ!
では最後に本記事の要点をまとめて終わりましょう。
【本記事の要点まとめ】
- グループディスカッションは、面接やESと同じくらい重要な選考のひとつ。
- グループディスカッションで落ちる原因は「評価ポイントを把握していない」「議論の流れを意識していない」「自分の役割を理解できていない」「企業が求める人物像ではなかった」「まったく話せていない」の5つ。
- グループディスカッションに落ちやすい人の特徴として「周りの意見を聞かない」「論点がズレている」「批判ばかり言う」「人の意見に同調してばかり」などが共通する。
- グループディスカッションを攻略するには、知識だけでなく実践練習が重要であり、中小規模の合同説明会に参加するのがおすすめ。









