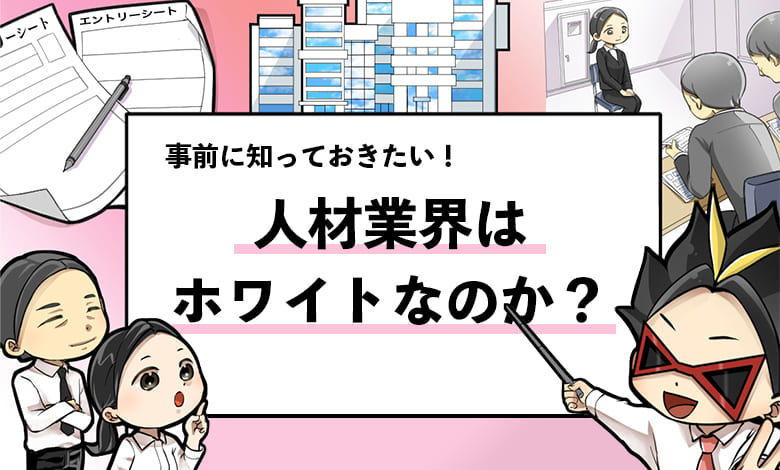
【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
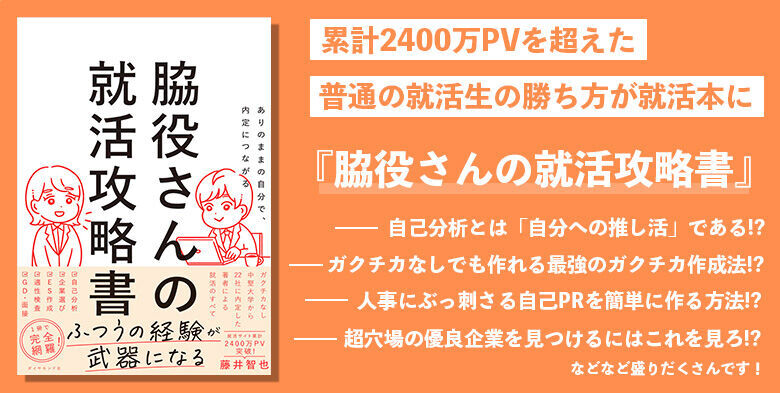
それでは本題に入っていきますね!
「人材業界へ就職したいけど、できればホワイト企業に勤めたい!」
「人材業界に興味があるけど、そもそも業界としてホワイトなの?」
そんな悩みを持っている人も少なくないと思います。
人材業界は「営業がきつい」「激務」といったイメージを持っている人も多いでしょう。
ただし噂だけで、ホワイトかブラックかを判断するのは要注意!
噂だけで判断すると、あなたに合う企業を除外してしまう可能性もありますからね。
今回は「人材業界のホワイト企業」や「そもそも人材業界はホワイトなのか?」を解説していきます。
人材業界に興味のある人は、ぜひ最後まで読んでください!
人材業界の企業って、ホワイト企業とブラック企業がはっきり分かれるイメージがありますね!
そうだね。人材業界は儲かっている企業と儲かっていない企業もはっきり分かれているから、企業によって労働条件が大きく異なる。
だからこそ人材業界を志望している場合は、1社ずつの企業分析を徹底する必要があるよ!
- 人材業界のホワイト企業ランキングTOP5
- 人材業界はホワイト業界か?|労働条件編
- 人材業界がブラックと思われている理由
- 人材業界のホワイト企業を見極める方法
- 人材業界の種類
- 人材業界のやりがい
- 人材業界の将来性・今後の展望【4選】
- 【補足】人材業界はやめとけと言われる理由
- 本記事の要点まとめ
人材業界のホワイト企業ランキングTOP5

では、人材業界のホワイト企業ランキングを紹介します。
ランキングは、求人情報サイトであるキャリコネ が実施した「人材サービス業界の“ストレス度の低い企業”ランキング」を参考にしています。
ストレス度の低さで、高い評価を受けていたのは次の5社です。
【ストレス度の低い人材企業5社】
- 株式会社リクルートスタッフィング
- パーソルテンプスタッフ株式会社
- 株式会社パソナ
- 株式会社スタッフサービス・ホールディングス
- パーソナルキャリア株式会社
1位:株式会社リクルートスタッフィング
株式会社リクルートスタッフィングは、リクルートホールディングスグループにある人材紹介・派遣サービス企業です。
働く人の「らしさ」を活かすために、個人が活躍できる企業を紹介しています。
そんなリクルートスタッフィングは、2013年から働き方改革に尽力してきました。
とくに注目を集めているのが、社員の生産性を重視した「スマートワーク」です。
「スマートワーク」で、年間労働時間の上限を設定し休日出勤や残業を大幅に削減させたのです。
2位:パーソルテンプスタッフ株式会社
パーソルテンプスタッフ株式会社は、パーソルグループ傘下の企業です。
「はたらいて、笑おう」をコンセプトに、幅広い業種の人材派遣を行なっています。
育児や介護などで、はたらく時間・場所に制約のある人を支援する福利厚生があるのが特徴。
また時短勤務に柔軟に対応しており、ダイバーシティ営業部では9時〜16時までの時短営業をしています。
さらに残業規制が徹底され、22時までにすべてのPCがシャットダウンされるようになっています。
3位:株式会社パソナ
株式会社パソナは、「誰もが自由に好きな仕事を選択でき、働く機会を得られること」を目指して、人材派遣や人事コンサルティングを手がけています。
パソナでは、「リンクワーク」という時間や場所に縛られない柔軟な働き方を推進されています。
またパソナ自体が、介護や子育て支援、家事代行サービスなどの福利厚生サービスを提供している企業でもあります。
4位:株式会社スタッフサービス・ホールディングス
株式会社スタッフサービス・ホールディングスは、「個人や企業、社会にチャンスを提供する」ことを理念に事務職やITエンジニアなどの人材派遣をしています。
求人情報サイトの「オー人事net」を運営していることでも有名です。
スタッフサービスは、社員の生産性向上のため休日出勤や残業を大幅に削減しています。
2017年のオフィス移転を機に、誰でもすぐ使えるオープンミーティングスペースを導入するなど、社員の仕事効率が上がる環境づくりが進められています。
5位:パーソルキャリア株式会社
パーソルキャリア株式会社は、パーソルテンプスタッフと同じくパーソルグループ傘下の企業です。
「doda」をはじめ、人材紹介や採用支援サービスに取り組んでいます。
パーソルキャリアでは、2017年から服装自由にし、風通しの良い社風となっています。
また土日・祝日の勤務もほぼなく、リモートワークの採用や社内イベントの導入などに積極的です。
人材業界はホワイト業界か?|労働条件編

具体的な数値を元に、人材業界がホワイトかどうかを確認していきましょう。
ここで確認するのは、次の5つです。
【今回のチェック項目】
- 離職率
- 勤続年数
- 平均年収
- 残業時間
- 有給取得日数
①離職率
「離職率」が高く「勤続年数」が短い企業は、やめていく人が多いと予想できます。
よって、ブラック企業の可能性が高いです。
厚生労働省が発表した調査によると、21卒の3年以内の離職率は34.9%でした。
中でも、人材業界が含まれる「サービス業」の3年以内離職率は40.3%
(人材業界以外の業界も含まれているため、あくまで参考数値ですが)

引用:厚生労働省「新規大卒就職者の産業別就職後3年以内の離職率」
すべての業界の平均離職率とくらべても、大きな差はありません。
よって、人材業界はすぐに人が辞めていくとは言えないとわかりますね。
②勤続年数
厚生労働省による令和6年の「勤労統計調査特別調査」によると、全体の平均勤続年数は13.7年でした。
人材業界の平均勤続年数については、求人サイトの「ブンナビ」を参考にします。
ブンナビで、人材業界の企業(職業紹介・人材派遣のみ)の平均勤続年数を高い順に並べると、画像のような結果になりました。

最も平均勤続年数の長い株式会社フルキャストホールディングスでも10.3年。
全体平均の13.7年よりも短いですね。
よって、人材業界は平均よりも“入れ替わりの激しい業界”であることがわかりました。
③平均年収
給与が低い場合も、社員への待遇がよくないということでブラックと考えられます。
国税庁の「令和5年民間給与実態統計調査」によると、国民の平均年収は460万円です。
人材業界の平均年収も、「ブンナビ」で確認してみましょう。
「職業紹介・人材派遣」企業を平均年収の高い順に並べると、次のようになっています。


9社の平均年収が掲載されていますが、総じて平均年収よりも高いのがわかりますね。
また人材広告の最大手である株式会社リクルートホールディングスの平均年収は、約1,138万円と高額です。
これらのデータから人材業界の給与は、他の業界に比べて高いと判断できます。
(ですが、この給料に関してはピンキリです。
儲かっている人材企業は高くても儲かっていない人材企業は本当に低いので、一概には言えないことを補足しておきます!)
④残業時間
ワークライフバランスの重要性が叫ばれている昨今の日本において、残業時間の長さはホワイトかどうかを図る重要な要素となります。
人材業界の残業時間を「ブンナビ」で確認すると、次の7社しか回答がありませんでした。


厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、全国の平均残業時間は10時間となっています。
ブンナビの回答企業数が少ないため、一概には言えませんが、平均と比べると人材業界は少し残業時間が多い傾向にあると考えられます。
⑤有給取得日数
有給取得日数の多さは、企業の働く環境をはかるひとつの指標となるでしょう。
人材業界の有給取得日数も「ブンナビ」で調べました。
結果は以下のとおり。


残業時間と同じように、ほとんどの企業が回答なしで、回答があったのが9社でした。
最も有給取得日数が多かったのは、パソナグループで11日です。
ただ厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」には、日本の平均有給取得日数が10.9日とあります。
人材業界の有給取得日数は平均よりもやや少ないことがわかります。
【総評】人材業界はホワイトともブラックとも言い切れない
以上の結果をまとめると、次のようになります。
【今回調査した結果】
- 離職率⇒ 平均と同じ
- 勤続年数 ⇒ 平均よりやや悪い
- 平均年収 ⇒ 平均より良い
- 残業時間 ⇒ 平均と同じ
- 有給取得日数 ⇒ 平均よりやや悪い
調査の結果、人材業界はほかの業界に比べ、勤続年数は短い傾向にあるものの離職率は平均と同じ程度でした。
給与の待遇は平均よりも優れています。
また残業時間や有給取得日数の水準は、平均を大きく下回っているわけではありません。
そのため、現時点では人材業界をホワイトと判断できませんが、ブラックとも言い切れません。
ただホワイトかどうかは、企業によっても異なることには注意してください。
人材業界を志望している人は、ブラック企業かホワイト企業かを見極める力を養うことが大事です。
「【ホワイト企業の特徴15選】絶対にチェックすべき項目を解説! 」でホワイト企業の特徴をまとめています。
ブラック企業を避けて、ホワイトな人材会社を目指す人は1度目を通しておいてくださいね。
人材業界のホワイト企業を効率よく見つける方法!
人材業界を志望している人は、ホワイトな企業を見つけられるかどうかが重要です。
そもそも人によって、「どんな企業をホワイトと感じるか」はちがいます。
休みが取れて残業も少なく、ワークライフバランスが取れる会社をホワイトだと思う人もいるでしょう。
一方で、残業が多少あってもがんばり次第で若いうちからどんどん昇格していける会社をホワイトだと感じる人もいます。
よって、大事なのは「自分に合うホワイト企業を見つけられるか」なのです!
あなたに合うホワイト企業を見つけるのに効果的なのは、”逆求人サイト”と”就活エージェント”を活用する方法。
逆求人サイトはプロフィールを登録しておけば企業からスカウトが届くので、気になる企業の選考だけ進めばOKです。
就活エージェントは、面談でどんな企業がいいか条件を伝えると、それに合う求人を持ってきてくれます。
どちらも利用することで、自分で企業を探す手間を省けるのが大きなメリットです!
僕はこれまで200以上の就活サービスを見てきましたが、中でも「キミスカ」と「ホワイト企業ナビ」は利用必須。
人材業界の中でも自分に合うホワイト企業を効率よく見つけたい人は、利用してみてくださいね!

なお、ホワイト企業の内定を獲得するのに有益な就活サイトを別記事でまとめました。
僕がいま就活生だったら絶対にこれを使う!という6サイトだけを厳選したので、ぜひ参考にしてください。
人材業界は会社ごとに、残業時間も給料も本当に大きな違いがあることが分かりますね。
そうなんだよ!だから一概に「人材業界はホワイト」とは言えない。ちなみによく「人材業界はブラックだ!」と言われることが多いから、その点を次の章で解説していこうか。
人材業界がブラックと思われている理由

本記事では人材業界はホワイトとともブラックとも言い切れないと結論づけました。
とはいえ、なかには「人材業界がブラックだ」と思っている方もいます。
その理由として次の3つが挙げられます。
【人材業界がブラックだと言われる理由】
- 営業が多いから
- 労働時間が長くなりやすいから
- 会社によって給料が大きく異なるから
理由① 営業が多いから
人材業界は、営業が多いです。
なぜなら、優秀な人材を確保したいのは、ほぼすべての企業に共通しているからです。
全国にある、ほぼすべての企業が人材業界の顧客になります。
すると必然的に、業界全体として営業が多くなります。
世間一般では、「営業=きつい仕事」というイメージがあるのは否定できません。
そのため、人材業界がブラックだと思われているのです。
理由② 労働時間が長くなりやすいから
人材業界は、労働時間が長いと見なされがちです。
というのも求職者との面談が、勤務時間終了後の夜遅くになりやすいからです。
人材業界では、求職者との面談は大切な業務です。
働きながら仕事を探している求職者が多く、求職者の仕事終わりの面談となる傾向にあります。
そのため、人材業界の就業時間は夕方以降にも続きます。
そのことから、人材業界は労働時間が長いブラックな業界だと思われるのです。
理由③ 会社によって給料が大きく異なるから
人材業界は企業ごとに儲けが本当に違います。
大手のリクルートやパーソル、パソナは知名度がゆえに圧倒的な集客力を誇り、その分利益が大きい。
一方で人材紹介事業を展開する中小企業は本当に多く、そのほとんどの企業が知名度がないので集客に困っています。
「集客に困っている=営業が大変、儲からないので給料が低い」という状況になりやすいので、個人的には中小の人材企業はおすすめ度が低いと考えています。
なるほど!こうした特徴があるから人材業界はブラックだと言われやすいんですよね。
そのとおり。◯◯業界はブラックだと安易に考えるのではなく、その裏にある仕組みや原因に目を向けることが重要だよ!
人材業界のホワイト企業を見極める方法

検討している企業が、ホワイトかどうかを見極めるのは簡単ではありません。
1社1社、丁寧に確認していく必要があります。
そこで僕が行なっていた、ホワイト企業かどうかを見極める次の3つの方法を紹介します。
【人材業界のホワイト企業を見極める方法】
- OB・OG訪問などで聞いてみる
- 実際に勤めている社員の話を聞く
- 口コミサイトを確認する
方法① OB・OG訪問などで聞いてみる
ホワイトかどうかを見極める基本は、OB・OG訪問で話を聞くことです。
相手が高校や大学の先輩であるため、話を聞きやすいでしょう。
また待ち合わせ時間や、相手の顔色、服装などから、仕事の忙しさや疲労度などを見て取れるので、さりげなく確認するのもおすすめです。
OB・OG訪問をする上での注意点は、次の3点です。
【OB・OG訪問の注意点】
- 聞きたいことは事前にメモする
- 質問攻めにするより、会話の脈略を大切に自然な流れで質問する
- OB・OG訪問が採用活動の一環である会社では、ネガティブ情報を聞き出せない恐れがある
OB・OGには、自分の話したいことや話したいペースがあります。
できるだけ、会話のペースを合わせることが大切です。
うまく打ち解けられれば、自然と本音を話してくれることがあります。
方法② 実際に勤めている社員の話を聞く
行きたい企業にOB・OGがいない場合や、情報を聞き出し切れなかった場合は、社員の話を聞くのが有効です。
実際に志望企業で働いている人の生の声は、貴重な情報源になります。
社員の方に話を聞くには、以下の方法がおすすめです。
【社員に話を聞く方法】
- 人事に紹介してもらう
- OB・OGに紹介してもらう
- 内定者懇親会などに積極的に参加する
求職者や内定者は、企業にとって将来の活躍を期待する貴重な存在です。
社員の話を聞きたいという要望を、ないがしろにすることはほぼありません。
方法③ 口コミサイトを確認する
OB・OGや社員も、企業に所属している人であるため、得られた情報が客観性に乏しい恐れがあります。
そこで、口コミサイトの活用をおすすめします。
というのも多くの口コミサイトには、退職者の声が掲載されていて、他の企業と比較した上での意見が多数あるからです。
OB・OGや社員の話と、口コミサイトの内容を照らし合わせれば、自分なりの基準でより適正にホワイトかどうかを判断できるでしょう。
人材業界の種類

ここで、人材業界についての基礎知識を解説していきます。
人材業界とは「人と企業をつなぐサービスを展開する業界」のこと。
優秀な社員を増やしたい企業と、自分に合った企業を見つけたい求職者を結びつけるのが人材業界の役割です。
人材業界にはビジネスモデルに応じて、大きく次の4つの事業があります。
【人材業界の種類】
- 人材紹介
- 人材派遣
- 人材広告
- 人材コンサルティング
人材紹介
人材紹介とは、求職者と面談して、企業に紹介する事業のことです。
人材を紹介した企業から、成果報酬を受け取ります。
人材紹介を事業とする企業には、次のようなものがあります。
人材派遣
人材派遣は、自社に登録している人材を、企業に派遣して労働サービスを提供する事業です。
派遣した人材への給与は、人材派遣企業が支払います。
人材派遣企業の収益は、企業からの報酬金と派遣した人材への給与を差し引いた額となります。
主な人材派遣企業は、次です。
人材広告
人材広告とは、企業の求人情報を自社メディアに掲載するサービスとなります。
人材広告企業は求人情報を掲載することで、「掲載料」や「成果報酬」を受け取ります。
次に記載しているのが、主な人材広告企業です。
人材コンサルティング
人材コンサルティングは、企業の人事採用戦略や、人事評価制度についてのコンサルティングをする事業です。
人材コンサルティング企業は、コンサルティング料金を受け取ります。
人材コンサルティングをしているのは、次の企業です。
「人材業界」と一口に言っても、ビジネスモデルが全然違うんですね!
そうなんだよ!各ビジネスモデルごとに利益率も違ってくるから、ホワイト度も変わってくるよ。
人材業界のやりがい

この章では「人材業界の魅力」について考えていきましょう。
働く上でのやりがいや身につくスキルがあることは重要ですからね。
人材業界の魅力は大きく次の2点だと僕は思います。
【人材業界の大きな魅力】
- 人の人生の選択に立ち会える
- 営業力が身につく
魅力① 人の人生の選択に立ち会える
人材業界の最大の使命は、求職者に適した仕事を提供することです。
就職は人生に関わる選択。
その重要な選択を支援できるのは人材業界の一番の魅力であり、やりがいですよね。
実際に僕がサラリーマンの時、仕事に行くのが本当に嫌でした。
そうなってくるともはや日曜日から憂鬱なんですよね...。
よって1週間のうちで楽しめるのは金曜の夜と土曜だけ。
長い人生の中、仕事が合わないだけで不幸せだなと実感しました。
仕事、企業の選択は自分の幸せに大きく影響する。
だからこそ、関わった人の仕事選びや企業選びに携わることは、その人の幸せに直結するので責任感もありますが、同時に大きなやりがいもあると思います。
魅力② 営業力が身につく
人材業界の営業職につけば「営業スキル」を磨けます。
人材業界は営業が花形の仕事です。
ほぼすべての企業が人材を求めています。
例えばマイナビやリクナビなら、掲載企業を探す必要があります。
人材紹介会社なら紹介先を増やすための営業が必要になってくる。
現物の商品がないからこそ、関わる企業との関係性が大事です。
そして、企業を増やすための営業が非常に重要な役割をするのです。
これらの理由から営業のノウハウやスキル、経験を磨く環境が整っているのも人材業界の魅力です。
たしかに「仕事」と「幸せ」って切り離せないですよね。仕事が自分に合っているだけで、幸福度はめちゃくちゃ上がるでしょうから。
そうなんだよ。どんな商品を提供することよりもその人の幸せに直結するからね。
人材業界の将来性・今後の展望【4選】

人材業界は、働く人と企業を結びつける大事な役割を担っています。
ただ近年は「AI」や「DX」も進化しており、今後どう変わっていくのか気になる人も多いですよね。
そこで今回は、人材業界の将来性や今後注目されるポイントを解説します。
【人材業界の将来性を左右するポイント】
- AIやDXによる業務効率化
- 多様な働き方の拡大
- グローバル人材の需要拡大
- 企業のホワイト化が進む可能性
①AIやDXによる業務効率化
AIやDXの導入が進むことによる、業務効率化については着目しておきましょう!
たとえば、企業と求職者をつなげる人材紹介企業の場合。
AIが応募者の経歴や希望条件を分析して、一致度の高い企業を自動でリストアップすることで、マッチングを自動化できるようになる可能性があります。
さらにオンライン面談が増えてきた今、AIを使ったデータ分析やチャットシステムなども役立ちます。
現状、AIでは代替えできない最終面談や、人間関係の調整などは引き続き「人」の手が必要です。
ただAIやDXをうまく活用することで、事務作業やデータ管理の負担も大きく減り、結果的に職場環境が改善されるメリットも期待できます!
②多様な働き方の拡大
多様な働き方が増えていることも、人材業界には大きな影響があります。
リモートワークや時短勤務、副業などの多様な働き方が広がると、人材業界にも新しいサービスのニーズが生まれます。
なぜなら企業側は、一人ひとりのライフスタイルに合わせた雇用形態を求めるからです。
たとえば週3日勤務や在宅での仕事を希望する人が増えると、その働き方に対応できる企業を探すサポートが必要になりますよね。
そこで、人材業界の企業としては新たなサービスを展開できるのです。
働きやすさを大事にする人が多い今、この変化は大きなチャンスでもあります。
③グローバル人材の需要拡大
グローバル人材の需要が拡大していることについてもチェックしておくといいですね。
海外からの人材を積極的に採用する企業が増えており、人材業界はグローバル対応を進める流れがあります。
なぜなら国内の少子高齢化に伴い、幅広い業種で海外からの労働力を積極的に取り込もうとしているからです。
たとえば、外国人向けにビザ取得の手続きを手伝ったり、多言語で面接をしたりする仕組みがあるなど。
国際的なフォローができる人材企業は今後ますます需要が高まっていくと考えられますね。
④企業のホワイト化が進む可能性
人材業界といえば激務というイメージが強かったかもしれませんが、最近はホワイト化に取り組む企業も増えています。
なぜなら、働きやすさを整えないと、若い世代の人たちが「ここで働きたい」と思ってくれないからです。
実際口コミサイトなどをみても、労働時間の短縮や柔軟な勤務制度を整えている人材企業も増えてきている傾向にあります。
ホワイト化を進める動きは、人材業界においても今後は広がっていくと考えられますね。
人材業界は激務のイメージでしたが、最近はいろいろ変わってきているんですね。こうした取り組みなら安心できそうです。
そうなんだ。AIやDXのおかげで業務も効率化されてるし、多様な働き方を求める人にも合った環境が整いやすくなってるよ。気になるならチェックしてみるといいね。
【補足】人材業界はやめとけと言われる理由

ネットで「人材業界はやめとけ」という声を見ることがありますよね。
そこで補足として、人材業界はやめとけと言われがちな理由を共有しておきます。
人材業界はやめとけと言われる理由は、主に以下の5つ。
【人材業界はやめとけと言われる理由】
- 参入障壁が低くベンチャー企業が多いから
- 業務内容が単純化しやすいから
- 営業先があまりにも多いから
- 人と人との板挟みになるから
- 心理的な責任が重いから
まず、人材業界は参入障壁が低いので、個人事業主やベンチャー企業が多いんですね。
規模が小さい企業だと、一人当たりの業務量は増えるのに、競合が多いので儲けはそこまで取れなかったりするんです。
また、基本的には営業をしつづける必要がある仕事で、企業と求職者の板挟みになります。
人と人との板挟みになる人材業界の仕事を、面白い・やりがいがあると感じられるかどうかも働く上で大事ですね。
人材業界はやめとけと言われる理由については、以下の記事でより詳しく解説しています。
人材業界を志望しているけれど「やめとけ」という声で不安になっている人は、参考にしてくださいね。
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
人材業界は、現時点ではホワイトでもブラックでもありません。
ただ本記事で紹介した人材業界のホワイト企業5社からわかるように、業界全体として労働環境を改善していく流れはできつつあります。
今後の人材業界は働きやすく、人と企業を結びつけるやりがいに溢れた環境に変化していく可能性があるのです。
人材業界を志望している人は、しっかり1つ1つの企業の内情を調べてみてくださいね。
なお、この記事と合わせて「【人材業界ランキング】売上高や平均年収など項目ごとにトップ企業を厳選紹介!」も読んでみてください。
人材業界の企業を「売上」や「年収」など項目ごとにランキングで紹介しています。
企業探しにも役立つので、一度チェックしてみてください!
それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょうか。
【本記事の要点】
- 人材業界は企業ごとに残業時間や離職率が大きく異なるために、ホワイト業界・ブラック業界のどちらとも言いづらい。
- 人材業界は離職率だけを見ると比較的高い傾向にあるので、合う合わないがはっきりした業界と言える。(営業が得意不得意、勤務時間が遅くなりがちなど)
- 人材業界への就職を考える時に重要なことは1社単位で評価することであり、そのためには口コミサイトやOB訪問を駆使することがおすすめ。







