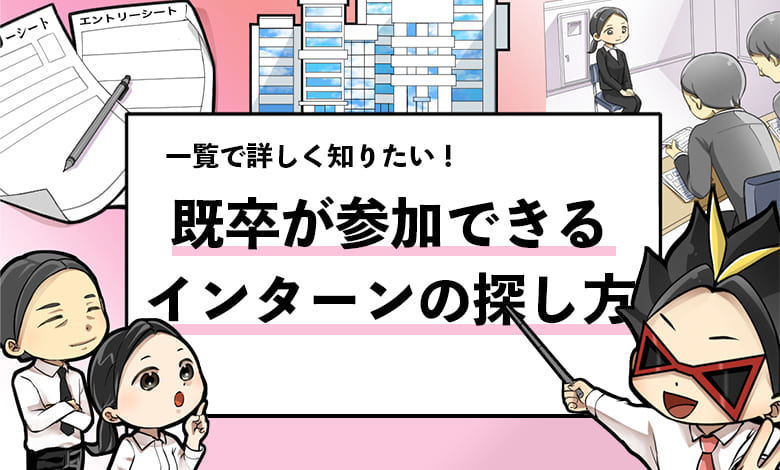
こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。
今回は"既卒者がインターンを探す方法"を解説していきます。
また探し方だけじゃなくて、どんなインターンに参加すべきなのかまで踏み込んで解説しますね。
既卒はとにかく空き時間の使い方が重要になってきます。
面接官から「既卒の期間中に何をしていましたか?」と聞かれるからです。
ここで「ただアルバイトをしていただけです」と答えてしまうと、確実にマイナス評価されてしまいます。
だからこそ、インターンシップに参加することで空き時間を有効活用しましょう!
最後まで有益な情報を濃縮して書いていきます。
- 「既卒」とは何か?|既卒の定義について
- 既卒者はインターンと同時に就活エージェントと連携すべき
- 既卒者向けのインターンの探し方4選
- 既卒がインターンシップを選ぶポイント
- 既卒がインターンシップに参加する際の注意点
- 【質問】既卒はインターンに参加できない企業もあるのでしょうか?
- 本記事の要点まとめ
「既卒」とは何か?|既卒の定義について
この記事の最初に、既卒の意味について触れておきます。
既卒とは「大学や短大・専門学校などの教育機関を卒業後、正社員にならなかった人」のことを指します。
主に卒業後、3年以内の人のことを指す言葉なので、そう覚えておいてください。

似た言葉に「第二新卒」という言葉があります。
第二新卒は、1度正社員として就職後に3年以内の転職を考えている人です。
よって既卒は"正社員経験のない"卒業後3年以内の人。
第二新卒は"正社員経験のある"卒業後3年以内の人だと覚えておきましょう!
なるほど!既卒は正社員経験のない人のことを指すんですね!
そうだよ。正社員経験のある人は既卒ではないので、そこを押さえておきましょう。
既卒者はインターンと同時に就活エージェントと連携すべき

既卒者がインターンに参加することは非常に有効です。
しかしインターンに参加するだけでは、内定を獲得することはできません。
(インターン先から内定が出ることはありますが、それはある程度の期間、働いてからになります)
そこで既卒は第一に、既卒者は就活エージェントと連携すべきです。
既卒に特化して、面談を元に求人の紹介から選考支援までしてくれます。
また、既卒向けの求人を常に保有しているので、どのタイミングでも求人を紹介してもらえて選考に進むことができます。
1日でも早く正社員になりたい既卒者にとっては非常に大きなメリットですよね。
既卒に特化した就活エージェントとしておすすめどころは以下です。
どちらも大手かつ、既卒や第二新卒などの若手に特化しているので、担当者さんの知識が豊富で頼りがいがあります。
(マイナビやリクナビなどの大手が提供しているものは、転職者向けなので既卒とは相性があまり良くないです)
【既卒の就活に強い就活エージェント】
・DYM就職|多数の求人を保有
(対応エリア:東京、札幌、仙台、名古屋、京都、大阪、広島、福岡)
・ウズキャリ|書類通過率が驚異の87%超えと支援が手厚い
(対応エリア:東京、大阪、名古屋、福岡、沖繩、オンライン面談可能)
ちなみにこうした既卒に特化した就活エージェント、就活サイトをランキング形式でまとめた記事も以前書きました。
「既卒なんだけど、どんなサイトやサービスを使えば良いのか分からない」という方は、インターンを探す前に、知識として入れておいてくださいね!
なるほど!インターンを探しつつ、内定を獲得するためにも就活エージェントと連携して、自分に合う求人を同時に探していくことが重要なんですね。
そうだね。既卒者は翌年の就活解禁で、新卒向けの求人にも応募することができるけど、既卒向けの求人に通年でエントリーすることもできるからね。
内定率を上げるためも両方行うのがおすすめだよ。
既卒者向けのインターンの探し方4選

それでは就活エージェントと連携して、求人を探しつつ、インターンシップも探して空き時間の有効活用に励んでいきましょう。
インターンシップには1日〜1週間ほどの短期インターンと、3ヶ月以上の長期インターンがあります。
そのまま入社に繋がることや、職種理解の深さを考えると長期インターンがおすすめ。
しかし、長期インターンの開催場所は関東や関西などの都市部に集中しているので、地方の方には向いていません。
しかし既卒向けのインターンのほとんどは長期インターンです。
よってそもそも都市部へ通うことができない既卒者はインターンへの参加が向いていないる可能性がある。
参加できそうな地域のインターンがあるかどうかを調べてみて、求人がない場合は、インターンに無理に参加せずに、本を読んだり、プログラミングを学んだりと自己研鑽に励むことをおすすめします。
【既卒者向けのインターンの探し方】
- インターン専門のサイトを利用する
- wantedly経由でインターンの参加をお願いする
- ハローワークでインターンの開催企業をヒアリングする
- 企業の公式サイトから応募する
探し方① インターン専門のサイトを利用する

既卒がインターンシップを探す方法として、最も効率的なのがインターン専門サイトの利用ですね。
マイナビやリクナビのような求人情報に特化したサイトではなく、インターン専門の求人に特化したサイトが複数あるんですよね。
インターンは大学生向けの印象がありますが、大手のインターンサイトである「ゼロワンインターン」で調べてみると、既卒歓迎のインターンは1453件もあります。
このように、インターン専門サイトはインターンの求人が豊富なので使い勝手が良いですね。

既卒が応募できる長期インターンシップの求人を扱っているサイトをまとめておきますね。(23年10月18日時点)
既卒が応募可能なインターンシップを扱っているサイトとしては、ゼロワンインターンが最も多いのでおすすめですね。
逆にこれら以外のサイトだと、既卒歓迎のインターンシップを掲載している求人サイトがほとんどないので、上記のサイトから探すのが現状は最適かと。
探し方② wantedly経由でインターンの参加をお願いする

続いて、インターンシップの探し方としてwantedly(ウォンテッドリー)の活用があります。
wantedlyはビジネスSNSとして約35000社の情報が掲載されています。
あくまで求人サイトではなく、ビジネスSNSなので、企業に対してエントリーではなく「話を聞きにいきたい」というボタンから接点を持つことができるんですよね。
よってこの「話を聞きにいきたい」を経由して、インターンシップに参加させてもらえないかを直接交渉するのもおすすめです。
面接練習にもなる
ちなみにwantedlyを経由して、企業の担当者と話す機会を作ることは面接練習にもなるんですよね。
企業側はインターン生を雇う時に必ず面接をおこなうわけで、それが面接練習の場数にもなるため、たとえインターンとして採用されなくても経験が残る。
wantedlyに掲載している企業の多くは、ベンチャー企業や中小企業であり、かなり柔軟に話を聞いてくれる企業が多いです。
だからこそ、既卒がインターンとして採用してもらうためにちょうど良いサイトだと僕は考えています。
wantedly公式サイト:
https://www.wantedly.com/projects
探し方③ ハローワークでインターンの開催企業をヒアリングする

次に既卒がインターンを探す方法として、ハローワークに1度相談してみるのも良いでしょう。
ハローワークでは既卒者の就職支援も行っており、担当者によっては企業との繋がりが深いような人もいます。
そういった人にインターンに参加したい旨を伝えることで、企業と繋いでもらえる可能性があるんですよね。
ハローワークは基本的に求人の紹介がメインですが、担当者によっては柔軟にインターンを探してくれる場合もある。
かなり非効率かつ、可能性は低めですが伝えておくだけ損はありません。
探し方④ 企業の公式サイトから応募する

そして最後に、既卒のインターンの探し方としては企業の公式サイトからの応募があります。
1社ごとに検索する手間と、既卒が応募可能なものを厳選する手間がかかるので、おすすめ度は低いですが、気になる企業があればインターンを募集していないか確認してみてください。
直接問い合わせることで対応してくれる企業もある
またベンチャー企業や中小企業の場合、お問い合わせからインターンとして働きたい旨を伝えることで対応してもらえる可能性があります。
wantedlyと同じ要領で、自分を売り込むイメージですね。
僕ならこんなメールでお問い合わせをするというテンプレを書いてみたので、直接お問い合わせする場合はぜひ活用してください。
【インターンの参加を直接お願いする場合のテンプレ】
件名)インターンシップについての相談|(名前)
◯◯株式会社
採用担当者様
初めてご挨拶させていただきます。
私、◯年に◯◯大学を卒業し、
既卒として採用活動を行っております(名前)と申します。
貴社にて、ぜひインターン生として働きたいと考えご連絡致しました。
つきましては、貴社の◯◯職にて、インターン生の受け入れに対応されているか、ご回答頂けると幸いです。
私がこうして既卒として活動している背景ですが、
就活時にインターン経由で企業理解を深めた上での入社が重要だと考えました。
お忙しい中、大変恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます。
◯◯大学 ◯◯年卒業
(名前)
(電話番号)
(メールアドレス)
基本的にはインターン専門の求人サイトからの応募が最もおすすめ!それに加えて、wantedlyや企業への直接応募にて参加する方法があるよ!
直接連絡する方法は、営業の練習にもなりそうで良いですね!
既卒がインターンシップを選ぶポイント

ここまで既卒者向けのインターンの探し方を紹介していきました。
加えて、最も大事な視点である「どんなインターンシップに参加すべきか」という、インターンの選び方についてこの章で解説していきます。
インターンの中には、アルバイトと変わらないような仕事も多くあります。
そんなインターンだと参加したところで、アルバイトと何も変わらず、ただコキ使われるだけで終わるので意味ないですよね。
そこで僕が考えるインターンシップを選ぶポイントを2つ押さえておいてください。
ポイント① 将来的に就きたい職種を選ぶ
まず第一に、将来就きたい職種を選ぶことをおすすめします。
そもそもインターンに参加する目的を明確化していない人が多いですが、目的の1つとして「職種理解のため」があると僕は思います。
将来、営業職に就きたいと考えている人がいたとしましょう。
しかし、これまでの人生の中で「営業職の具体的な仕事内容がどんなものか」や「本当に自分は営業職に合っているのか」を理解することは難しい。
要するに、ほとんどの就活生は予測でしか職種を選ぶことができないんですよ。
だから3年後の離職率の平均が3割になるほど多いわけで。
インターンを通して、職種理解を深めることで、自分が本当にその職種に合っているかどうかを確かめることに繋がります。
志望職種でのインターン経験は就活の際のアピール材料になる
更に言うと、自分が志望している職種でのインターン経験があると、就活の際のアピール材料にもなりますよね。
インターンでの営業職経験のある人の方が、面接官に「この人は既卒だけどしっかりと営業経験もあるんだな」と思ってもらえる。
また既卒としての空き時間を有効活用したと認識してもらうこともできます。
これらの理由から、インターンを選ぶ際は自分の志望職種を中心に選ぶことをおすすめします。
(入社してから全然営業を任せてもらえない、雑用ばかりだったとならないよう、求人情報の確認や担当者との事前の話し合いは徹底しておきましょう)
ポイント② 仕事内容が単純作業のインターンは避ける
続いて、既卒がインターンを選ぶポイントとして、仕事内容が単純作業のインターンは避けるようにしてください。
例えば、一生テレアポだけをさせられるようなインターンですね。
これはアルバイトと変わりません。
(企業側はインターンと名前を変えることで、人を集めようとしているパターンがよくあるんですよ!)
テレアポだけでなく、企業への営業訪問、資料作成まで任してもらえるようなインターンが好ましいですよね。
このように"アルバイトと同じような単純作業ではないか"という視点を持って、インターンの求人を精査するようにしてください。
【おすすめしないインターン内容】
- テレアポ業務
- 販売店での販売業務
- 訪問営業(個人の家を訪問して売り込む営業)
- アシスタント業務(雑用ばかりの可能性が高い)
- ライター(将来ライターになりたい人は良いがそうじゃない人はひたすら記事の作成を任されるだけの可能性も高いのでおすすめ度は低い)
なるほど!インターンとして応募していても、実質的にはアルバイトと変わらないような求人も多いんですね。
そうだよ。アルバイトだと集まらないから、インターンとして人手を集めようとしている企業は多い。そういうインターンって、参加しても学べることが少なかったり、就活で話せるような経験が積めない可能性があるから注意しよう。
既卒がインターンシップに参加する際の注意点

続いて、既卒がインターンシップに参加する際の注意点を紹介します。
参加するにあたって、これだけは押さえておいて欲しいという事を3つ共有しておくので、これからインターンへの参加を検討している人は押さえておいてください。
【既卒がインターンシップに参加する際の注意点】
- 労働条件が悪い場合ははっきりと伝える
- 自分に合わない場合はスパッと辞める
- フルコミッションのインターンは要注意
注意点① 労働条件が悪い場合ははっきりと伝える
まずインターンシップに参加してみて、あまりに労働条件が悪い場合ははっきりと伝えるようにしましょう。
明らかに時給が低い、無給で残業をさせられる、休日出勤を過剰にお願いされるなど、企業によってはインターン生を雑に扱うような企業もあります。
その場合は「せっかくインターンをさせてもらっているのだから仕方ないか」と考えずに、はっきりと伝えた方が良いですよ。
(仕方ない...という優しさがある人は、本当にカモにされるで気をつけましょう)
注意点② 自分に合わない場合はスパッと辞める
次に、インターンシップに参加してみて明らかに自分に合わないと判断した場合は、スパッと辞める選択をとっても良いですよ。
インターンシップの参加経験は履歴書に絶対に書かないといけないものではありません。
よってインターンを1週間で辞めようが、それが経歴として残ることはない。
「長く働かないと経歴に傷が...」と考える必要はありません。
例えば、営業職のインターンに参加してみて、明らかに苦手かつ仕事が嫌だと思う場合(努力しても改善の見込みがない)は別の職種を経験する時間を作った方が良いですよね。
人にはそれぞれ適性ってものがあります。
例えば、僕は考えることが大好きですが、単純作業が死ぬほど苦手です。
もし僕が工場勤務になって単純作業を任されたら、誰よりも仕事はできません。
「Aの職種が苦手だから、自分は仕事ができない人間なんだ」と考えるのではなく、「Aの職種は苦手だった。次にBの職種への適性が高いかどうか確かめてみよう」と適性の高い仕事を探し続けることがキャリア形成において重要だと思いますね。
注意点③ フルコミッションのインターンは要注意
最後に、ゼロワンインターンのインターン求人を見ていると「フルコミッション」の求人が意外と多いことに気づきました。
フルコミッションとは「完全歩合制」のことで、成果を出したら報酬が支払われる仕組みのことです。
逆に言えば、成果が0だと給料も0になってしまいます。
そんなフルコミッションですが、既卒には特におすすめしません!
既卒者はただでさえ就活がうまくいくか不安な状態にあります。
そこでフルコミッションの仕事をして、成果が出せなかった場合、本当にメンタルをやられると思うので避けた方がいいよなー、と思いますね。

そもそもフルコミッションを採用している企業って、「リスクを出さずに人を使いたい」という考えが透けて見えるので個人的に好きではありません。
バリバリの経験者を採用して、高い報酬のフルコミッションで雇うのは良いと思います。
しかし、正社員経験のない既卒を大歓迎としつつ、安い報酬のフルコミッションを採用している企業は個人的に微妙だと思っています。
たしかにフルコミッションというプレッシャーが既卒にかかるのは、負担が重すぎますよね...。
そうだね。企業側はそういった負担になるとか考えていなくて、リスクなく稼ぐことを優先しているように僕は思えてしまうよ。
【質問】既卒はインターンに参加できない企業もあるのでしょうか?

既卒の方からよくある質問として、「既卒は参加できないインターンはあるのでしょうか?」という質問が挙げられます。
結論から言うと、インターン生として既卒を受け入れていない企業はあります。
そもそも企業によっては新卒のみしか採用しない企業もあるんですよね。
ですが、そういった既卒は参加できないインターンを避ければ良い話です。
具体的に長期インターン用の求人サイト大手であるゼロワンインターンを見ると、「既卒歓迎」の求人が約1800件もありました。
既卒が参加できないインターンもありますが、一方で既卒歓迎とするインターンも大量にあるので、既卒歓迎のインターンを選ぶようにするのがおすすめです。

本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
既卒者向けのインターンの探し方や注意点まで、把握してもらえたら幸いです。
既卒向けのインターン求人サイトを見ると、社長直属で仕事ができたり、マーケティング、法人営業など本当に面白そうなインターンが多かったんですよね。
長期インターンの場合は給料が出るので、アルバイトをするならこうした長期インターンシップに参加する方が絶対的におすすめだと僕は思います。
しかし、当然ですがインターンに参加することに加えて、既卒として正社員になるための就活も同時並行で行うことが重要です。
インターンに参加することで"やっている気になる"という状態になりやすく、インターンが終わった時に「やば!全然就活はしてなかった!」となる可能性がありますからね。
(インターン先にそのまま正社員採用されるかどうかは、インターン先が決めることなので)
既卒向けの就活のやり方は「【既卒1年目の就活のやり方】卒業したての既卒者は何をすべき?」にてまとめておきました。
インターンへの参加と合わせて、同時並行で就活もこなしていきましょう!
それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょうか。
【本記事の要点】
- 既卒歓迎の長期インターンシップ(3ヶ月以上のインターンシップのこと)は多数存在する。
- 長期インターンシップの開催場所の多くは関東や関西などの都市部に偏っているので、地方在住でそのまま地方就職を考えている人は参加できない可能性が高い。
- 長期インターンシップの探し方として最もおすすめはゼロワンインターンなど、インターンシップの求人に特化したサイトを利用すること。
今回の記事が少しでもあなたの就活の役に立ったのなら幸せです。
就活攻略論には他にも、僕が4年に渡って書き続けた800の記事があります。
ぜひ他の記事も読んでもらえると嬉しいです\(^o^)/







