
就活生や転職者のみなさん、こんにちは!
これまで7年、書いた記事は1500記事を超え、求人サイトの運営まで始めた"日本イチの就活マニア"こと就活マンです!
今回は「就活向けの自己紹介カードの書き方」について解説していきます。
最近の就活生だと、自己紹介カードってワード自体、馴染みがないですよね。
それも当然といえば当然なんです。
なぜなら近年の就活では、ほとんどの企業がエントリーシートの提出を求めているため、自己紹介カード自体を使っていないんですよね。
ただ、稀に自己紹介カードの提出を求めてくる企業もいます。
加えて、自己紹介カードは選考以外でも有効活用することができるんですよね。
本記事では、有効活用する場面や自己紹介カードに書くべき内容、項目ごとの例文などを共有していくので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
そもそも自己紹介カードとは?

そもそも「自己紹介カードって何?」という疑問を持つ人もいますよね。
イメージとしてはエントリーシートにかなり近いものです。
エントリーシートとの違いは「必須かどうか」という点ですね。
最近の就活において、エントリーシートの提出はほとんどの企業が必須としています。
一方で、自己紹介カードの提出を必須にしている企業はないですよね。
加えて、エントリーシートには企業指定やOpenESなどの様式がありますが、自己紹介カードにはそういった様式もありません。
自己紹介カードの目的
エントリーシートとは違って提出が必須でもなく、決まった様式もない自己紹介カードの目的って何だと思いますか?
もちろん、ごくわずかではありますが、企業が提出を求めてくる場合もあります。
そのケースでいえば、選考書類としての目的となりますよね。
しかしこのケースは非常に稀なパターン。
僕が考える自己紹介カードの活用目的は「詳細な名刺」ですね!
普通の名刺だと、名前や大学名、連絡先程度しか情報がないですよね。
しかし自己紹介カードの場合、それらに加えて趣味特技や長所、資格やガクチカなどあなた自身について詳細な紹介文を記載します。
つまり、企業に対して自分自身のアピールするための手段の一つですね!
企業説明会やOB訪問など、企業担当者と関わる際に渡すことで、自分を知ってもらうことができますよね。
【重要】現在の就活では作成する機会は少ない!
何度も言いますが、現在の就活ではエントリーシートの提出が主流です。
つまり、自己紹介カードが必要な機会はほとんどありません。
どちらかというと、必須対策ではなく補足対策的な位置づけですね。
自己紹介カードよりも優先すべき対策は多くありますからね。
あくまで自己紹介カードは「プラスアルファ」であることを理解してください。
優先すべきはエントリーシートの作成なので、まずはそちらに全力を注ぐべきですよ!
たしかに自己紹介カードって言葉自体、聞く機会が少ないですね。
今の就活ではほとんど聞かないよね。主流は間違いなくエントリーシートだから、まずはエントリーシートの質を高めるべきだよ。
就活で使う自己紹介カードに書くべき内容
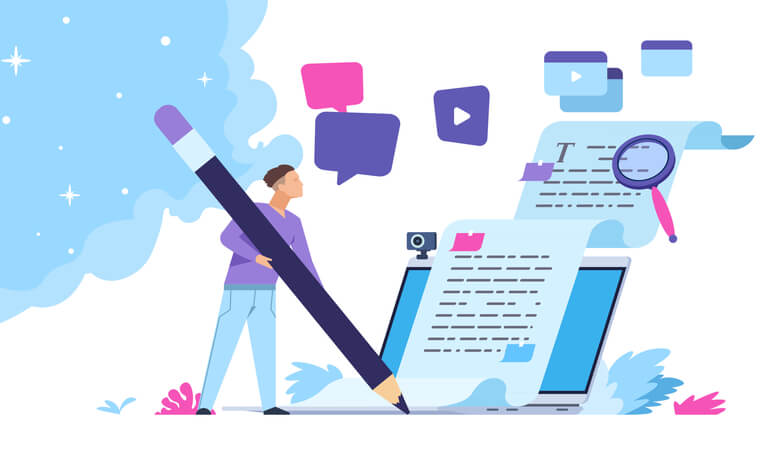
自己紹介カードの必要性について解説しました。
ただ、この記事を読んでくれてるということは、自己紹介カードの提出が必要である就活生の可能性も高いですよね。
そこでこの章からは、自己紹介カードの書き方について解説していきます。
まずは自己紹介カードに書くべき内容について共有しますね!
【自己紹介カードに書くべき項目】
- 基本的なプロフィール(氏名・大学名等)
- 部活・サークル
- 資格
- 趣味特技
- 長所
- ガクチカ
項目① 基本的なプロフィール
まずは基本的なプロフィールを書いてください。
「氏名」「大学名」「学部学科」など、名刺に書く程度の簡単なプロフィールで十分ですよ!
項目② 部活・サークル
次に「部活・サークル」を書きます。
こちらも詳しく書く必要はないですが、キャプテンなどの役職に就いているのであれば書いておくべきですね。
また、所属している部員数や練習頻度、目標としている内容(リーグ戦優勝、インターハイ制覇など)も書くと、企業側もイメージしやすくなりますよ。
項目③ 資格
次に「資格」も書いておきましょう。
その時点で保有している資格はもちろん、大学卒業時に取得予定の資格があれば「取得見込」という形で記載して大丈夫ですよ。
(TOEICなんかも資格ではないですが、アピール要素になるので記載すべき!)
項目④ 趣味特技
次に書くべきは「趣味特技」ですね。
こちらも詳細まで書く必要はないので、項目と簡単な説明程度で十分です。
項目⑤ 長所・短所
「長所・短所」も書いておくべきですね。
趣味特技同様、項目と簡単な説明という流れで書いておけば大丈夫です。
項目⑥ ガクチカ
最後に「ガクチカ」を書いておくのもおすすめです。
あなた自身の人柄について、ガクチカは最もアピールしやすいですからね。
ただ、あくまで「自己紹介カードにおけるガクチカ」なので、エントリーシートレベルの詳しい内容はいりません。
また、自己紹介カードとは別にエントリーシートの提出を求められ、ガクチカをそちらで書くのであれば、自己紹介カードに書く必要はありませんよ。
【補足】選考に必要であればエントリーシートを参考にすべき
この章では詳細な名刺としての「補足的な自己紹介カード」に必要な項目を共有しました。
ただ、選考に必要な自己紹介カードの提出を求められることもありますよね。
その場合は作成したエントリーシートを参考にすれば問題ありません。
項目についても「志望動機」や「自己PR」など、エントリーシートで記載している項目をそのまま使いましょう。
エントリーシートを転用することで、新しく文を考える必要もありません。
就活において効率性は非常に重要なので、この方法がおすすめですよ!
ポイントは「簡潔に書くこと」だよ。エントリーシートに慣れてるとどうしても詳しく書いてしまうんだけど、あくまで補足的な位置づけのため、長い文章はかえってマイナス印象だよ。
就活で使える自己紹介カードの例文

自己紹介カードに書くべき項目を解説しました。
次にこの章では、先ほどの項目を使って、具体的な例文を共有しますね。
実際に例文を見ることでイメージしやすくなるかと思います。
なお、全体文量の目安は「A4用紙1枚程度」になります。
【自己紹介カード完成例文】
氏名:就活 太郎
所属大学:◯◯大学 ◯◯学部 ◯◯学科 ◯年
<部活・サークル>
・アカペラサークルの活動に注力
・リーダーとして50名のメンバーをまとめた。
・文化祭ではオリジナル高いパフォーマンスで高評価を得た。
大学時代はアカペラサークルの活動に注力しました。3年の時にはサークルリーダーとして、アカペラの課題曲、出演・企画するイベント、参加するコンテストなどサークル運営を先導しました。
<資格>
・2020年◯月◯日 日商簿記検定試験2級 取得
3級は2018年に取得済み。2級は一度目の受験では不合格となり、1年ほど勉強して2級の取得に成功しました。
・2020年◯月◯日 TOEIC830点
社会人になれば活用する場面も多いと考え、英語を勉強してきました。英語力を図るためにTOEICを受検し、830点を取得しています。900点台を目指し、今も勉強を継続しています。
・2018年◯月◯日 普通自動車免許 取得
サークル活動での機材運搬などで必要となり、大学1年生のサークル入会後すぐに取得しました。
<趣味特技>
・趣味:ピアノ
・特技:水泳
ピアノは5歳の頃から近所のピアノ教室に通って上達させてきました。高校受験を機にやめましたが、それ以降も趣味としては続けています。
水泳は小学校5年生の時から習っていて、高校では水泳部に所属していました。長距離の部門で県大会5位に入賞した経験もあります。今でも継続して2km以上泳ぐことが可能です。
<長所・短所>
・長所:先頭に立って行動できる点
・短所:自分の意見を言わないと気が済まない点
持ち前の高いリーダーシップを発揮し、個性豊かな50名のメンバーを1年間、牽引してきました。社会人としても、プロジェクトや事業を推進していく際に活かします。
一方、自身の意見を言わないと気が済まない性格が短所です。短所として理解はできているため、今後は「今必要な意見なのか」を考えるとともに、客観的に聞く姿勢も重視していきます。
<学生時代、最も力を入れて取り組んだこと>
・ゼミにおける「都市の交通網」に関する研究活動
社会学部である私は、都市計画について研究するゼミに所属し「都市の交通網」に関して現状の交通網の課題・解決方法を考察しました。具体的には日本有数の大都市である◯◯市の交通網に焦点を絞り、市役所の都市計画を担当する方や、地元の鉄道会社などのヒアリングを実施。また、交通渋滞、地方公共鉄道の混雑度合いなども調査。最終的に◯◯市の交通網の課題をまとめ、中間研究発表会でプレゼンをしました。今後は主要道路の高規格化や◯◯市でも取り入れられている市営交通システムの導入などを軸とした解決策を結論として提示する予定です。
最初に簡潔な結論を書くことで見やすくなるんだ。その後に説明文を書けば、説明の内容も理解しやすいからね!
評価される自己紹介カードの作成方法

自己紹介カードの例文を共有したので、イメージはできたかと思います。
ただ、せっかく作成したなら、より評価される内容にしたいですよね!
そこでこの章では、自己紹介カードの質を高める方法を解説します。
僕が特におすすめするのは以下の3つですね。
【自己紹介カードの質を高める方法】
- 逆求人型サイトを利用して現役人事に添削してもらう
- 自己分析を徹底することで説得力を高める
- 先にエントリーシートの質を高める
方法① 逆求人型サイトを利用して現役人事に添削してもらう
僕が最もおすすめする方法が「逆求人型サイトの利用」ですね。
逆求人型サイトとは、プロフィールを入力するたけで企業側からオファーをもらえるサービスのこと。
オファーがもらえたら、そこからチャットにてやり取りが可能。
つまり、現役人事に対して就活相談することができるんです。
自己紹介カードを提出するのって企業人事ですよね。
ということは、提出先であり評価する側の立場である企業人事の方に添削してもらうのが一番効果的だということです!
また、逆求人型サイトはサービスごとに登録企業が異なります。
よって、いろんな業界の人事担当者と繋がるためにも「複数のサイトを併用する」のが重要です!

これまで200以上の就活サイトを見てきた僕のおすすめは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「ホワイト企業ナビ」の2サイト。
」と「ホワイト企業ナビ」の2サイト。
まだ利用したことがない人は、この機会にぜひ使ってみてくださいね。
方法② 自己分析を徹底することで説得力を高める
自己紹介カードを書く上で必須となるのが自己分析ですね。
自分自身のことを紹介するわけですから、自己分析なしには書けません。
逆に自己分析をしないまま作成した自己紹介カードの説得力はめちゃくちゃ低くなるんですよね。
ただ、自己分析って正直面倒な作業でもある。
そこで「なるべくわかりやすく簡潔に自己分析する方法」について、別記事にて解説したので、ぜひこちらを参考にしてください!
方法➂ 先にエントリーシートの質を高める
自己紹介カードとエントリーシートの違いは説明しましたよね。
ただ、大半の就活生は自己紹介カードより先にエントリーシートの作成をすると思います。
自己紹介カードはエントリーシートからの使い回しも可能。
そのため、先にエントリーシートの質を十分に高めておくことこそ、質の高い自己紹介カードの作成に直結するといえますね。
たしかに現役人事に添削してもらう方法が一番効率的ですね!
評価するのは企業の人事担当者だからね。人事担当者の目線で見て、面白いと思ってもらえる自己紹介カードの作成を目指すべきなんだ!
自己紹介カードを作成する時の注意点

それでは最後に、自己紹介カードを作成する際の注意点を共有しておきます。
以下の点に注意してくださいね。
【自己紹介カード作成上の注意点】
- 必ずパソコンなどのテキストで作成する
- とにかく「見やすさ」を重視する
- 記載事項を増やし過ぎない
- 必ず許可を取ってから提出する
注意点① 必ずパソコンなどのテキストで作成する
まず注意すべきは作成方法について。
手書きではなく、必ずパソコンなどのテキストで作成してください。
理由はシンプルで「その方が見やすいから」ですね。
特に字に自信がない方などは、それだけで見る側の意欲がなくなってしまうこともあるので、パソコンで書くべきです。
注意点② とにかく「見やすさ」を重視する
次に注意すべきは「見やすさを重視すること」です。
内容に集中するあまり、レイアウト面をおろそかにしてしまし、見にくい構成になるのは絶対に避けるべき。
冒頭でもお伝えしたとおり、選考で提出を求められるパターンを除いて、自己紹介カードは「補足的な役割」でしかありません。
つまり、企業担当者も必ず見なければいけない書類ではないんですよね。
そこで見にくいレイアウトだったら、ただでさえ忙しい中、わざわざ見ないですよね。
注意点③ 記載事項を増やし過ぎない
次の注意点は「記載事項を増やし過ぎないこと」です。
これも先ほどの見やすさに関連した内容ですが、量が多すぎる文章って単純に読みたくないですよね。
ましてや必須書類でもなければ、見てもらえる可能性の方が低いわけです。
目安としては「A4用紙1枚以内」ですので、これ以上書く必要はありません!
注意点④ 必ず許可を取ってから提出する
最後の注意点は「必ず許可を取ってから提出すること」です。
ただ、選考における必須書類のパターンは除きます。
例えば郵送にて自己紹介カードを送るなどは避けるべきですね。
ましてや事前に許可を取ってなければ、企業側も何の書類なのかわかりません。
渡しやすいタイミングとしては「企業説明会直後」などがベストかと思います。
もちろんその場合でも「御社に私のことをさらに知っていただきたく、お渡ししてもよろしいでしょうか。」という事前許可は取るべきですよ!
たしかにこれらの注意点は事前に把握しておくべきですね。
せっかくアピールするための自己紹介カードなのに、そこでマイナス印象を与えてしまったら本末転倒だよ。。。
本記事の要点まとめ
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!
就活における自己紹介カードの位置づけや書き方について、ご理解いただけたかと思います。
自己紹介カードって、別に出さなくても問題ないんですよね。
ただ、プラスアルファの配慮だったりアピールという意味では、たしかに効果的な方法になります。
就活で内定を獲得するためには、いかに企業担当者の印象に残るかが重要です。
そういった視点でみても、自己紹介カードはメリットが大きいからこそ、マイナス印象を与えない内容にすることを忘れずに!
それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりにしましょうか。
【本記事の要点】
- 自己紹介カードとエントリーシートの最も大きな違いは「提出必須かどうか」という点である。
- 現在の就活で自己紹介カードを作る機会は少ない。
- 万が一、作成する必要があってもエントリーシートから内容を転用できるため、優先すべきはエントリーシートの質を高めること。
- 自己紹介カードの質を高める最もおすすめの方法は「複数の逆求人型サイトを併用」して現役人事に添削してもらう方法。
- 自己紹介カードを作成する上で注意すべきは「パソコンで作成」「記載事項を増やし過ぎない」など、とにかく見やすさを重視することである。









