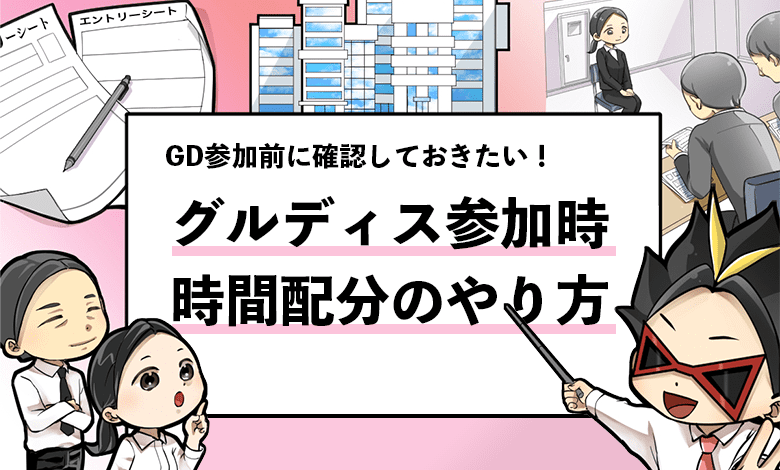
【2025年8月追記】
・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加
就活生の皆さん、こんにちは!
このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!
少しだけお知らせさせてください!
8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!
しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!
僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)
この本はそれを形にした本です。
「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。
全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!
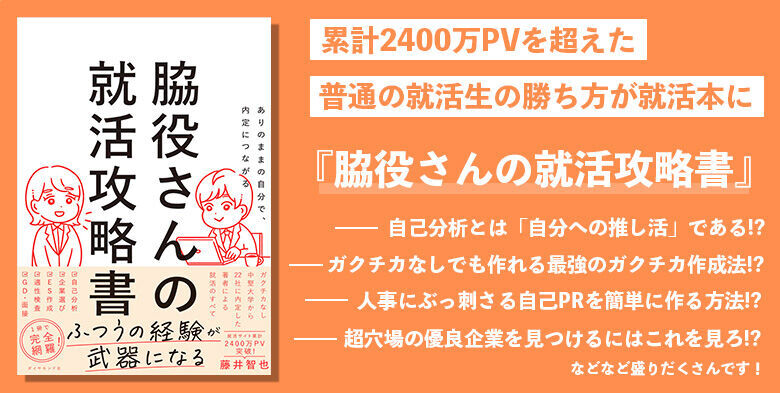
それでは本題に入っていきますね!
本記事を読めば、グループディスカッションの時間配分について「セオリー」や具体例を理解することができます!
基本的なグループディスカッションの進め方については以前「【グループディスカッション対策は9ステップ】GD攻略法を共有」の記事で解説しましたが、よくこんな意見を聞くことがあります。
「グループディスカッションの時間配分はどうやって決める?」「どのくらいが妥当な時間配分?」
しかし、グループディスカッションの時間配分には、ある程度のセオリーがあります。
つまり「知っている」か「知らない」かでグループディスカッションが成功するかどうかを決めるほど大きな要因を持っています。
そこで本記事では、グループディスカッションの時間配分について具体例を用いながら解説を進めていきます。
ぜひ本日の記事から、グループディスカッションの時間配分について学んでいってください!
グループディスカッションの時間配分にはセオリーがあるんですか!知っておきたいです...!
時間配分は「知っている」か「知らない」かで大きな差がある!グループディスカッションマスターになりたい人は必ず抑えておこう!
- 【結論】グループディスカッションのおすすめの時間配分
- 【必須知識】グループディスカッションの全体の流れ
- 【詳細解説】おすすめのグループディスカッションの時間配分
- グループディスカッションの時間配分で気をつけること【3選】
- 【補足】グループディスカッションの時間配分に失敗すると?
- グループディスカッションの時間配分に関するよくある質問
- グループディスカッションの時間配分はセオリーが超重要!
【結論】グループディスカッションのおすすめの時間配分
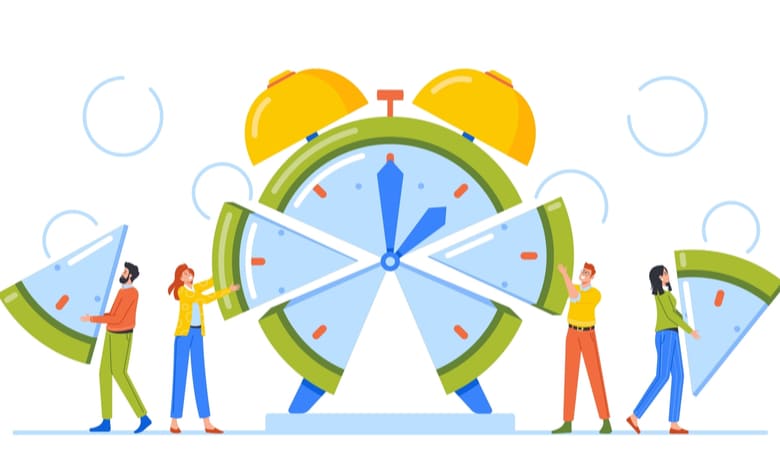
グループディスカッションの全体構成を、以下の①〜⑦の項目で想定し、オススメの時間配分をお伝えします。
グループディスカッションの基本的な流れは以下の8つです。
【グループディスカッションの全体構成】
①自己紹介
②役割決め
③時間配分
④定義付け
⑤アイデア出し
⑥アイデア整理
⑦発表準備
⑧バッファ時間(余白時間)
これらの構成を踏まえておすすめの時間配分から紹介しますね。
僕が考える時間配分の最適解は以下のとおりです!
【おすすめの時間配分】
全体時間が20分の場合)
①自己紹介+②役割決め+③時間配分:1分以下
④定義付け+⑤アイデア出し:8分〜10分
⑥アイデア整理:2分〜4分
⑦発表準備:4分〜5分
全体時間が20分の場合)
①自己紹介+②役割決め+③時間配分:2分以下
④定義付け+⑤アイデア出し:15分〜18分
⑥アイデアを整理:3分〜5分
⑦発表準備:2分〜4分
全体時間が1時間の場合)
①自己紹介+②役割決め+③時間配分:2分以下
④定義付け+⑤アイデア出し:30分〜35分
⑥アイデアを整理:5分〜10分
⑦発表準備:5分〜10分
⑧バッファ時間(余白時間):5分以上
上記の時間配分を覚えておけば、よほどの大きな間違いをしないので頭に叩き込んでおきましょう。
しかし「時間配分の理由や根拠は?」や「本当にこの時間配分で大丈夫?」と疑問に感じる人もいますよね。
後の章で、上記配分の理由について詳細を解説していきます!
よりグループディスカッションの理解を深めるために各項目の中身を見ていきましょう。
■グルディスを受けないで内定を獲得する攻略法もある!
(僕はグルディスがあまり好きじゃなかったので、この方法取ってた!)
グルディスを受けないで内定を獲得する方法として、基本的にグルディスを実施する企業は大手企業が多いんですよね。
そこで中小〜中堅企業の優良企業もちゃんと狙って内定を獲得する方法がおすすめで、これだとグルディスに当たる確率が下がります!
中小〜中堅企業を狙う方法として、1社ずつ探すのは当然なのですがかなり面倒なのと、そもそもどんな会社があるか分からないので、スカウトサイトがおすすめ。
大手サイトの「キミスカ」と「ホワイト企業ナビ」をプロフィールをコピペして簡単に併用して、より多くのスカウトを狙うのがおすすめです!
今は売り手市場なので、企業側からのアプローチが多いため、スカウトサイトの利用価値が過去一番レベルで高いのが最高です!ぜひ押さえておいてください!
ここで時間配分のおすすめを簡単に把握してから、次にグループディスカッションの全体の流れを確認していこう!
【必須知識】グループディスカッションの全体の流れ
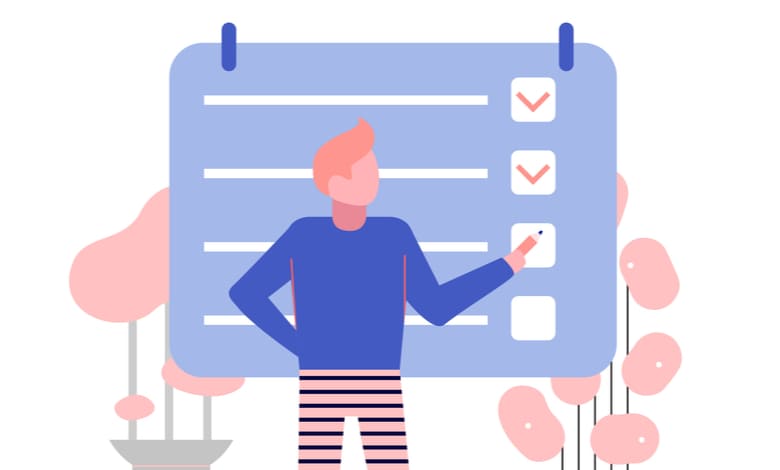
グループディスカッションの時間配分を把握する上で、まずグループディスカッション全体の流れを把握しておくことが重要です。
細部から見るよりも、全体把握を優先することが大切です。「木を見て、森を見ない」状態にはならないように気をつけましょう。
①自己紹介
まずは「自己紹介」です。
「では、グループディスカッションを始めてください」で始まった瞬間から、いきなりアイデアを投げつける人もいますが「いや、誰だよ」ってなりますよね。
まずは、議論する仲間のことを知るために自己紹介をします。自己紹介については、全体の時間にもよりますが、ダラダラと続ける必要はありません。
【自己紹介で最低限話しておく項目】
- 名前もしくはニックネーム
- 出身大学
上記2つを抑えておけば、その他余計な自己紹介は不要です。
②役割決め
続いて「役割決め」です。
グループディスカッションは、大きく4つの役割があります。
【グループディスカッションの4つの役割】
①司会
②書記
③タイムキーパー
④役割なし
僕がオススメしている役割は「②書記」ですが、自分が希望していない役割になってしまう場合も想定されますので、それぞれの役割について別記事で確認しておきましょう。
ここまでの「自己紹介」と「役割決め」については、手短に行うことです。
ダラダラと時間を使うのは勿体ないからです。
例えば、4人グループであれば1分程度。
6人グループだと2分程度で終わらせましょう。
ちなみに「【グループディスカッションで役割を決めないのは絶対NG】その理由と対策を解説」で詳しく解説しましたが、グループディスカッションで役割を決めないのはNGです。
なぜなら人事は、しっかりと役割を決めて、その上でそれぞれの役割を遂行できるのかを見ているからです。
それ以前に役割を決めないと、進行が難しくなるので絶対に決めてから進めましょう!
③時間配分の決定
続いて「時間配分」です。
役割分担が決まった後は、「司会」が進めることになりますが、時間配分についても30秒程度でパッと決めることが大事です。
ここもあまり時間を使う所ではありません。
ちなみに余談ですが、人事側担当者の意見では「時間配分を決めているグループ」と「時間配分を決めていないグループ」では、圧倒的に前者が優勢です。
理由はシンプルです。
社会人の仕事というのは全体把握をしておかなければいけないからです。
例えば、営業職で生産部門の業務大枠を理解している人と理解していない人では雲泥の差が出るからです。
「あいつ全然生産部門のこと考えてくれてないよな」と思われている営業職は残念ながらたくさんいます。
もちろんあんまり売れません。
グループディスカッションの進め方一つとっても「社会人としての全体把握能力」が測られています。
時間配分を決めるだけでも、社会人としての適正を測られているんですね!
そうですね。グループディスカッション中の発言から、社会人としての能力を見極められることが多いです!
④テーマの定義付け
続いて「テーマの定義付け」です。
議論を行う上で、前提条件を確認しておかなければ有効な議論はできません。
例えば、5W1Hの観点から「何について、誰が、どのように」と条件提示をすると良いでしょう。
これも社会人の業務では非常に大切です。
例えば、営業職の場合、商品説明をする相手は、経営者から消費者まで幅広い相手に説明しなければいけません。
「相手が誰なのか」によって説明の仕方は当然変わります。
大学生相手に説明するのと、業界専門家に説明するのは、全く異なりますよね。
それと同じです。
グループディスカッションでも「前提条件の設定」ができるかどうかで、社会人の適正を測られています。
まずはお互いの前提条件を整えるために「テーマの定義付け」が大切なのです。
⑤アイデア出し
続いて「アイデア出し」です。
議論の中心になる部分であり、全員で意見を出すことが大切です。
重要な3点を以下にまとめました。
【アイデア出しで大切な3点】
- 全員が意見を言うこと
- 頭ごなしに否定しないこと
- 具体⇆抽象を繰り返すこと
最後の「具体⇆抽象」については難易度が高いマル秘テクニックなので解説をします。
「アイデア出し」は、基本的に具体的な議論になりがちです。
しかし、議論が加速すれば本質的な部分から外れてしまうことが多々あります。
そこで、少し議論が外れてきたときに、"抽象的なアイデア”を出すことで議論を正常な軸に戻すことができます。
グループディスカッションマスターになりたい人は、是非覚えておいてください。
アイデア出しで困ったときは「具体化と抽象化」を覚えておいたら良さそうですね。
鋭いアイデアを出せれば、グループディスカッションでも活躍することができますので、是非覚えておきましょう!
⑥アイデアを整理してまとめる
続いて「アイデア整理とまとめ」です。
議論をまとめて発表準備を行うフェーズであり、グループディスカッションの総評に大きく関与する部分です。
議論の流れや結論をまとめることが重要であり、1番時間を使った方が良いフェーズです。
よくある失敗例は、議論に熱が入りすぎて、肝心のまとめが疎かになってしまい論理性や独自性が欠落してしまうパターンがあります。
自分達なりのアイデアに論理性を持たせながら説明することが重要になります。
⑦発表
最後に「発表」です。
グループディスカッションは、必ず「発表」があります。
当然ですが、最終的な発表が良くなければ、グループ全体の評価が下がってしまうことになります。
たとえ、優れた議論ができていても発表でつまづくグループがたくさんあります。
「このチーム、議論は良かったんだけど、アウトプットがつまらないよね、、」
と言われないようにしましょう。
最後の最後でつまづかない為には、冒頭の「時間配分」が重要なポイントになります。
やっぱり「時間配分」をミスると取り返しがつかなくなりそうですね
そうなんですよね。時間配分を軽視する人がいるけど、限られた時間で答えを出さないといけないグループディスカッションでは、想像以上に重要だね。
【詳細解説】おすすめのグループディスカッションの時間配分

ここまでグループディスカッション全体の流れを見てきました。
冒頭でご紹介したオススメの時間配分について、さらに詳しくポイントや要点をご紹介していきます。
20分の場合
まずは20分の場合は、以下の配分がオススメです。
①自己紹介、役割決め、時間配分:1分以下
②定義付け、アイデア出し:8分〜10分
③アイデアを整理:2分〜4分
④発表準備:4分〜5分
ポイントは以下の3点です。
【全体時間20分のポイント】
・「①」の時間配分までは1分以下で決めること
・「②」議論の中心に1番多く時間を使うこと
・「④」発表準備に最低限の時間を確保すること
20分の場合、グループディスカッションの時間は想像以上に早く終わってしまいます。
「え、もう20分終わった?」
という事態が何度もありました。
全体時間が20分の場合は、何事も手短にどんどん進めていくことが大切です。
例えば、自己紹介や、役割決めは、何なら着席した瞬間から始まっているようなものです。
全体が始まる前に手短に自己紹介を済ませておけば、時間短縮も可能です。
全体時間20分の場合は、とにかく時間短縮が必要です。
後々に必ず時間が足りなくなるからです。
また、グループディスカッションの中心は「議論」です。全員で議論する時間を1番多く確保するようにして、オリジナリティの高いアイデアや考えをアウトプットできるようにしましょう。
最後に、発表準備にも最低限の時間を確保しておくことが重要です。
議論が熱くなりすぎて、発表する内容が決まっていませんでした....という状態にならないように時間配分でリスクヘッジをしておきましょう。
30分の場合
続いて30分の場合は、以下の時間配分がオススメです。
①自己紹介、役割決め、時間配分:2分以下
②定義付け、アイデア出し:15分〜18分
③アイデアを整理:3分〜5分
④発表準備:2分〜4分
ポイントは以下の2点です。
【全体時間30分のポイント】
・「②」議論の中心となる定義付け、アイデア出しに多くの時間を確保する
・「④」発表準備は、発表時間が変わらない限りおよそ2分〜4分でOK
繰り返しになりますが、グループディスカッションの中心は「議論」です。
チームでより良いアイデアが出るように、議論の時間を1番多く確保しましょう。
また発表準備は、発表時間が変わらない限りは、そこまで時間を変える必要はありません。
発表時間に応じて原稿の分量やスライド量を調整すれば良いからです。
基本的には、2分〜4分の時間を必ず確保しておきましょう。
1時間(60分)の場合
最後に1時間の場合は、以下の時間配分がオススメです。
①自己紹介、役割決め、時間配分:3分以下
②定義付け、アイデア出し:30分〜35分
③アイデアを整理:5分〜10分
④発表準備:5分〜10分
⑤バッファ時間(余白時間):5分以上
ポイントは以下の3点です。
【全体時間1時間のポイント】
・「③」アイデアをまとめる時間を少し多めに確保しておく
・「④」発表時間が多くなる可能性が高いので、発表準備に多めの時間を確保しておく
・「⑤」バッファ時間を最低でも5分は確保しておく
1時間の場合は、議論の時間を半分程度で終わらせ、アイデアをまとめ発表に向けて準備する時間を多く確保しておくことがポイントです。
議論時間が長くなればなるほど、意見のまとまりが悪くなり、発表の精度が落ちる傾向があります。
そのため、バッファ時間(余白時間)も確保しておきながら議論を進める必要があります。
バッファ時間(余白時間)の有無で、心の余裕も大きく変わります。
ギリギリで議論を進めるよりも心に余裕を持った状態で議論した方が、より精度の高いアウトプットができるので、1時間の場合、必ずバッファ時間を確保しておきましょう。
ここで解説した時間はあくまでおすすめの目安であって、このとおりに遂行するのは不可能です!よって参考程度で押さえておいて、その場その場で臨機応変に対応することが最も重要!
グループディスカッションの時間配分で気をつけること【3選】

ここまで、20分、30分、1時間のグループディスカッションでのオススメ時間配分についてご紹介してきました。
続いて、気をつけるポイントを3つご紹介していきたいと思います。
【グルディスの時間配分に関するポイント】
- 時間配分を決めるための時間を使いすぎない
- 時間通りに進まないことを前提にする
- 発表準備にできるだけ時間を取る
①時間配分を決めるための時間を使いすぎない
まず最初のポイントは「時間配分は最小限の時間で決めること」です。
時間配分はあくまでも目安です。グループディスカッションの本題は、全員で議論をしながら少しでもよいアウトプットを生み出すことです。
時間配分を決めるのに、3分以上かかるようなグループは、議論がなかなか始まらず結果的にアウトプットの精度が落ちてしまいます。
もし、グループ内で時間配分がなかなか決まらない状態であれば、本記事でご紹介したおすすめの時間配分を使ってパパッと進めていきましょう。
②時間通りに進まないことを前提にする
続いては、マインド面です。
「時間配分を決めたからには、時間通りに進めないといけない」と時間に固執しすぎるのは、正直、イケてない就活生です。
社会人の仕事とは、常に「想定外」を想定しながら、仕事を進める必要があるからです。
余裕がある社会人と、余裕のない社会人だったら、前者の方がいいですよね。
グループディスカッションでも同じです。
大事な事は、全員で優れたアウトプットを出すことです。
グループディスカッションでも時間通りに進まないことがよくあります。
時間通りに進まないからといって、慌ててはいけません。
大前提「時間通りに進まないのがグループディスカッション」というスタンスで余裕を持って取り組むことが大事です。
③発表準備にできるだけ時間を取る
最後に「発表準備への時間確保」についてです。
グループディスカッションでは、発表準備時間を気持ち多めに確保しておくことが重要です。
多くの場合、グループディスカッション時間は、あっという間に過ぎることが多く「気がついたらあと3分しかない」なんて状況がよくあります。
発表準備を多めに確保し、さらに全体のバッファ時間(余白時間)も確保しておくと余裕を持ってグループディスカッションに取り組むことができます。
「発表が上手くいかない」と悩んでいる人は、通常よりも少し多めの時間を確保して、まとめる時間を長く取るのも良いでしょう。
グループディスカッションは常に時間との戦いなんですね....!
特にグループディスカッションに慣れていない人は「まず時間配分を抑える」だけでも余裕を持てますよ!
【補足】グループディスカッションの時間配分に失敗すると?

この章では、グループディスカッションの時間配分に失敗した場合の最悪の結末をお伝えします。
よくあるのが「結局、案がまとまらず、グタグタな発表で終わる」という失敗です。
例えば以下のような例があります。
【よくあるグループディスカッションの失敗例】
- 発表時間に間に合わない
- 伝えたい要点がまとまらない
- 肝心の議論が表面上で終わってしまう
- 結局、最後に時間が無くなる
というような、様々な状況が散見されます。
つまり「時間配分」は、グループディスカッションの1番重要な部分であり、時間配分を間違ってしまうと最後まで取り返しのつかない状態に陥ってしまう事になります。
時間配分を間違えると取り返しが難しくなるんですね....
時間配分はグループディスカッションで、1番大事な部分なので必ず抑えておきましょう!
グループディスカッションの時間配分に関するよくある質問

最後に、グループディスカッションの時間配分に関係するよくある質問にズバリお答えしていきます。
「時間配分は分かったけど....他にも...?」という人は、是非最後までチェックしていってください。
オンライングループディスカッションの時間配分で気をつけることは?
オンラインでのグループディスカッションの場合は、大きな変化点として以下3点が考えられます。
【オンライングループディスカッションの変化点】
・会話の流れを変えづらい
・全体的に情報量が少ない
・会話を切り出すのが難しい
時間配分をする際にも、上記3点を考慮して「発表準備」に多めの時間を確保するのをオススメしています。
議論内容がなかなかまとまらなかったり、発表する内容が決まらなかったりと、様々な問題が考えられますので、とにかく余裕を持って取り組むことが大切です。
タイムキーパーが時間配分を決めるのか?
続いて「時間配分は誰が決めるのか?」という疑問です。
結論、「司会」もしくは「タイムキーパー」のどちらかが決めてあげるのが親切でしょう。
自己紹介から役割分担が決まった後に、自然な流れで切り出すのがオススメです。
例えば、以下のように切り出します。
「では、僕がタイムキーパーをします。今回は全体の時間が30分なので、定義付けとアイデア出しに15分程度、案のまとめを5分、発表準備を5分、バッファを5分で進めていければと思いますが、どうですか?」
という感じで、スパッと決めるとスムーズに進みます。
時間配分がなかなか決まらない場合はどうする?
続いて「え、時間配分ぜんぜん決まらんやんこのチーム、、」という状態の時についてです。
正直、時間配分で揉める時間が勿体ないので、その際は議論に入りながら、タイムキーパー役が時間配分を頭の中で決めながら、議論を進めることをオススメしています。
グループディスカッションは時間との勝負です。
あっという間に時間が無くなってしまうので、少しでも早く進めれるように準備しておきましょう
想定より時間が余った場合はどうする?
最後に「あ、予想以上に時間が余ってしまった、、、何する?雑談する?」という状態の対処法です。
当然ですが、人事側担当者は話し合いのプロセスを見ています。
時間が余ったからと言って関係のない雑談をしていれば、間違いなくマイナスイメージを持たれてしまいます。
時間が余った時のオススメ方法は「想定される質問の回答を作っておく」です。
発表後は、他チームや人事担当者からの質問タイムがあります。自分達の案に対して、鋭い質問が飛んできた時に備えて、回答を準備しておきましょう。
しかし、他の人が雑談タイムに入ってしまうケースも想定できますよね。
そんな時は「〇〇という質問がきたらどうする?△△といった考えもあると思うけどどう思う?」という感じで会話を切り出すのがオススメです。
人事担当者側からも「あ、この人は準備力があるな」と良い評価をもらうことができます。
グループディスカッションの時間配分はセオリーが超重要!

さて、ここまでお疲れ様でした!
グループディスカッションの時間配分について、何も知らなかった人でも本記事を読めば「グループディスカッションのセオリー」を把握することができたことでしょう。
グループディスカッションでは「知っている」と「知らない」には大きな違いがあります。
時間配分を完璧に抑えることで、その後の議論→発表までをスムーズに乗り切ることができます。
一方で、時間配分をミスると取り返しのないミスとなり、イケてない発表しかできず何とも言えない雰囲気になります。
「グループディスカッション時間配分のセオリー」を抑えて、就活第一関門を突破していきましょう!
▼合わせて読むべき記事







